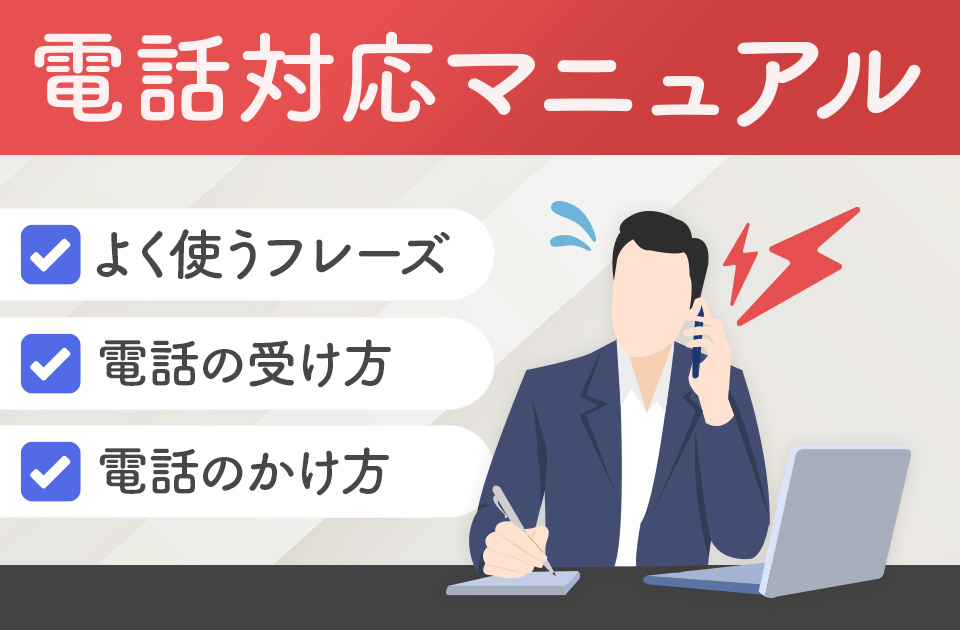年末調整の書き方マニュアル!提出期限を過ぎた場合はどうする?

毎年、年末になるとやってくる年末調整。提出書類が多く手間のかかる年末調整ですが、なるべくスムーズに作業を進めて気持ち良く年末を過ごしたいものです。
そこでこの記事では、年末調整について重要なポイントを理解し、年末調整を少しでもスムーズに行っていただけるよう徹底解説します。年末調整に関する基礎知識から、今年の変更点や具体的な年末調整の方法、よくあるトラブルまでご紹介。年末調整は、すべての従業員にとってとても重要な手続きです。年末調整の担当者の方だけでなく、従業員の方もぜひご覧ください。
※年末調整の提出が間に合わずお困りの方はこちらをご覧ください。
目次
年末調整とは
毎年必ず行う必要のある年末調整ですが、その必要性や対象者についていま一度しっかりと確認しておきましょう。
年末調整
年末調整とは、従業員が1年間納めてきた所得税と実際に納めるべき所得税の差額を計算し、年末にまとめて清算する業務のことです。企業は毎月の給与を支払う際、源泉徴収税額表によって所得税および復興特別所得税を源泉徴収しています。つまり、給与は所得税が引かれた状態で支払われています。
しかし、企業が源泉徴収した所得税の1年間の合計額は、本来年間に納めなければいけない税額と一致しない場合がほとんどです。
上記の差額が出てしまうことには、以下のような理由が挙げられます。
- 1年の途中で給与額に変更があった場合
- 1年の途中で控除対象扶養親族の数に変更があった場合
- 生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除が必要
源泉徴収税額表は年間を通して毎月の給与に変更がないものとして作成されているため、1年の途中で給与額に変更があった場合は差額が生じます。
(参考)国税庁|パンフレット・手引 源泉所得税関係 年末調整関係
1年の途中に控除対象扶養親族の数に異動があった場合、異動後の支払分から修正を行いますが、異動前の各月の源泉徴収税額は修正されていないため、必ず差額が生じます。
生命保険料や地震保険料の控除などは年末調整の際に控除されるため、それらの控除を行うと差額が生じます。
年末に年末調整を行い、税額を計算し直すことで、本来納めるべき所得税額が初めてわかります。年末調整では、納めた税額が本来納めるべき税額よりも多い場合は還付し、少ない場合は追加徴収することで差額を清算します。
年末調整はさまざまな書類を用意しなくてはいけないため、多少面倒に感じるかもしれません。しかし、比較的還付を受けられる場合の方が多いため、お金が戻ってくる可能性を考えてポジティブな気持ちで臨みましょう。
年末調整の対象者
会社に勤めている全ての方が基本的に年末調整の対象となりますが、例外的に対象外となる場合もあります。ここでは年末調整の対象となる人と対象にならない人を、詳しくご紹介します。
年末調整の対象となる人(※1)
(1) 会社などに1年を通じて勤務している人
(2) 年の途中で就職し年末まで働いている人
12月以外に行う年末調整の対象者
(3) 年の中途で退職した人のうち、
・本人の死亡により退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除く)
・12月に支給されるべき給与等の支払いを受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)
※令和7年(2025年)3月時点での情報です。
(4) 年の中途で、海外の事業所や支店に異動・転勤したなどの理由で「非居住者※2」となった人
※1(1)~(3)は退職時、(3)は非居住者となったタイミングで年末調整を行う
※2非居住者:日本国内に住所がなく、また1年以上居住の事実がない人
(参考)国税庁|パンフレット・手引 源泉所得税関係 年末調整関係
年末調整の対象とならない人
(2) 年末調整の対象者のうち、災害により被害を受けて災害減免法の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
(3) 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した人で、年末調整対象者の (3)に該当しない人
(5) 非居住者にあたる人(1年を通して海外へ赴任しているなど)
(6) 同じ会社に継続雇用されていない、いわゆる日雇労働の人など
(参考)国税庁|パンフレット・手引 源泉所得税関係 年末調整関係
確定申告との関係性
年末が近づいてくると、年末調整とともに確定申告について考える方も多いと思います。確定申告は年末調整と同じく1年間の所得を計算し、納めるべき税額を算出して差額を調整する手続きのことです。
年末調整は会社が行ってくれますが、確定申告は勤務先での年末調整がない個人事業主や、勤務先での年末調整の対象外となった人などがご自身で行うものです。
また、会社で年末調整の対象となっている人でも、年末調整で申請できない控除があれば確定申告が必要です。ここでは年末調整の対象者が、確定申告も必要となる場合について詳しくご紹介します。
年末調整だけでは補えない控除
確定申告は、年末調整だけでは補えない各種控除を補う役割を果たします。年末調整では以下に示した控除の申請はできません。そのため年末調整を行っている場合も、これらの控除が適用されるためには確定申告が必要です。
医療費控除
申告者もしくは同一生計の家族の医療費が年間10万円を超えた場合、医療費控除の対象になります。ただし総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額等の5%以上となれば医療費控除の対象になります。
寄付金控除
ふるさと納税を含め、ある特定の団体(国や地方自治体、日本赤十字社など)に寄付をした場合、寄付金額から2,000円を引いた金額を控除できます。
災害や盗難被害による雑損控除
災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合、損失の一部を所得から差し引き一定金額の控除を受けることができます。ただし、詐欺や恐喝による損害は控除の対象となりません。
住宅ローン等の適用初年度の減税控除
住宅借入金等特別控除として、個人が住宅ローン等を利用し住宅の新築、取得、または増築等をした場合、それらにかかわる住宅ローン等の年末における残高を基準として、一定金額を控除できます。適用初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
年末調整を行えない場合
個人事業主や年末調整の対象から外れた人は正確な納税が行えないため、必ず確定申告を行わなければいけません。また、副業や2つ以上のアルバイトをしており掛け持ちで働いている場合は1ヶ所の勤務先でしか年末調整が行えないため、年末調整を行っていない勤務先での収入に関しては確定申告を行う必要があります。
年末調整を修正する場合
その年の年末調整の期限は、翌年の1月31日となっています。年末調整に不備があった場合、期限前であれば修正して再提出することができますが、期限を過ぎた場合は修正のための確定申告をする必要があります。
そのため、会社で年末調整を行った場合でも、年末調整の期限後に不備が発覚した場合、個人での確定申告が必要です。無駄な工程を増やさないためにも、年末調整の提出書類は正確に記入しましょう。
年末調整に必要な書類
年末調整ではさまざまな書類を取り扱います。ここではそれらのうち、会社に提出する書類についてご紹介します。基本的には会社が税務署から必要書類の配布を受けるため、従業員ご自身で準備する必要はありません。もし書類が必要になった場合は、国税庁のホームページからダウンロードして取得できます。
▶国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)」
扶養控除等(異動) 申告書

出典:国税庁「《記載例》令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例」
扶養控除は、扶養家族の人数に応じて金額の決まる控除のため、この申告書で扶養家族について申告をする必要があります。扶養家族がいない場合でも提出は必須です。
詳しくは国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」をご確認ください。
配偶者控除等申告書

出典:国税庁「《記載例》令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
配偶者控除等申告書(給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書)は、年末調整においてその年の基礎控除、配偶者(特別)控除、および定額減税、所得金額調整控除を受けるための申告書です。これは全ての給与取得者が提出しなくてはならない申請書ではなく、年末調整において配偶者控除等を受けたい人のみが提出する申告書です。
詳しくは国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」をご覧ください。
※令和7年(2025年)3月時点での情報です。申告書の様式は変更される可能性があります。
保険料控除申告

出典:国税庁「《記載例》令和6年分給与所得者の保険料控除申告書」
給与所得者が生命保険や地震保険などの保険料、または社会保険の保険料などを支払っている場合、保険料の控除を受けられます。これも、全ての給与取得者が必ず提出すべきものではなく、年末調整において保険料控除を受けたい人のみが提出する申告書です。
詳しくは国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」をご確認ください。
源泉徴収票

出典:国税庁「令和6年分源泉徴収簿」
源泉徴収票とは、会社から支払われた給料の総額と納めた所得税の金額を記載した書類です。基本的に会社が作成してくれますが、年の途中で退職した場合に受け取りが必要です。
年内に再就職する際は、再就職先の会社で年末調整をするため、これまで働いていた会社から源泉徴収された税額が記載された源泉徴収票を受け取り、再就職先の会社に提出しましょう。
また、再就職せず退職後に収入がない場合も確定申告において源泉徴収票が必要となるため、必ず会社から源泉徴収票を受け取りましょう。
税務署や市区町村に提出が必要な書類
年末調整では、従業員から集めた書類をもとに会社が税務署や市区町村に法定調書を提出する必要があります。年末調整において提出が必要な書類を5つご紹介します。
源泉徴収票等の法定調書合計表
出典:国税庁「令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書、不動産の使用料等の支払調書など、法定調書の種類ごとに人数、支払金額、源泉徴収税額など全てをまとめた情報を記載し、税務署へ提出する合計を記載する書類です。翌年1月31日までに給与等の支払者が手続きを行う必要があります。
詳しくは国税庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」をご確認ください。
源泉徴収票
「年末調整に必要な書類」でもご紹介したように、源泉徴収票とは会社から支払われた給料の総額と納めた所得税の金額を記載した書類で、税務署と給与取得者へそれぞれ提出が必要です。こちらも翌年1月31日までに給与等の支払者が手続きを行います。
支払調書
支払調書とは、給与以外に報酬や使用料などを支払った場合に、それに対する源泉徴収税額を記載する書類です。こちらも翌年1月31日までに提出する必要があります。
給与支払報告書

出典:八王子市「令和7年度(6年分)給与支払報告書【個人別明細書】」
給与支払報告書とは、従業員の居住している市区町村に対して提出する書類です。内容は源泉徴収票とほぼ同一で、市区町村ではこの書類に基づき住民税を課すため、地方税法第317条の6「給与支払報告書等の提出義務」により提出が義務付けられています。
提出を怠った場合、会社や担当者が1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまうため、提出忘れがないよう十分に注意しましょう。
年末調整の最新の傾向と変更点
令和7年度税制改正により、令和7年分の年末調整からは様々な変更がある見込みです。税制改革の内容は多岐に渡りますが、中でも年末調整に関係する変更点は以下の5点です。
基礎控除、および給与所得控除の最低額の引き上げ
令和7年より年間所得2,350万円以下の個人の場合、基礎控除が48万円から58万円に引き上げられます。それに従い、給与所得控除の最低額も55万円から65万円に引き上がります。これまで、給与収入の非課税限度額は「103万円の壁」と言われてきました。しかし今後はそれも「123万円の壁」に変わります。
(参考)財務省「令和7年度税制改正の大綱」
特定親族特別控除(仮称)の新設
特定親族特別控除とは、合計123万円以下の所得があり、居住者と生計を同じくする19歳以上23歳未満の親族(居住者の配偶者や青色事業専従者、控除対象扶養親族ではないこと)に対する控除です。所得がある大学生を有する世帯などに対し、経済的負担を軽減する目的で新設されました。
これまでは子供の年収が103万円を超えると、親は扶養控除の適用外になっていました。しかし、基礎控除と給与所得控除の引き上げで扶養控除の最低年収が123万円まで引き上がるほか、年収123万円を超えても特定親族特別控除が適用され、年収150万円までは扶養控除の満額と同等の63万円の控除になります。また150万円を超えても、188万円までは収入に応じた控除が適用されます。
この変更により、令和7年分からの年末調整では申告書の新しい様式への対応や、給与システムなどへの新しい控除区分追加などの作業が発生すると予想されます。
(参考)財務省「令和7年度税制改正の大綱」
ひとり親家庭や勤労学生の所得要件の引き上げ
基礎控除および給与所得控除の最低額引き上げや、特定親族特別控除の所得要件変更に従い、関連するさまざまな所得要件も変わりました。同一生計配偶者および扶養親族、ひとり親家庭の子供の合計所得金額要件は現行の48万円から58万円以下に、勤労学生の所得要件は現行の75万円から85万円以下に引き上がります。それにより、これまで控除の対象でなかった人も控除が適用される場合があります。
(参考)財務省「令和7年度税制改正の大綱」
子育て世帯における生命保険料控除についての見直し
23歳未満の扶養親族を持つ居住者に対し、令和8年分における一般生命保険料控除が最大2万円まで上乗せされることになりました。控除される金額は、保険料により変わります。具体的な控除金額は以下の通りです。
- 年間の新生命保険料 30,000円以下 ・・・新生命保険料の全額
- 30,000円超60,000円以下 ・・・新生命保険料×1/2+15,000円
- 60,000円超120,000円以下 ・・・新生命保険料×1/4+30,000円
- 120,000 円超 ・・・一律60,000円
旧生命保険料とあわせてこの制度で新生命保険料を支払った場合、 一般生命保険料控除の適用限度額は6万円です。また、個人年金保険料控除全体の合計適用上限額は現行の12万円から変更はありません。
(参考)財務省「令和7年度税制改正の大綱」
子育て世帯における住宅ローン控除等優遇措置の継続
令和6年には、子育て世帯や若夫婦(40歳未満の配偶者を有する者や19 歳未満の扶養親族を有する者)の住宅取得支援を目的に、住宅ローン控除の借入限度額上乗せ措置が行われました。この優遇措置が令和7年まで延長されます。具体的には認定住宅の借入限度額が4,500万円から5,000万円に、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅は3,500万円から4,500万円に、省エネ基準適合住宅は3,000万円から4,000万円に上乗せされました。省エネ効果の高い住宅ほど、上乗せ額も高くなっています。
また、子育て対応改修工事を行った場合、250万円を限度として工事費の10%をその 年の所得税から控除できる優遇措置も延長されました。
ほかにも令和7年度の税制改正では、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額引き上げや、確定拠出年金(DC)一時金の重複排除期間が4年以内から9年以内に見直されるなど、様々な変更が行われています。年末調整に影響がある場合もありますので、詳しくは財務省の「令和7年度税制改正の大綱」を確認し、必要な準備を整えておきましょう。
年末調整のしかた
従業員の場合
会社から渡された必要書類に必要事項を記入し、控除証明書などの交付を受けてそれらと一緒に勤務先へ提出します。
-
<事前に用意する書類>
- 保険料控除証明書
- 源泉徴収票
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書
- 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
→保険会社、金融機関などから書面を受領します。
→その年に転職した場合は、前の職場が発行する源泉徴収票を受領しておいてください。
→国民年金機構から発送されるものを使用します。
→住宅ローン控除申請の際、ローンを利用した金融機関に発行してもらいましょう。
→住宅ローン控除のための確定申告を行った年の10月頃に、税務署から9年分まとめて郵送されてくるものを使用します。
年末調整の担当者
(1)11月下旬までに従業員へ必要書類の配布と回収
まずは10月下旬頃から必要書類を従業員へ配布し、11月下旬頃までには回収しましょう。従業員へ配布し、回収する書類は以下となります。詳しくは「年末調整に必要な書類」をご覧ください。
-
<全員必要>
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
<該当者のみ>
保険料控除申告書と控除証明書類
配偶者控除等申告書
住宅借入金等特別控除申告書
(今年転職してきた人は前職場の)「源泉徴収票」
(2)11月下旬~12月下旬頃に回収書類のチェックと年末調整の計算
書類を回収したら、記入漏れや記入ミスの有無をチェックします。その後、年末調整の計算を行い、源泉徴収票にまとめます。
(3)1月31日までに法定調書の作成と提出
以下の法定調書を作成し、年末調整の期限である1月31日までに提出を完了し源泉徴収税の納付を行います。提出が必要な書類の詳細は、「税務署や市区町村に提出が必要な書類」をご覧ください。
- 源泉徴収票等の法定調書合計表
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 給与支払報告書
年末調整の電子化
令和2年分(2020年分)の年末調整から、年末調整の電子化に向けた施策が実施されています。年末調整の煩雑な手続きを省略できるのが利点で、特に国税庁の年末調整控除申告書作成用ソフトウェアでは、より使い勝手がよくなるよう、入力ミス予防措置の追加や動線の改善といった変更が随時加えられています。
ここでは年末調整を電子化するメリットと、電子化によって変わる手続き内容を解説します。
▶参考:国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
電子化のメリットとは?
従業員のメリット
従業員のメリットとしては、手書きによる記入(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、年末調整の申告書作成が簡単になります。また、控除の証明書等を紛失した場合、これまでは発行元の機関に書類の再発行依頼が必要でしたが、電子化によって再発行の手間を省けます。
会社側のメリット
電子化によって控除額の自動計算ができ、各従業員の控除額の検算が不要になります。また控除証明書等もデータ化することで、確認作業を削減できます。記入漏れや記載ミスに関する問い合わせ件数の減少や、書類保管コストの削減なども期待できるでしょう。
電子化するための事前準備
年末調整を電子化する際は、事前準備が必要です。ここでは年末調整電子化のための具体的な事前準備について、ご紹介します。
(1)年末調整ソフトウェアの検討
電子化を実施するにあたり、複数提供される年末調整ソフトウェアから、使用ソフトウェアの選定について検討します。企業が販売するソフトウェアのみならず、国税庁が提供する年末調整控除申告書作成用ソフトウェアもあります。
(2)従業員への周知
年末調整の電子化にあたり、控除証明書等の電子データ取得を促すため従業員に早めの周知が必要です。マイナポータル連携により電子データの取得が可能ですが、マイナポータル連携が難しい場合は保険会社等のホームページから取得してもらいましょう。また、電子化にあたり使用するソフトウェアも周知し、個別に取得してもらいましょう。
(3)給与システムの見直し
年末調整のソフトウェアでは、従業員から提供されたデータを現在利用中の給与システム等にインポートし、年税額等を計算します。必要に応じて、自社の給与システムの改修を行いましょう。
こんなときどうしたらよい?
年末調整を行う際、資料を読み込むだけでは判断の難しい状況がいくつかあります。そこで、国税庁の「年末調整Q&A」の中からよくある質問を抜粋してご紹介します。
月分の給与を翌月支給する場合はいつまでが対象になるのか
給与規定により、毎月1日から末日までの給与が翌月に支給される場合があると思います。12月分の給与は1月に支給されますが、年末調整の対象は年内に支払いが確定した給与であり、「支払いの確定日」は実際に給与が支給された日を指します。このため、1月に支給される12月分の給与の金額は年末調整に含まれません。1月に支払う12月分の給与は、翌年の年末調整に含める必要があります。
年末調整のよくあるトラブル
手順通りに年末調整を進めていても、回避できない問題が発生することがあります。年末調整のよくあるトラブルと解決方法を知ることで、スムーズに手続きを行いましょう。
その年の途中に転職してきた人がいる
一番トラブルになりやすいのが、その年の途中に転職してきた人がいる場合です。その年の途中に転職してきて年末まで働く場合、転職先企業(現職場)がその人の年末調整を行います。
しかし転職してきた人が前職場で発行された源泉徴収票を提出してくれない場合や、間違えて前年分の源泉徴収票を提出する場合があるため、注意しましょう。
また、海外の会社から退職金を受け取った場合や、前職の退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合などは、従業員個人で確定申告しなければならないため、必ず確認してもらってください。
期限に間に合わない
年末調整の期限は1月31日となっていますが、従業員の書類提出や、確認作業の遅れなどにより、提出が間に合わなかったとしても特に罰則は課せられません。
数日の遅れの場合は、所轄の税務署に連絡すれば待ってもらえる可能性があります。特定の従業員の書類提出が間に合わなかった場合は、従業員本人に確定申告を行ってもらえば大丈夫です。
しかし、意図的に年末調整を怠った場合は脱税とみなされ、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が課される可能性があります。年末調整は、必ず行いましょう。
記入漏れや変更が生じた
年末調整の書類を提出した後に記入漏れやミスに気付いた場合、提出期限の1月31日までであれば修正できます。期限後にミスや変更が発覚した場合は、該当する従業員に個人で確定申告を行ってもらうことで修正しましょう。
計算ミスによる従業員との金銭トラブル
年末調整で従業員から追加徴収を行うことになった場合、従業員との金銭トラブルに発展する可能性があります。稀に追加徴収を快く思わず、従業員が企業にクレームを入れたり徴収を拒否したりする場合があるのです。しかし、企業がそれに応じる必要はありません。追加徴収分の費用を企業が代わりに支払うと、次回の年末調整がよりややこしくなります。追加徴収の経緯を正直に説明し、納得してもらうようにしましょう。
年末調整にはマニュアルが必要不可欠
会社では、何年も年末調整の業務に従事し、手順を熟知しているベテラン従業員から、新入社員など年末調整に関する知識をほとんど持たない従業員まで、多くの人が年末調整手続きにあたります。それだけに、全員に口頭で手順を説明したり、何度も問い合わせに対応したりすることには多くの労力とコストが必要です。
また、年末調整には毎年変更点があり、昨年の手続きが容易だったとしても、今年は難しくなるなどの可能性もあります。国税庁や会計ソフトのサイトなどで手順が紹介されていますが、企業によって書類の提出期限や提出先、使用するソフトウェアなどが異なるため、自社独自の手順書が必要になります。
従業員が誰でも簡単に理解でき、毎年の変更に対応できるマニュアルを作っておくことがベストでしょう。
マニュアルを利用するメリット
マニュアルに年末調整の手順をまとめることで、テレワーク中の従業員も年末調整を容易に行えます。年末調整の知識を持たない従業員も、手順に沿って記入するだけで年末調整の書類が用意でき、問い合わせの大幅削減も期待できます。
年末調整の電子化が当たり前となりつつある今、手順をマニュアルにまとめて誰がいつどこにいても手続きを行える環境の整備は必須です。
バックオフィス業務の効率化にも有効
年末調整以外に、経理や総務、人事、法務、財務など、書類作成の機会が多いバックオフィス業務においても、マニュアルは有効です。書類作成の問題点は、記入ミスや記入漏れなどによる書類の修正や問い合わせ対応です。ミスを事前に防ぐため、書類作成時の細かな注意点を手順とともにマニュアルにまとめることで、バックオフィス業務の効率化が期待できます。
まとめ
年末調整の基礎知識や新たな変更点、各種手続きの具体的な手順やよくあるトラブルまでご紹介してきました。毎年多くの確認が必要で、決まった時期に担当者の負担が大きくなってしまう年末調整ですが、事前の対策しだいでより効率的に手続きを行えます。早めに電子化を進めるとともに、マニュアルを活用することでさらなる効率化を進める工夫をしましょう。