電話対応マニュアル|電話の受け方・かけ方、よく使うフレーズの例文を紹介
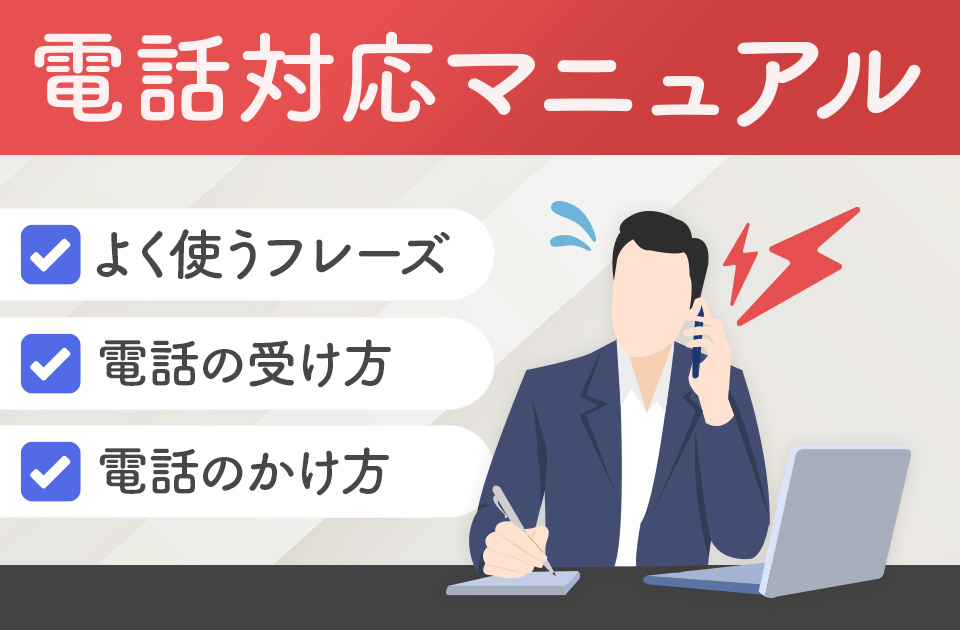
電話対応は、取引先や消費者と信頼関係を築く入り口となる業務であり、そこには習得しておくべきビジネスマナーが多々詰まっています。本記事では、電話対応の基本やよく使うフレーズの例文を紹介します。社内研修や新人教育マニュアルの作成にぜひ役立ててください。
【お問い合わせ対応に追われている方必見】お問い合わせの数を50%削減する方法を解説!
目次
ビジネスでの電話対応の基本
ビジネスシーンにおける電話対応は、会社全体の印象を左右する業務と言っても過言ではありません。基本的なビジネスマナーが備わっていない新入社員に丸投げしてしまうと、取引先や消費者からの信頼を損なうおそれがあります。丁寧な対応で好印象を与えるためにも、まずは電話対応の基本を押さえておきましょう。特に重要なポイントは以下の3つです。
メモ・筆記用具を準備しておく
メモと筆記用具は常に手元に準備しておきましょう。通話中に相手から聞いたことをすぐにメモできる状態にしておくことで、聞き漏れや勘違いを避けられます。記載すべき内容は、「日時・相手の企業名・担当者名・連絡先・用件」などの基本情報です。
聞き漏れがあると、確認のために手間がかかる上、相手からの信頼を損なう原因になります。用件にかかわらず、電話を受ける際は「必要な情報を必ず記録する」習慣を身につけましょう。また、内容を何度も聞き直すことは相手に余計な負担をかけるため、情報を正確に記録する姿勢が欠かせません。
取引先企業名や担当者などを把握しておく
取引先企業や担当者の情報を事前に把握しておくと、会話をスムーズに進めやすくなります。たとえば「A社の〇〇さんは、FAX受信の確認でよく電話をかけてくる」という前情報があれば、電話を受ける時に用件をすぐに理解でき、迅速な対応が可能になります。また、手元に準備しているメモに、相手の名前やよくある用件などを記載しておくと、会話中にうっかり名前を間違えてしまうといったミスを減らせます。
相手が自分から名乗らない場合は、「失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」と丁寧に確認します。所属と名前をきちんと確認することで、失礼なく会話を進められます。やり取りの機会が多い取引先企業や担当者の情報は社内で情報共有し、どの従業員が電話を受け取ってもスムーズに対応できるように準備しておくと効率的です。
ビジネス電話でよく使うフレーズを把握しておく
電話対応をスムーズに行うためには、状況に応じた適切な言葉遣いやフレーズの習得が不可欠です。ビジネスシーンでは「もしもし」は使用せず、「はい、〇〇(会社名)でございます」と名乗るのが基本です。相手を待たせる際は、「少々お待ちください」などとクッション言葉を用いることで丁寧な印象を与えられます。
取り次ぎや折り返しが必要な場面では、「恐れ入りますが」「お手数ですが」といったフレーズを活用すると相手への配慮が伝わります。ビジネスシーンでの対応に不慣れな新入社員の場合、家族や友人との電話のような言葉遣いを無意識に使ってしまいがちです。よく使う言葉遣いとフレーズを事前に習得しておくことで、落ち着いて電話対応しやすくなります。
電話対応マニュアル:電話を受ける時
電話を受ける時は、迅速かつ的確な対応を徹底することで取引先企業との信頼関係を構築・維持しやすくなります。会話中の言葉遣いはもちろん、取り次ぎや電話の切り方などの細かな点まで気を配りましょう。電話を取るタイミングから会話中の対応の仕方、電話の切り方までを流れに沿って解説します。
1. 3コール以内に電話を取る
電話のコール回数は、相手を待たせた時間の目安になります。3コールを超えると失礼な印象を与えかねないため、別の作業をしている場合も一度手を止め、速やかに電話を取るように心がけましょう。電話が鳴ったらすぐに出る習慣を身につけることで、対応の遅れを防げます。
事情によって電話を取るのが遅れてしまった場合は、「大変お待たせしてしまい申し訳ございません。〇〇(会社名)でございます」と最初に一言添えましょう。相手を待たせてしまったことを最初に謝罪してから会話を始めると、丁寧な印象を与えられます。
2. 自社名や電話を受けた自身の名前を伝える
電話に出る際は、まず会社の代表として社名を名乗り、その後に自分の部署名や名前を伝えるのが基本です。所属を自分から明かすことで信用度が高まり、相手は安心して用件を伝えられます。「はい」「もしもし」などの応答だけでは、確認のやり取りで相手に余計な手間をかけてしまうため、最初に自分から社名や名前を伝えるようにしましょう。
会社によっては、個人名ではなく部署名やチーム名を名乗るようにルール化されている場合もあります。たとえば「お電話ありがとうございます。株式会社〇〇の■■係でございます」と最初に名乗れば、確認の手間が省けてスムーズです。
3. 相手の社名や担当者名、用件を復唱しながらメモする
電話応対している時は、相手の社名・氏名・用件などを正しく聞き取り、復唱しながらメモを取るのがポイントです。復唱することで聞き間違いを防ぎ、「正確に伝わっている」という安心感を相手に与えられます。万が一聞き取れなかった場合は、自分で勝手な解釈をせず、その場ですぐに正確な情報を聞き直すことが大切です。
話を聞きながらメモを取る際は、「5W1H」を意識するのが効果的です。「When(いつ)・Where(どこで)・Who(誰が)・What(何を)・Why(なぜ)・How(どのように)」を意識してメモを取ると、用件を正確に記録できます。
4. 対応や他の担当者に取り次ぎが必要な場合は保留ボタンを押す
相手の用件によっては、自分では判断できない場合や、他の担当者への取り次ぎが必要な場合があります。その際には相手に保留にする旨を伝えた上で、保留ボタンを必ず押してから対応にあたります。何も言わずに保留にし、相手を放置するのは失礼にあたります。
相手に保留を伝える時には「すぐに確認いたしますので、少々お待ちください」「ただいま担当の〇〇に代わりますので、少々お待ちいただけますでしょうか」などと一言添えます。どのような目的で保留が必要なのかをきちんと伝えることで、待たせる相手に安心感を持ってもらえます。
5. 保留を解除し、状況を伝える
保留を解除したタイミングで「大変お待たせいたしました」と一言添えてから、状況を説明します。たとえば担当者が不在の場合は「戻り次第、こちらから折り返しご連絡いたします」と伝えることで誠意が伝わります。担当者が在席している場合には、「ただいま担当の〇〇に代わります」と告げてから受話器を渡します。不安を与えず円滑に対応を進めるには、相手に状況を丁寧に説明することが大切です。
6. 相手が受話器を置くのを確認してから電話を切る
電話を切る時は、相手が受話器を置いたのを確認してから静かに切るのがマナーです。相手よりも先に電話を切ってしまうと「話を打ち切られた」と感じたり、耳元で“がちゃり”と切る音が聞こえて不快にさせてしまったりするおそれがあります。
受け手は話が終わったと勝手に判断せず、最後まで相手の行動をよく確認してから電話を切りましょう。電話をかけた側は何かしらの用件があって連絡しているため、「話を終えるタイミングを決めるのもかけた側にある」と捉えておくと、意識付けた行動につながります。
7. 社内関係者に情報共有が必要な場合はメモをまとめる
担当者が不在の場合や引き継ぎが必要なケースでは、メモを作成して社内関係者に情報共有しましょう。先にも紹介した通り、記録の際は「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」を意識することで、簡潔かつ正確に情報を整理できます。たとえば「いつ誰から、どのような用件で電話があったのか」を詳細に記録しておくと、担当者がスムーズに対応可能です。
情報共有を怠ると、対応の遅れや誤解を招くリスクがあります。場合によってはクレームに発展するおそれもあるため、不確実な口頭での情報伝達は避け、メモをまとめるように心がけましょう。
電話対応マニュアル:電話をかける時
こちらから架電する場合においては、事前にしっかりと準備をしてから行動できます。相手の情報確認やかける時間帯の配慮などを意識し、相手に失礼なくスムーズに用件を伝えましょう。ここでは、ビジネスシーンで電話をかける時のマニュアルを流れに沿って紹介します。
1. 相手先企業の担当者名や用件を先にまとめておく
電話をかける前に、相手の情報を必ず整理しておきます。担当者名や部署名を正確に把握しておくことで、取り次ぎがスムーズになり、余計な時間を取らせずに済みます。会話中にうっかり相手の名前を間違えてしまう失敗を避ける意味でも、事前の確認は非常に重要です。
また、電話で伝える用件をメモにまとめておけば、伝え忘れや説明の漏れを防止できます。確認のために何度も席を離れたり、電話のかけ直しで余計な時間を取らせたりするのは相手に対して失礼です。1度でスムーズに用件を伝えられるよう、入念な準備をしてから電話をかけましょう。
2. 相手先に失礼のない時間帯に電話をかける
電話をかける時は、時間帯にも十分な配慮が必要です。始業直後や終業間際は、業務開始の準備や片付けで忙しくしている可能性があります。電話が業務の妨げになってしまうため、避けるようにしましょう。また、正午~13時頃の昼休みの時間帯での電話も、相手の休憩を中断してしまうリスクがあります。
電話をかけるタイミングは、始業してから少し業務が落ち着く午前10時以降や、終業までまだ余裕のある午後の早い時間帯が適切です。相手の事情に配慮した時間選びを心がけることで、ビジネスマナーの向上につながります。どうしても相手の忙しい時間帯に電話をかけなければならない場合は、最初に「お忙しい時間に申し訳ございません」「お昼時に大変失礼いたします」などとお詫びの言葉を伝えましょう。
3. 自社名や名前、用件を伝える
電話が繋がったら、まずは自分の会社名と名前を名乗りましょう。その後、相手の担当者に取り次いでもらうよう依頼します。用件は結論から先に伝えるのがポイントです。たとえば「〇〇の件でご連絡いたしました」と伝えると、内容を相手に理解してもらいやすく、取り次ぎがスムーズになります。
また、用件を伝える前に、相手の状況を確認する配慮も大切なマナーです。いきなりこちらの用件を伝えるのではなく、「〇〇の件でご相談したいのですが、今お時間よろしいでしょうか」と一言添えると丁寧な印象を与えられます。
4. 相手先の担当者が不在の場合は伝言などを依頼する
担当者が不在の場合は戻り時間を確認し、「改めてこちらからお電話いたしますので、その旨をお伝えいただけませんでしょうか」などと伝言を依頼しましょう。その際は、自分の会社名・名前・連絡先を正確に伝えることが重要です。情報に誤りがあれば、電話をかけ直す際に、再度自分の所属や名前を詳しく相手に説明しなければならない手間がかかります。
相手からの折り返しを希望する場合は、「お戻りになりましたら、お電話いただけますようお伝えください」と伝えましょう。丁寧な表現を心がけることで、相手に失礼なくスムーズな連絡を促せます。
5. お礼を伝え受話器を静かに置く
電話を終える際には、時間を割いてくれた相手に感謝の気持ちを伝えるのがマナーです。「お時間をいただきありがとうございました」などと丁寧にお礼の言葉を述べてから電話を切りましょう。電話は基本的にかけた側が先に切るのがマナーですが、相手が取引先や消費者の場合は例外です。こちらから一方的に終わらせるのではなく、先に相手が電話を切るのを確認してから受話器を置きましょう。
受話器を置く際は、乱暴な印象を与えないよう極力音を立てないようにするのがポイントです。フックスイッチ(受話器を置く部分にある突起)が付いている電話機であれば、指で長押しすると音を立てることなく通話を終了できます。
よく使う電話対応フレーズの例文
ビジネスシーンで電話をかける時は、状況に応じて適切なフレーズを使い分けると好印象かつスムーズに対応できます。とっさの場面でも失礼のない対応ができるように、クッション言葉や担当者が不在時の言い回しをあらかじめ押さえておくと安心です。ここでは、電話対応でよく使うフレーズの例文を状況別に紹介します。
電話対応中によく使うクッション言葉の例文
ビジネスシーンでの電話では、相手に柔らかい印象を与える「クッション言葉」が便利です。直接的な表現を避けつつ、配慮を示すことで丁寧な対応につながります。
-
尋ねる時/提案する時
- 「失礼ですが、~」
- 「差し支えなければ、~」
- 「よろしければ、~」
- 「恐れ入りますが、~」
- 「お忙しいところ大変恐縮ではございますが、~」
- 「申し訳ございませんが、~」
- 「大変心苦しいのですが、~」
お願いする時
お断りする時
これらのクッション言葉を使うことで、相手に圧迫感を与えずにお願いや確認、断りを伝えられます。とっさの場面でも自然に口から出せるよう、日頃から意識して使う習慣を身につけておくのがおすすめです。
電話を受けたが担当者が不在の場合の例文
「相手から電話を受けたものの、こちらの担当者が不在だった」というケースはよくあります。状況によって、以下のようなフレーズを使い分けましょう。
-
離席中の場合
- 「申し訳ございません。〇〇はただいま席を外しております」
- 「よろしければ、戻り次第こちらから再度ご連絡いたしましょうか」
- 「あいにく、〇〇は別の電話に出ております。後ほど折り返しのお電話を差し上げてもよろしいでしょうか」
- 「申し訳ございません。〇〇は本日すでに退社(退勤)しております」
- 「申し訳ございません。〇〇は本日お休みを頂戴しております。明日折り返しのお電話を差し上げてもよろしいでしょうか」
別の電話に対応中の場合
退社・休みの場合
担当者の不在時は、相手に不便をかけやすい場面です。状況を正確に伝えるとともに、こちらから折り返しや伝言を提案すると、誠意が伝わります。
電話をかけたが相手先の担当者が不在の場合の例文
「用件があって電話をかけたものの、相手先の担当者が不在だった」というのもよくあるケースです。失礼な印象を与えないよう注意しながら、伝言や折り返しを依頼しましょう。
- 伝言を依頼する場合:「恐れ入りますが、〇〇様に伝言をお願いできますでしょうか」
- 折り返しを依頼する場合:「恐れ入りますが、〇〇様が戻られましたら、お電話いただくようお伝えいただけますでしょうか」
伝言や折り返しをお願いする際は、必ず自分の会社名・名前・連絡先を一緒に伝えることが重要です。正確な情報の共有により、相手がスムーズに対応しやすくなります。
相手の声が聞こえづらい場合の例文
電話越しでは、通信環境や声のトーンによって相手の声が聞き取りづらい場合があります。その際も、失礼のないように表現を工夫しながら伝えましょう。
- 声が遠く感じる場合:「申し訳ございません、少々お電話が遠いようです」
- 聞き取れなかった場合:「恐れ入りますが、もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか」
「お声が遠いようです」という表現は、相手の話し方に問題があるかのように聞こえてしまうため避けましょう。「お電話が遠い」と表現することで、声ではなく環境が問題であるように表現でき、相手に不快感を与えずに伝えられます。聞き直す場合も、クッション言葉を添えて丁寧にお願いするのがマナーです。
電話対応を行う際に注意するべき点
電話対応はお互いの顔が直接見えない分、声のトーンや言葉遣いが印象を大きく左右します。相手に不快感を与えないよう、会社の代表者であるとの自覚を持ち、明るく丁寧な声や正しい言葉遣いで対応することが重要です。ここでは電話対応で特に注意すべき3つのポイントを取り上げます。
会社の代表・顔であることを自覚する
役職にかかわらず、電話対応する従業員は会社を代表する存在です。言い換えると、電話対応のマナーひとつで会社全体の印象が決まってしまう場合があります。雑な対応では「電話対応すらできない会社」と受け取られる可能性があるため、会社の顔としてふさわしい対応を心がけましょう。会話の内容はもちろん、言葉遣いや声のトーン、レスポンスの早さなど、細かな点が会社の信用につながります。
普段の会話よりも声に意識を向け、ゆっくりハキハキと話す
電話はお互いの表情や仕草が見えないため、声のトーンや話すスピードが印象を大きく左右します。活発で丁寧な印象を与えられるよう、普段の会話よりもワントーン高めの明るい声を意識しましょう。また、早口では聞き取りづらいため、一語一語を丁寧に、はっきりと発音することも大切です。お互いの顔が見えないからこそ、普段以上に声の明るさと話し方の丁寧さを意識し、相手に好印象を与える必要があります。
言葉遣いやマナーに注意する
ビジネスシーンの電話対応では、敬語を正しく使い分けることが求められます。「もしもし」「了解です」「なるほどですね」などのくだけた表現は避け、尊敬語・謙譲語・丁寧語を状況に応じて使い分けましょう。家族や友人との日常会話で使用するような言葉遣いは、ビジネスの場には適しません。電話対応では、ちょっとした言葉遣いひとつで相手の受ける印象が変わります。相手を不快にさせないためにも、常にマナーを意識した表現を心がけてください。
電話対応用のマニュアルを作成する時のコツ
電話応対のスキルやクオリティについて、従業員ごとの対応力のバラつきを防ぎ、一定の品質を保つためにはマニュアルの作成が効果的です。特に、電話対応に不慣れな新入社員にとっては、わかりやすいマニュアルの有無が業務への適応スピードに大きく影響します。ここでは、マニュアル作成の際に役立つコツを3つ解説します。
自社の電話対応のパターンやスクリプトをまとめておく
行き当たりばったりでマニュアルを作成すると実際の場面で活用できない可能性があります。そのため、まずは自社にかかってくる電話の主な相手や用件を洗い出し、それぞれのケースに対応するスクリプトを用意しましょう。テンプレートではなく、自社の業務に沿った内容にすることで質の高いマニュアルを作成できます。新入社員でもスムーズに対応できるよう、電話の基本的な流れから具体的なセリフまで明記するのがポイントです。また、問い合わせ内容ごとの対応方法を記載しておけば、担当者不在時でもスムーズな対応が可能になります。
電話対応時のFAQなどを用意しマニュアルに検索先を明記する
特に製造業や小売業における電話対応では、取引先や消費者から問い合わせがあることは珍しくありません。そこで、よくある質問や問い合わせへの回答を事前にFAQとしてまとめておく方法が効果的です。実際に質問が寄せられた際に、すぐに的確な回答ができる体制を整えると迅速な電話対応が可能になります。また、社内データベースや関連資料へのアクセス方法やURLをマニュアルに明記するのも有効です。質問に即時に答えられない場合でも、担当者がすぐに必要な情報にアクセスできるため、対応の遅れや混乱防止に役立ちます。
緊急時やクレーム時のエスカレーション先などを明記する
緊急時やクレーム発生時は、迅速かつ適切な対応が求められます。対応が遅れると取引先からの信用低下につながるため、不測の事態が起きた際に誰に繋ぐべきかをマニュアルに明記しておくことが重要です。対応のフローチャートを作成し「誰に・いつ・どのように」報告するかを明確にすれば、担当者が迅速に対応できます。また、緊急時の連絡網を組み込むことで、担当者不在時でもスムーズに連絡が取れるようになり、混乱や対応の遅れを防げます。
【電話対応マニュアルを作成するなら】プロのノウハウ満載の『マニュアル作成の教科書』をダウンロード
まとめ
電話対応は会社の印象や信頼関係に直結する重要な業務です。基本的なマナーと注意点を押さえ、相手に丁寧な印象を与える対応を心がけましょう。
従業員ごとの対応のバラつきを防ぐには、電話対応マニュアルの作成が効果的です。効率良くマニュアル作成するなら、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz(ティーチミー・ビズ)」がおすすめです。テンプレートに沿って文字を入力するだけで簡単にマニュアルを作成でき、動画や音声、写真などの素材を取り込んだ編集も可能です。マニュアルを浸透させるためのトレーニング機能など、さまざまな機能を必要に応じて活用することで自社に合わせたマニュアル作成・運用が実現します。ぜひ導入をご検討ください。











