働き方改革とはなにかを簡単にご紹介!働き方改革の推進に必要なこととは?

2019年に働き方改革関連法案が施行されましたが、一体どのようなものなのか理解できていない方も多いかもしれません。そこでこの記事では、働き方改革とはなにかを簡単に説明しつつ、働き方改革の推進に必要なことやツールについても紹介していきます。
働き方改革について興味があるけれど、難しそうなのでよくわからないという方のために、制度の目的や背景、意義について簡単に解説していますので、ぜひ参考にしてください。
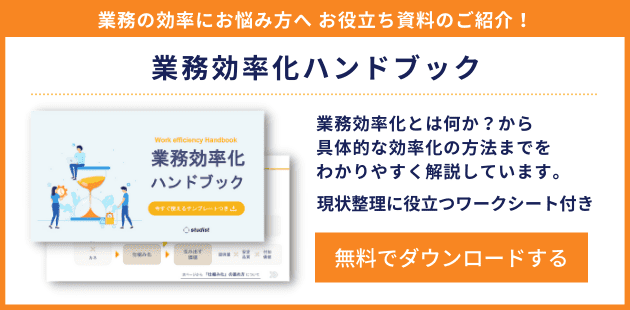
目次
働き方改革とは簡単に言うとどのような改革?
「働き方改革」という言葉は何となく耳にしたことがあるものの、具体的な内容を問われると説明できない方も多いかもしれません。
働き方改革とは簡単に言うと、一億総活躍社会の実現に向けた労働環境改善のための一連の施策です。そのためには、働く人が多様な働き方を選択し、より良い将来を目指す環境の促進が重要です。
働き方改革の背景
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)結果の概要」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳の労働力人口)は、1995年から減少を続けています。少子高齢化の影響を受け、総人口の減少を上回るペースで生産年齢人口の減少が進んでいる点が、特に懸念される問題です。
また総務省統計局が公表している「人口推計-2023年(令和5年)6月報-」によると、2023年6月1日時点での日本の総人口は約1億2,452万人です。しかし、2065年までには約9,159万人、さらに2070年には約8,700万人と減少の一途をたどることが予想されています。
これに対して、生産年齢人口は2020年には約7,509万人ですが、2070年には約4,535万人にまで減少すると予想されている状況です。総人口に対する割合が約50%になるほどの生産年齢人口の減少は重要な問題であり、国全体の生産力や成長力の低下につながりかねません。
その結果、格差が固定化し、世界中が経済発展を遂げる中で、日本だけが経済的に取り残されるリスクが高まっています。
こうした事態を防ぐために「働き方改革」が導入されました。要するに、総人口減少と労働力人口の減少という課題に対して、日本の経済を効率的に維持・発展させる手段としての改革です。
参考:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)結果の概要 令和 3(2021)年~令和 52(2070)年」P7、P9、P10
参考:総務省統計局「人口推計-2023年(令和5年)6月報-」P1
働き方改革の目的
働き方改革の目的は、労働の効率化や多様性の実現、長期間活躍できる社会環境を構築することです。
1.労働の効率化を目指す
昭和の時代には、「モーレツ社員」と呼ばれる価値観が存在しました。同じ成果を出している場合でも、長時間働く社員が短時間働く社員よりも高く評価されるという考え方です。
合理的に考えれば、後者の方が生産性を評価されるべきですが、単に長時間働いていたことだけが理由で前者が評価されていました。このような傾向は現在でも完全には消えておらず、働き方改革の導入後も「モーレツ社員」が存在し、生産性に影響を及ぼしています。
グローバル的な観点から見ると、長時間労働に対するこのような信念は非合理的で奇妙なものです。実際、日本の労働生産性はOECD加盟国の35ヵ国中の22位で、主要先進国である7ヵ国の中では最下位となっています。
働き方改革の枠組みでは、非効率的な長時間労働を是正すべく「労働時間の上限規制」を導入し、36協定の特別条項を見直しています。これにより、以前は事実上制限がなかった残業時間の上限が「年間720時間、月100時間未満、複数月80時間」と定められました。
2.労働の多様性を確保する
従来は、毎日同じ時間にオフィスに出勤し、定時まで勤務して帰るというアプローチが一般的でした。しかしながら、働き方改革の下では、「高度プロフェッショナル制度の導入」や「フレックスタイム制の改訂による清算期間の拡大」などによって、労働時間の柔軟な調整が可能となっています。
同時に、働き方の多様性を確保する目的から、「在宅ワーク」や「テレワーク」などを推進し、毎日オフィスへ通勤する必要がない形で仕事ができる環境を整備してきました。自宅や近くのサテライトオフィスで仕事をできるようにすることは、育児や介護を理由とする離職の防止につながります。
さらに、本業への影響を懸念し制限する会社が多かった「副業・兼業」も2018年に解禁されるなど、多くの変革が実施されました。
このような改革によって、労働者は従来の「オフィスへの出勤と定時までの労働」という固定観念にとらわれる必要がなくなってきています。個々の状況にあわせて、生産性向上が期待される多様な働き方を選択できるようになりました。
3.社会で長期間活躍できる環境をつくる
働き方改革では、社会で長期間活躍できる環境を整備するために、定年後も働く意欲がある高齢者の再雇用を促進しています。これは労働力人口を確保する上で重要な観点です。
また長期間社会で活躍できる環境づくりは、高齢者に限らず女性にも適用されます。従来の働き方では、女性がキャリアを築くためには出産や育児を諦めるケースも多々見られました。その結果、女性の社会進出が進む一方で出生率が低下し、将来的な労働力人口の不足が懸念される事態に至っています。
働き方改革においては、「在宅ワーク」や「テレワーク」、「同一労働同一賃金」の導入により、女性が出産や育児を理由にキャリアを断念せず、また一度離れた後でも社会復帰しやすい環境を整える取り組みを進めています。これにより、男女平等を促進し、最終的に労働力人口の増加にもつながります。
働き方改革はいつから始まったか
働き方改革関連法案はすでに施行されており、2019年4月から「残業時間の上限規制」「勤務間インターバル制度の普及推進」「産業医機能強化」「有給休暇取得の義務化」「高度プロフェッショナル制度の創設」「フレックスタイム制の改訂による清算期間の延長」といった取り組みが進んでいます。
大企業において、2020年4月に「同一労働同一賃金の義務化」がスタートし、2021年4月には中小企業も続くことになりました。また、「中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止」が2023年4月から行われています。
なお、働き方改革関連法案は、「労働基準法」「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」「労働安全衛生法」「雇用対策法」「じん肺法」「労働契約法」「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という8つの法律から成っています。
働き方改革の3つの柱
働き方改革には3つの柱があります。政府が掲げる「一億総活躍社会」を目指し、労働者の生産性向上やワークライフバランスの改善を図るための指針です。
1. 長時間労働の是正
労働時間の是正を通じて、適切な労働時間を確保し、労働者の健康と生産性を向上させる指針です。具体的には時間外労働の制限を厳格化しています。原則として月45時間、年360時間まで(要件を満たせば例外として月100時間未満、年720時間まで)に抑制されました。また、労働者が有給休暇を取得しやすい環境整備も重視されています。
2. 正規、非正規間の格差解消
雇用形態に制限されることなく、労働者の待遇(給与や福利厚生)を同一にする指針です。特に「同一労働・同一賃金」が重要なポイントです。雇用形態のみで待遇を決定するのではなく、業務内容や結果を反映する取り組みが進められています。
3. 多様で柔軟な働き方
多様なライフスタイルに対応できる労働環境を整備し、労働者が働き方を柔軟に選択できるようにする指針です。出社や定時労働にとらわれず、テレワークやフレックスタイムの導入や、高度プロフェッショナル制度への理解と推進といった取り組みが進められています。
働き方改革でなにが変わっていくの?
以下に、働き方改革によって具体的になにが変わるのか、わかりやすく説明していきます。もし「働き方改革は自分に関係ない」と考えているならば、ぜひ参考にしてみてください。働き方改革は、働く人々の立場や視点から進められる取り組みなため、多くの人々に影響を及ぼす可能性があります。
テレワークの普及推進
従来の概念によれば、業務は主にオフィス内で実施されるものでした。そのため、社員は毎日オフィスに出勤する必要がありました。
しかし昨今は、新型コロナウイルスの影響もありテレワークを導入する企業が増加しています。総務省の通信利用動向調査によると、テレワークを導入している企業は5割以上であり、在宅勤務を導入している企業は、テレワーク導入企業のうち9割を超えています。
テレワークの普及により、特定の場所に拘束されることなく仕事を行える社員が増加しました。通勤にかかる移動時間や費用の削減が可能となり、身体的・精神的な負担が軽減されることで生産性向上が期待されます。
厚生労働省と総務省は「テレワーク総合ポータルサイト」でテレワークの導入に資する情報を公開し、セミナーも開催しており、テレワークのさらなる普及に向けた様々な取り組みを行っています。
時短勤務制度や育児・介護休暇制度の整備
従来は、通常8時から17時までの勤務が求められていましたが、制度施行後は8時から15時までなどのように労働時間を調整する短縮勤務制度や、育児・介護休暇制度が広がっています。すでに多くの企業が対応を進めており、今後、さらなる推進が期待される一面です。
育児休暇や介護休暇を取得するのは女性が圧倒的多数でした。しかし、働き方改革では男性の育児休暇にも重点が置かれ、労働者への通知と推進が企業に義務化されています。さらに、2020年10月には新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が、1歳までの育児休業制度とは別に設けられました。育児休業制度も、2回に分けて取得できるようになるなど、男性の育児休業取得を後押しする取り組みが進められています。
フレックスタイム制の導入
働き方改革の導入前より、フレックスタイム制を取り入れている企業は数多くありました。この制度では、社員は定められた総労働時間の範囲内で始業・終業時間を柔軟に調整できます。働き方改革では取り組みの一環として、この調整可能な期間を1か月から3か月へと延長しました。
たとえば、通常の勤務時間が9時から18時である場合、フレックスタイム制を活用すれば、早めに出社して17時に帰宅することが可能です。同様に、1時間残業することで、翌日には1時間早く退勤することができるといった柔軟な運用が可能な制度です。
非正規社員と正社員の格差是正
日本における非正規社員の賃金は、正社員の基準給の約60%に過ぎません。一方、欧米ではこの比率は80%とされており、日本の非正規雇用と正規雇用の間に大きな格差が存在していることがわかります。
働き方改革では非正規社員の待遇改善を目指し、「同一労働同一賃金の原則」が導入されました。この原則は、2020年4月から大企業で適用され、その後2021年4月から中小企業にも拡大されています。
同一労働同一賃金とは、同じ付加価値をもたらす労働に対しては同等の賃金を支払うべきであるという考え方です。たとえば、ベテランの非正規社員が新卒の正社員よりも極端に低い給与を受けている場合、これを是正する必要があります。
長時間労働を改善する36協定の見直し
36協定は、休日労働を実施する際に必ず締結する合意書です。この名称は、労働基準法第36条に基づいています。
従来、36協定では1か月あたりの残業を最大で45時間、1年間における残業を最大で360時間までと制限していました。その一方で、「特別条項」と呼ばれる条件を追加することで、事実上、労働時間を制約なく延長できる一面がありました。
しかし、働き方改革ではその問題を見直し、時間外労働の上限を設定する変更がなされています。この変更により、年間で最大720時間、単月で100時間未満(休日労働を含む)、2か月から6か月の平均で80時間(休日労働を含む)が残業の上限になりました。
同様に、繁忙期において月に45時間(あるいは42時間)を超えて働くことが許容される回数は、年間で最大6回に設定されています。
高齢者の雇用を促進
現在、65歳以上の高齢者の半数以上が引き続き働きたいとの意向を持っていますが、実際にその年齢で働いている人は全体の約20%にとどまっています。労働力人口は減少傾向にありますが、老年人口は2040年までに約4,000万人前後に増加する見込みです。
働き方改革の取り組みの一環として、高齢者の雇用継続や定年の延長支援に加えて、高齢者の雇用マッチングの支援が検討されています。
高齢者の雇用を奨励し、活力あるシルバーパワーを活かすことによって、減少している労働力人口の課題解決が期待される取り組みです。
外国人労働者の雇用を促進
日本の外国人労働者は増加し続けています。2021年には約182万人の外国人が日本で働いていることがわかりました。外国人の雇用がさらに促進されれば、労働力の向上が見込めます。
しかし、以前は外国人が就労できる職種の受け入れが限定され、スキルや資格を持っていても日本人同様には働けませんでした。そこで、働き方改革により受け入れが拡大されました。現在では外国人の雇用を促進する制度が整えられ、より多くの外国人が日本の企業で就労できるようになっています。
なぜ働き方改革に失敗する?企業がつまずく3つの問題点
企業が働き方改革に取り組んだ際には失敗することもありますが、そこには共通する理由があります。単純に勤務時間を短くする施策をとっただけでは失敗する可能性が否定できません。
ここでは、働き方改革が失敗する2つの要因について解説していきます。
労働時間だけ短くし、業務量は減っていない
働き方改革として、単純に「短時間勤務制度」「育児休暇」「フレックスタイム制度」を導入し労働時間を短縮する施策をとった結果、逆に残業時間が増えるということがあります。
単純に労働時間を短くしても、社員一人に与えられた仕事量は変わりません。きちんと現状把握をしないと、早く家に帰ることはできても家で仕事を行い、翌朝早く出社して仕事を終わらせるという悪循環が生まれることもあります。
現在無駄な業務をしていないか、その仕事にかかる時間はさらに短縮できないかなど、業務効率化のための改善をした上で労働時間を短くする施策に取り組まなくてはいけません。
チーム間の連携が悪化している
チームを組むメリットは、チーム内で分担することで業務をスムーズに進められ、生産性の向上が見込める点です。しかし、時短勤務制度やフレックスタイム制の導入によって仕事が属人的になってしまった結果、チーム間の連携が悪くなるという失敗事例もあります。
仕事の属人化とは、ある業務を特定の人が担当していたために、その人がいなくなると業務をどのように進めればいいのかがわからない状態になることです。こうした事態を防ぐには、マニュアル作成により業務の可視化と標準化をすることが重要になります。
「働き方改革すること」が目的になっている
働き方改革はそのものが目的ではなく、よりよい労働環境や生産性の向上、社員の働きやすさの追求などを実現するあくまでも手段です。働き方改革を成功させるためには、なぜその改革が必要であるか、どのようなメリットがあるかを関係者が理解していなければなりません。
単に新しい制度やルールを導入しても、その目的や意義を理解せずに現場が実施することは困難です。成果につなげるためには、説明会やワークショップを通じて、なぜ変革が必要なのか、それがどのような成果をもたらすのかを明確に伝え、関係者の理解を深め、協力しあう必要があります。
「生産性の向上」が働き方改革の鍵
生産性の向上とは、簡潔に言えば「持っているリソースを最大限に活かし、最小の投資で最大の成果を達成すること」です。
生産性の向上は、しばしば業務効率化と混同されます。しかし、業務効率化は業務の「無駄・無理・ムラ」を削減し、時間とコストを節約することを目指すものであり、生産性向上の手段のひとつです。この手段を用いることで、企業の利益増加、社員の給与向上、余暇の創出といった利点が期待できます。
生産性を向上させるための方法は複数ありますが、最初に挙げられるのは「業務の見える化」です。現在の業務を視覚的に表現して問題やボトルネックを浮かび上がらせ、生産性向上のための計画を立てることが重要です。
業務効率化の観点からは、業務の標準化や社員のスキル向上も欠かせません。そのために不可欠なのが「マニュアルの作成」です。マニュアルにより業務の適切な手順を全社員で共有することで、業務効率化に貢献するだけでなく、業務の個人依存を防ぐ効果も期待できます。
「Teachme Biz」が働き方改革におすすめの理由
「Teachme Biz」とは、時間や場所にとらわれずにマニュアルを作成し閲覧できる、クラウド型マニュアル作成ツールです。このツールは、画像や動画、テキストを駆使した「ビジュアルSOP(標準作業手順書、Standard Operating Procedures)」を通じて、テキストだけのマニュアルよりもわかりやすく作業手順を明確に示せます。また、作成したデータの共有や管理を簡単に行えることも大きな強みです。
ここでは、「Teachme Biz」が働き方改革において有用である理由をご紹介します。
マニュアルのクラウド化でどこからでもアクセス可能
「Teachme Biz」はマニュアルをクラウド化することが可能です。作成したデータにどこからでもアクセスできるので、フレックスタイム制や時短勤務制度を利用する場合でもチームメンバーとの情報共有が容易になります。
自身が在宅ワーク、テレワークをする場合でも、マニュアルがクラウド化されていれば仕事の属人化を防ぐことができます。オフィスにいるメンバーとの連携が悪くなることもないため、生産性の向上が可能です。
言語問題を改善してトレーニング費用を削減
働き方改革では外国人労働者の受け入れも進められています。外国人と仕事をする上では言語の問題が存在します。「Teachme Biz」は、画像や動画で視覚的にマニュアルや手順書を作成できるだけでなく、多様な言語を併記する、さらにオプション機能では16言語の自動翻訳も可能です。ボタンのみで手軽に自動翻訳が行われるため、日本語が不得意な外国人スタッフもマニュアルを理解しやすくなります。
外国人労働者でも現場で簡単に正しいマニュアルや作業手順を確認できるため、日本人社員によるトレーニングのコストを削減することにもつながります。
資料の作成時間削減
「Teachme Biz」はマニュアルや指示書作成も容易なので、マニュアルをつくる側の負担を軽減できるのもメリットです。写真や動画を撮影しながら編集もできる「Teachme Biz」を活用することにより、導入前にはひとつの業務の手順書作成に1日を費やしていたという企業が、30分ほどで作成が可能になったという事例もあります。
「Teachme Biz」では社員の業務をスムーズに進行させられるだけでなく、無駄なコストを削減することで、生産性の向上につながります。
「社員ごとのスキルに差があり業務に無駄が多い」「紙ベースのマニュアルは膨大な手間がかかる割に機能していない」「そもそもマニュアルを作成する時間が取れない」といったことでお悩みなら、ぜひ「Teachme Biz」を活用した業務効率化のためのマニュアル作成を検討してみてください。
まとめ
働き方改革により、生産性の向上を目指し、個々のスキルを活かしながら効率的に働ける環境の構築が求められるようになりました。育児休業制度の見直しや外国人労働者の雇用促進もあり、大きな改革を必要とする企業も少なくありません。
スムーズな対応のためには、企業の課題を洗い出し、ソリューションを見出す必要があります。社員が働く環境の見直しや、属人化を避けて効率的な業務ができるマニュアルの作成などを検討してみてください。







