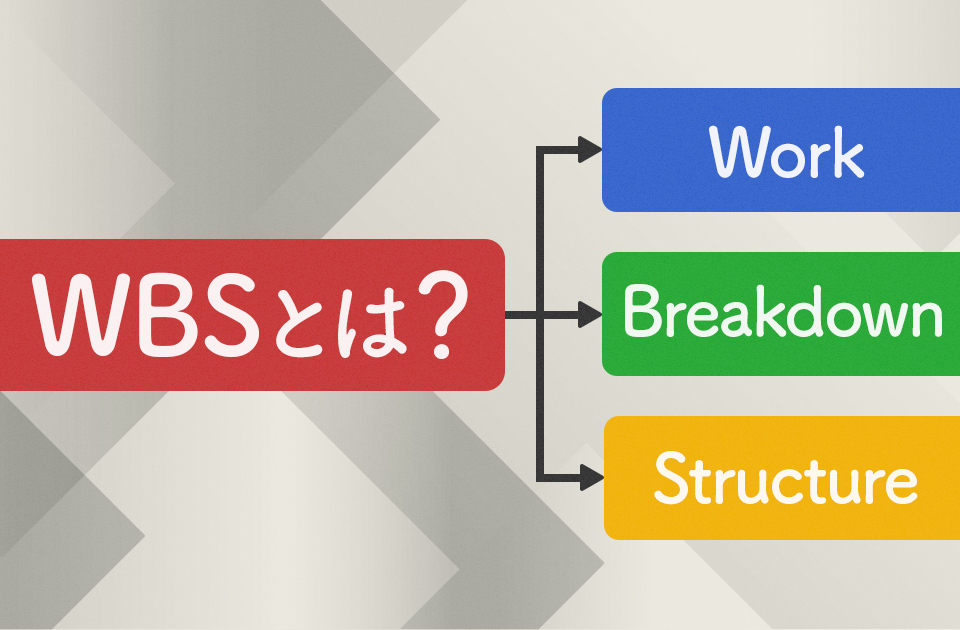QCサークル(小集団改善活動)とは?取り組むメリットや進め方を解説

QCサークル活動とは、現場で働く人が自主的に少人数集まって、品質管理や業務改善に取り組む活動のことです。この活動はチームワークの強化や人材育成にも役立つことから、製造業をはじめさまざまな業界で導入されています。本記事では、QCサークル活動の概要や導入するメリット、活動の進め方などについて解説します。
QCサークル活動(小集団改善活動)とは?
QCサークル活動とは、現場の従業員が小グループをつくり、自主的に品質向上や業務改善、業務上の問題解決に取り組む活動のことです。QCとは、「Quality Control」の略語で、日本語では「品質管理」を意味します。
QCサークル活動は、1950年にアメリカのW・エドワーズ・デミング氏が、日本の品質管理の手法として「PDCAサイクル」を提唱したことをきっかけに誕生した活動です。PDCAサイクルとは、計画→実行→評価→改善を繰り返して継続的に改善を図る手法のことです。この手法に改良を加え、現場レベルでも品質改善に参加できる仕組みとして生まれたのがQCサークル活動です。そして1961年にトヨタ自動車がこの活動を導入したことを契機に、今では製造業だけでなく、小売業やサービス業など、さまざまな業界で導入されています。
3つの基本理念と4つの要素
日本科学技術連盟は、1962年にQCサークル活動に関する雑誌を創刊したことで、QCサークル活動の普及と発展に大きく貢献しました。日本科学技術連盟によるとQCサークル活動には、以下の3つの基本理念があります。そしてこの理念を実現するために必要なのが以下の4つの基本要素です。
-
【基本理念】
- 従業員一人ひとりの能力を発揮させ、無限の可能性を引き出すこと
- 従業員の人間性を大切にし、働きがいのある職場環境をつくること
- 企業の体質を改善し、持続的な成長に貢献すること
- 人:活動を支える要素であり、人の熱意や能力が活動に大きく影響する
- グループ力:個々のメンバーが連携し、協力することで、相乗効果を生み出す
- 改善力:現場の課題を的確に分析し、解決する力のこと。改善力が高まることで 効果的な改善策を立案・実行できる
- 管理者の支援:活動しやすい環境を整え、適切なサポートを行うこと。QCサークル活動を円滑に進めるための重要な要素
【基本要素】
参照元:日本科学技術連盟|QCサークル活動(小集団改善活動)
QCサークル活動に取り組むメリット
QCサークル活動に取り組むことは、製品やサービスの品質向上や業務改善が図れるだけではありません。以下のようなメリットも期待できます。
- 現場の課題を把握できる
- 現場の自主性や課題解決力が向上する
- 現場のモチベーションが向上する
- 人材育成にもつながる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
現場の課題を把握できる
QCサークル活動では、従業員が主体となって現場の業務プロセスを分析し、非効率な作業や日常的な困りごとを見つけ出します。こうした取り組みは、経営層や管理職では気づきにくい、現場レベルの細かな課題を浮き彫りにします。QCサークル活動を通じて、職場のささいな問題点を把握・改善できれば、業務の効率化が図れ、製品やサービスの品質が向上し、顧客満足度を高めることができます。また、改善文化が企業に根付くことで、組織全体の競争力強化が図れます。
現場の自主性や課題解決力が向上する
QCサークル活動では、従業員が自分たちで課題を見つけ、解決策を考えて実行に移すため、現場の主体性が育ちます。また、PDCAサイクルを回しながら試行錯誤を重ねることで、論理的に考える力や問題を解決する力が鍛えられます。さらに、部門や階層を超えたメンバーが共通の目標に向かって協力する経験を通じて、メンバー間の協調性が高められ、組織の団結力向上につながります。
現場のモチベーションが向上する
自分たちのアイデアや取り組みによって実際に職場が改善され、周囲から称賛されることは、現場の大きなモチベーション源となります。また、自分の意見が尊重され、改善活動に役立てられることは、「自分にもできる」という自信につながり、仕事に対する意欲も高まります。さらに、活動を通じて個人の成長やチームへの貢献を実感することで、自己肯定感も満たされます。
このような現場のモチベーション向上は、企業にとっても大きなメリットです。例えば、職場のモチベーションが高まることで、生産性の向上や離職率の低下、優秀な人材の確保、企業イメージの向上などが期待できます。
人材育成にもつながる
QCサークル活動は、単なる業務改善の枠を超え、従業員が成長できる、実践的な学びの場です。課題発見から解決までのプロセスを通じて、論理的に考える力や分析力、新しいアイデアを生み出す力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力などが身につきます。また、若手社員はQCサークル活動を通じてベテラン社員からノウハウを受け継ぎ、リーダーシップを発揮する機会が与えられます。このような経験は、将来の管理職候補としての素養を育め、パフォーマンス向上にも寄与します。
QCサークル活動の進め方
QCサークル活動を成功させるためには、実現可能なテーマを選び、メンバーのモチベーションの維持・向上に努めることが重要です。ここでは、QCサークル活動の進め方について解説します。
1. サークルメンバーを決める
QCサークル活動を円滑に進めるためには、参加メンバーを慎重に選ぶことが大切です。メンバーの人数は一般的に5〜7名を目安に決めます。人数が少なすぎると1人にかかる負担が増え、人数が多すぎると一部の人だけが発言したり、活動が停滞したりする可能性があります。適切な規模を保つことが成功への鍵です。
メンバーを決める際は、議論がしやすいように同じ職場や関連部署から選出しましょう。このとき、年齢や経験、職種のバランスを考慮し、新人からベテランまで幅広いメンバーを選ぶことで、多角的な視点を得られます。参加メンバーが決まったらリーダーやサブリーダー、記録係など役割を決めましょう。また、事前に活動ルールを決めておくことも重要です。会合の頻度、時間、場所などを決めておくことで、全員参加がしやすくなります。
2. 取り組むテーマを決める
QCサークル活動の成果は、どのテーマに取り組むかによって大きく変わります。まずはメンバー全員で現場の課題を洗い出し、自分たちの部署の業務と深く関わる問題を見つけ出しましょう。ある程度課題が集まったら、取り組むテーマを決めます。テーマを決める際は、職場の改善に直結する内容はもちろんのこと、実現可能かつ測定可能なテーマを選ぶことがポイントです。実現が難しく、活動成果がわかりにくいテーマでは、メンバーのモチベーション低下やQCサークル活動の停滞を招くおそれがあります。一方、達成可能なテーマや成果がわかりやすいテーマであれば、改善がうまくいった際に、会社に貢献できるばかりか、活動のモチベーションアップにつながります。例えば「製造リードタイムの短縮」や「不良率の低減」など、明瞭かつ成果がわかりやすいテーマにしましょう。
3. 現状の把握を行い目標を設定する
QCサークル活動を効率よく進めるには、選んだテーマの現状を客観的に把握し、達成すべき目標や時期をはっきりと決めることが重要です。そこで取り組むテーマに関連するデータを集め、人や環境、時間などの要素の共通点や特徴を見つけ、整理しましょう。このように問題点を細分化することで、どこを改善すればよいかがおのずと見えてきます。
次に、「何を」「いつまでに」「どのように」改善するのかという観点から目標を設定します。「不良品発生率を半年以内に○%減らす」といったように、具体的な目標を数値で示すことで、活動の進み具合や成果を客観的に評価できます。このとき、目標設定をどのくらいにするかサークル内でしっかり話し合うことが大切です。高すぎる目標はプレッシャーやストレスを生み、低すぎる目標はモチベーションの低下につながります。そのため、慎重かつ十分に議論を重ね、適切な目標を設定しましょう。
いますぐ使える、業務棚卸表のテンプレート付き! 業務棚卸しお役立ち資料のダウンロード
4. 課題の分析を行う
改善策を立案するには、なぜ問題が発生しているのか根本原因を知る必要があります。そこで、現状把握で得られたデータや情報をもとにQC7つ道具や「なぜなぜ分析」を用いて、さまざまな角度から課題の分析を行います。QC7つ道具とは、パレート図、特性要因図、グラフ、ヒストグラム、散布図、管理図、チェックシートのことです。これらを用いることで、勘や経験ではなくデータに基づいた客観的な問題分析ができます。例えば、特性要因図を使って問題を「人」「機械」「方法」「材料」の4つ観点で整理すれば、課題の根本原因が特定できます。
一方のなぜなぜ分析とは、発生した問題に対して「なぜ」を繰り返して問題を深く掘り下げ、根本原因を特定する手法のことです。一般的に5回程度「なぜ」という問いかけを繰り返すことで、真の原因にたどり着けるとされています。
「なぜなぜ分析」について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。
なぜなぜ分析のやり方を解説!基本から実例、よくある失敗までまるごと紹介
5. 改善策を立案・実行する
課題の根本的な原因が特定できたら、具体的な改善策をメンバー間で出し合います。このとき多くのアイデアを出すことが大切です。選択肢が多ければ多いほど、実行可能で効果的な改善策を選べる可能性が高まります。
最終的に実行する改善策を決める際は、「効果の大きさ」「実施のしやすさ」「必要コスト」「実施期間」「リスク」などを基準に選びましょう。改善策が決まったら「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかをはっきりさせた実行計画を作成し、計画に基づいて実行します。実行後は、進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を修正することで、目標達成に向けた取り組みの精度や持続性を高められます。
【お役立ち資料をダウンロード】不適合品率改善の鍵は「人」と「方法」
【お役立ち資料をダウンロード】チョコ停・ドカ停は事前対策でしっかり防止
【お役立ち資料をダウンロード】手順書運用から始めるタクトタイム改善
【お役立ち資料をダウンロード】QCD改善のための多能工育成の鍵
6. 効果の確認と共有を行い「標準化」する
一定期間が過ぎたら、実行した改善策で効果があったかどうかをデータをもとに評価・確認します。改善策によって成果が得られた場合には、成果を職場全体や関連部署に広く共有します。さらに改善策は、今後の業務プロセスとして定着させるために標準化しましょう。標準化する際は、マニュアルや手順書に落とし込むと、誰が実施しても同じような効果が得られやすくなり、企業全体の成長と持続可能な発展に貢献します。
なお、成果が得られなかった場合には、改善策の実施状況、根本原因の分析、改善策の選択が適切だったかを検証します。問題点が特定できたら代替案を検討し、学んだことを次のPDCAサイクルに活かして、QCサークル活動を続けましょう。
QCサークル活動は時代遅れなのか?
QCサークル活動は継続しているうちに本来の目的を見失い、「活動すること」や「活動成果の発表」が目的になってしまうケースが少なくありません。こうした形骸化によって、QCサークル活動は一部で「時代遅れ」と見なされることがあります。
時代遅れといわれる理由
QCサークル活動が「時代遅れ」といわれる背景のひとつに、活動の継続が目的化し、本来の「課題改善」という意図が見失われやすくなることがあります。
また、限られた時間のなかで課題の洗い出しや資料作成などの作業を行うことが、ノルマのように感じられ、負担となるケースもあります。こうした作業が就業時間内に終わらず、時間外労働につながることもあり、それが現代の働き方に合わないとの指摘もあります。さらに、活動のために残業を強いられるような状況になると、自発的な参加意欲の低下を招く要因にもなります。
こうした状況から、QCサークル活動は一部で「時代にそぐわない」と見なされるようになってきています。
QCサークル活動の実情
QCサークル活動は一部で「時代遅れ」といわれることがありますが、現在でもトヨタ自動車をはじめ製造業・サービス業・医療機関など幅広く活用されています。
日本科学技術連盟(日科技連)によると、全国には9支部・35地区でQCサークル活動が推進されており、QCサークル全国大会や研修会などが定期的に開催されています。こうした全国的な組織体制と活動が継続している事実から、QCサークル活動を一概に「時代遅れ」と断言することは難しいでしょう。
まとめ
QCサークル活動とは、現場の従業員が少人数で自主的に集まり、品質向上や業務上の問題解決に取り組む活動のことです。取り組むことで、業務の効率化や、現場の自主性や課題解決力の向上、人材育成などのメリットが期待できます。
しかし、QCサークル活動は継続しているうちに、本来の目的よりも「参加する」ことが目的になり、形骸化する場合があるので、注意が必要です。そのため、QCサークル活動を導入する際は、実現可能な課題をテーマにし、参加メンバーのモチベーションの維持・向上を図ることが重要です。