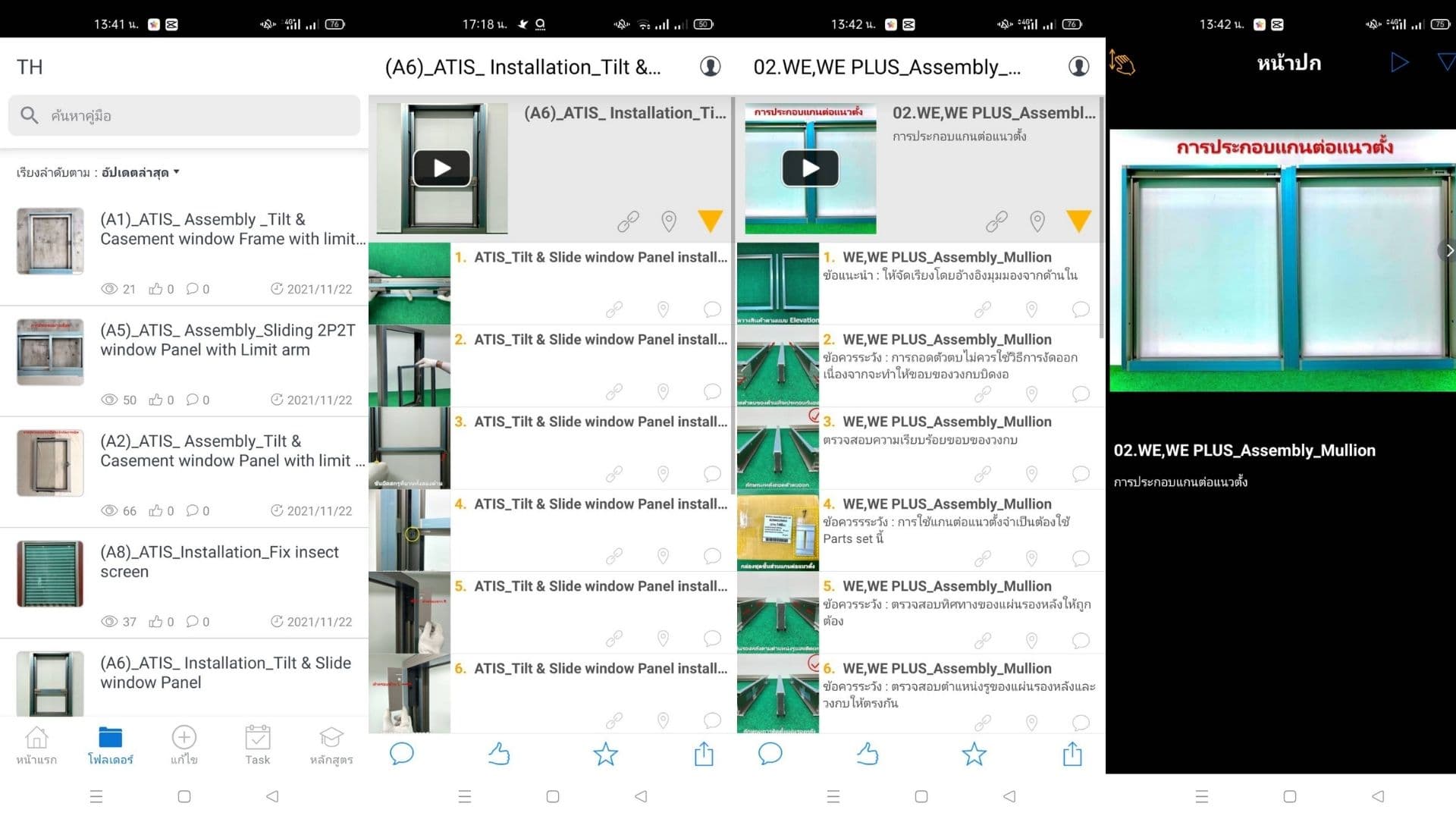リニアガイドのパイオニアであるTHK株式会社のベトナム生産拠点として、2007年に設立され、工作機械やロボット、半導体製造装置などの産業機器向けに、LMガイドやスライドレールの製造を行っているTHK MANUFACTURING OF VIETNAM様。高い精度と品質管理が求められる同社の検査工程において、作業者によらず正しい手順で作業が行える環境を整備すべくTeachme Bizを導入。導入背景や活用方法についてお話しを伺いました。
―――Teachme Bizを導入された背景を教えていただけますか?
吉田様(以下、敬称略):紙のマニュアルでは、特に検査工程での作業指示に苦労していました。「この角度から見る」「この光の当て方」「この力加減で」といった繊細な作業は、ベテランは経験で身につけていますが、紙のマニュアルでは伝えきれず、新人教育では大きな壁となっていたのです。
ズン様(以下、敬称略):紙のマニュアルでは、多くの問題がありました。マニュアルを見たい時にも探すことに時間がかかったり、マニュアルを見てもメンバーごとに手順の理解が異なることも多く、作業品質にばらつきが生じることもありました。そのため、作業開始前に先輩社員に確認するケースも多く、時間がかかっていました。
吉田:また、作業手順が改善された時の更新も課題でした。ページの差し替えや写真の撮り直しなど、手間がかかってタイムリーな更新が難しく、作業者による手順のばらつきが生じていました。
ズン:ExcelやPowerPointで1つのマニュアルを作るのに3時間ほどかかり、さらに印刷して配布する手間もありました。改訂があった場合は、古い資料を回収して新しい資料を配布し直す必要があり、その管理も大変でした。
吉田:動画を入れた分かりやすいマニュアルを作ろうかという話をしていた時、社長からTeachme Bizの紹介を受け、デモを見せていただきました。特にシンプルで分かりやすい点、画像や動画で作業を記録できる点に可能性を感じ、導入を決定しました。

品質保証部部長 吉田様
―――具体的にどのような業務でTeachme Bizを活用されていますか。
ズン:製品の最終検査工程で活用しています。各製品の見本にQRコードを貼り付けており、作業者はそれを読み取ることで、その製品専用の検査手順をすぐに確認できます。異なる製品の作業に入る際には、その製品独自の検査方法をしっかり理解してもらうため、必ずマニュアルを確認するルールとしており、各作業員は毎日マニュアルを参照しています。
吉田:作成したマニュアルは、まず新人作業者に使ってもらい、フィードバックを収集しました。「この部分の説明が足りない」「この動作をもう少しゆっくり見たい」といった具体的な改善点を随時反映していきました。システム上で簡単に編集できることも、このような継続的な改善を可能にしている要因です。
特に新人の視点からのフィードバックは、当たり前すぎて説明を省いていた部分を発見するのに役立ちました。このように段階的に改善を重ねていった結果、現場で実際に使える実践的なマニュアルが完成し、その後の他工程への展開もスムーズに進めることができました。

Mr. Nguyen Dinh Dung, Quality Assurance Inspection
―――Teachme Bizを使用する作業者の反応はいかがですか?
ズン:とても前向きな反応が多いです。特に若手のスタッフは、スマートフォンなどのデジタル機器に慣れているため、直感的に使いこなしています。入社したばかりの従業員からは「分からないことがあっても、すぐに確認できて安心」という声をよく聞きます。
一方で、最初は特に年配のスタッフから「今までの紙の方が慣れている」という声もありました。しかし、実際に使ってみると操作が簡単で、むしろ紙よりも便利だということを理解してもらえました。今ではベテランのスタッフからも「自分の経験やノウハウを若手に伝えやすくなった」という評価を得ています。
当社ではベトナム人従業員が多いのですが、日本人の技術指導員も定期的に日本から出張に来ています。以前は通訳を介してもニュアンスが正確に伝わらないことがありましたが、マニュアルをTeachme Bizで作るようになってから、動画と写真があることで、言語の壁を超えて正確な情報共有ができるようになっています。

検査前には必ず手順書を確認するルールを徹底
――現場での活用状況と導入効果を具体的に教えてください。
吉田:導入から約半年が経ち、特に2つの面で大きな効果が現れています。まず、作業の標準化による品質向上です。作業者間での判断基準が統一され、不良品の見逃しも大幅に減少しています。
2つ目は、新人教育の効率化です。以前は2週間かかっていた教育期間が、現在は1週間程度に短縮されています。動画の一時停止や繰り返し再生機能を活用することで、新人作業者が自分のペースで学習を進められるようになったことが大きいですね。また、ベテラン作業者の「コツ」や「勘所」が動画で可視化されたことで、暗黙知の継承もスムーズになりました。
――最後に、今後の展開についての具体的な計画を教えてください。
吉田:現在の作業手順書という活用方以外にも、幅広い展開を検討しています。具体的には、金型の分解・組立手順のマニュアル化や設備の修理・メンテナンス方法の文書化です。製造設備のトラブル対応や定期メンテナンスの手順を動画で残すことで、設備保全の質を向上させ、ダウンタイムの削減を目指します。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/thk-manufacturing-of-vietnam/ (事例動画あり)
―――まず御社の事業について教えてください。
五十嵐様(以下、敬称略):弊社は豊田通商株式会社の子会社で、1957年以来60年以上にわたりタイにおけるトヨタフォークリフトの正規代理店を務めてまいりました。フォークリフトの販売だけでなく、レンタルサービス、部品供給、安全訓練プログラムなど、幅広い事業を展開しています。最近では、カーボンニュートラリティや自動化分野のソリューションにも注力し、お客様への総合的なソリューション提供に力を入れています。

五十嵐様, General Manager
「必要な情報にすぐアクセスしたい」現場の声からDX推進へ
―――Teachme Bizを導入したきっかけを教えていただけますか。
五十嵐:社内でDX推進が本格化する中、私たちが真っ先に取り組まなければならなかった課題が、日々の業務で扱う情報をデジタル化し、必要な時にすぐアクセスできる環境を整えることでした。また、環境負荷低減の観点から、紙の使用量を抑えたいという要請も強まっていました。
それまでは手順書をはじめあらゆる資料が紙ベースで各部署に散在し、必要な情報を探し出すのに貴重な時間を費やしており、社員からも「もっと効率的な情報管理の仕組みが欲しい」という声が上がっていたのです。
そんな時にTeachme Bizと出会い、この導入が社内の情報アクセスを改善し、ペーパーレス化への第一歩になると確信しました。
Teachme Bizで現場技術者の自己解決を可能に
―――具体的にどのような活用をされていますか。
Ms. Rattanaporn(以下、敬称略):主に技術者向けのマニュアル作成に活用しています。例えば、フォークリフトの点検方法や修理手順などをマニュアル化し、QRコードで共有しています。技術者が現場で問題に直面した際、このQRコードをスキャンすることで、すぐに解決方法を確認できるようになりました。以前は上司に電話で確認する必要がありましたが、今では自分で解決できるケースが増えています。
また、新入社員向けのトレーニングにも活用しています。ビデオ教材を作成し、Teachme Bizを通じて共有することで、効率的な研修が可能になりました。
Ms. Kanyarat(以下、敬称略):安全管理部門では、社内外のステークホルダーとのコミュニケーションツールとして活用しています。外部の協力会社様向けには、従来は対面での研修が必要でしたが、Teachme Biz導入後はリンクやQRコードで研修マニュアルを配布し、自主学習が可能になりました。
社内向けには、その時々の状況に応じた月次の安全啓発活動に注力しています。トレーニング機能を活用することで、情報へのアクセスが容易になりました。また、クイズやコメント機能など、インタラクティブな要素を取り入れ、従業員の参加意欲を高めています。さらに、小さな報奨も用意し、Teachme Bizを通じた協調学習を促進しています。

(左) Ms. Rattanaporn Pengpit, Digital Transformation Team
(右) Ms. Kanyarat Hnanta, Safety & Kaizen - Supervisor
―――導入時や運用で苦労した点はありますか?
Rattanaporn:導入当初は新しいシステムへの抵抗がありました。特に紙のマニュアルに慣れていた現場の技術者から不安の声が上がりましたが、定期的なフォローアップと使用方法の指導を通じて、徐々に浸透していきました。
Kanyarat:私たちの部門では大きな抵抗はありませんでした。むしろ、情報へのアクセスが容易になったことを歓迎する声が多かったです。課題があるとすれば、マニュアル作成の面です。Teachme Bizは簡潔な内容が効果的なため、分かりやすく要点をまとめることに注力しました。
安全研修のデジタル化により月間12時間の対面研修を削減
―――導入の効果はいかがでしょうか。
五十嵐:Teachme Biz導入後、主に3つの大きな効果が見られました。1つ目は、QRコードによる情報アクセシビリティの向上です。作業現場の各所にTeachme BizのQRコードを設置したことで、必要な情報にワンタッチでアクセスでき、情報検索の時間が大幅に削減されました。2つ目は、従業員と管理職間のコミュニケーションが活性化したことです。これまでの一方通行になりがちだった情報共有が、自然と双方向のコミュニケーションに発展しています。最後に、情報の閲覧状況を正確に把握できるようになったことです。全従業員にアカウントを付与することで、誰がどの情報にアクセスしたのかを適切にモニタリングできるようになりました。これらの改善により、業務効率が大きく向上し、非常に満足しています。
Kanyarat:安全管理部門では、Teachme Biz導入前は協力会社様など外部関係者向けの対面研修に、週3回1時間で月間12時間を費やしていましたが、Teachme Biz導入によってこのプロセスがなくなりました。
また、社内のコミュニケーションも大きく改善しました。スタッフが私たちの共有する情報に素早く簡単にアクセスし、何か不明点や意見があればコメントを入れてくれる等、双方向でコミュニケーションを取ることができるようになりました。安全管理の観点からも、全員が必要な情報を共有できる環境が整ったことは大きなメリットです。
Rattanaporn:最も印象的な変化は、技術者の問題解決能力の向上です。以前は問題が発生すると都度上司に連絡していましたが、現在は現場でQRコードを通じて即座に必要な情報にアクセスでき自己解決ができるケースが格段に増え、問題解決のスピードが大幅に向上しています。

作業現場ではタブレットで即座にマニュアルにアクセス
全社展開に向けて、さらなる活用促進へ
―――最後に、今後のTeachme Bizの活用計画についてお聞かせください。
五十嵐:Teachme Bizの導入により、社内のDX化が大きく前進しました。情報共有の迅速化、ペーパーレス化、コミュニケーションの活性化など、多岐にわたる効果が見られています。ただ、全社員にTeachme BizのIDを付与していますが、部署によって使用頻度にばらつきがあるのが現状です。今後は、Teachme Bizの機能についての理解をさらに深め、より効果的な活用方法を模索していきたいと考えています。デジタルトランスフォーメーションを継続的に推進し、さらなる業務効率化を実現していきます。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/toyota-tsusho-forklift-thailand/ (事例動画あり)
少人数のチーム編成ゆえのマニュアルの導入
―――貴社の事業概要について教えてください。
吉岡様(以下、敬称略) 弊社は化学品原料の専門商社です。文政年間(1818年〜1831年)に尾張名古屋で砂糖や油を扱う個人商店として創業し、戦後に法人化を果たしました。
タイに進出したのは2018年です。中国等から輸入してきた商品を在庫として販売するほか、一部タイのメーカーの商品を代理店として仕入れ、販売を行っています。

Andoh Parachemie (Thailand) CO., LTD., 吉岡 稔益様
―――3名という少人数のチーム体制でありながら、Teachme Bizを導入された背景をお聞かせください。
吉岡 少人数だからこそマニュアルが必要だったんです。立ち上げ時は、私とタイ人スタッフ2名という最小限の人数でスタートしたのですが、人数が少ないがゆえの課題がありました。
例えば、タイ人スタッフが4〜5人いれば誰かが一人退職しても、別のスタッフに引き継ぎ業務をお願いすることができます。しかし、我々は最低限に人数を絞って運営していたため、そういうわけにもいきませんでした。
さらに、タイ法人を立ち上げる前から、タイはスタッフの入れ替わりが激しいと聞いていました。一ヶ月前に退職の申し出があったとしても、そこから次のスタッフを探して採用するとなると、実質引き継ぎにかけられる期間が数日だけということもザラだと。また、私自身の英語力が高くないことも導入の理由の1つでした。口頭で流暢に説明するのは難しいですが、マニュアルにしておけば、片言の英語でも何とか業務を伝えることができます。着任当時は私もとにかく不安でしたので、藁にもすがる思いでTeachme Bizの導入を決めました。
煩雑な書類申請の手続きも、マニュアルのおかげでスムーズに
―――引き継ぎにかかるコスト削減が導入の決め手だったのですね。実際に導入してみた使用感や手応えはいかがでしたか?
吉岡 多言語対応していることが心強かったですね。私はタイ語も英語もそこまで満足に喋れるわけではなかったので、あらかじめマニュアル作成をしておけば、いざ引き継ぎが発生したときも、「これを見れば仕事のやり方がわかるよ」と業務内容をスムーズに教えることができました。
また、ビジュアルで内容がまとめられることも役立ちました。弊社は化学薬品を扱うので、定期的に役所に届け出を出す必要があります。その点、Teachme Bizは画像やPDFの貼り付けができるので、そういった提出書類を貼り付けておいて、「この書類が届いたらこうする」という流れを一目で分かるように管理できたのはとても便利でした。
スタッフのモチベーションを管理しつつ、少しずつ内容を充実させていった
―――導入後、引き継ぎに十分なマニュアルが完成するまではどれくらいの時間がかかりましたか?
吉岡 一年ぐらいはかかったと思います。中には、年に数回しかない業務や、数年に一度だけ行う業務もあったので。社員の入れ替わりが多い組織だからこそ、そういった頻度が低い業務ほど、マニュアルに残しておくことが必須でした。「あのときマニュアルを作っておいて助かった」という場面が何度もありましたね。
―――現地スタッフにマニュアル作成を浸透させるには、どういった工夫をされましたか?
吉岡 いきなりマニュアルを作ってくれと伝えても難しいだろうと思ったので、まずは私が作成できるマニュアルをいくつか作成し、「これを真似て別の業務もマニュアルにまとめてみて」とお願いしました。また、業務が発生するたびに、その都度「これもあとでマニュアルにまとめてね」と伝え、少しずつ内容を充実させていきました。
それから、「まさにこのマニュアルが必要だった!」という秀逸なマニュアルを自発的に作ってもらえた時は、「すごいな」「いいの作ったね」と伝えて、ちょっとしたドリンクやお菓子をご馳走していました。
―――自分でも手本を示しつつ、モチベーションの管理も行っていたのですね。秀逸なマニュアルとは、例えばどういったものですか?
吉岡 きれいにまとまっているというよりは、先ほどお話した数年に一度の業務など、「後々このマニュアルがあったら助かるだろうな」と感じるような、穴になっている部分を埋めてくれた時ですね。
導入二年目以降はTeachme Bizのマニュアル作成量をボーナス査定に反映させていました。実際に、たくさんマニュアルを作成してくれたスタッフがいた時は、「あなたはたくさん作成してくれたから」と伝えた上でボーナスを増額することで、他の社員のモチベーションも上がるように工夫をしていました。

実際に作成されているマニュアル
Teachme Bizのおかげで精神的な余裕ができた
―――実際に運用してみて、どのような効果を感じられましたか?
吉岡 まず、引き継ぎがスムーズになりました。タイでは人の入れ替わりが激しいのですが、マニュアルがあることで新しい社員への引き継ぎがずっと楽になりました。
また、予想外の効果として、私自身の精神的な安定にも繋がりました。人が辞めると慌ててしまうものですが、「マニュアルがあるから何とかなる」という安心感が生まれたんです。特に2年目、3年目くらいはこの安心感が大きかったですね。
さらに、マニュアル作成を通じて、私自身も業務フローを整理できました。3年目くらいになると、マニュアルを見ながら新入社員に「次はこれ、次はこれ」と説明できるようになりました。
―――素晴らしいですね。少人数組織ならではの使い方で、大きな効果を得られたんですね。最後に、これからTeachme Bizの導入を検討している企業へのアドバイスがあればお聞かせください。
吉岡 マニュアルツールは大規模組織向けというイメージがあるかもしれませんが、少人数組織こそ効果的に使えると思います。引き継ぎの効率化はもちろん、言語の壁を越えたコミュニケーションツールとしても活用できます。また、マニュアル作成は地道な作業ですが、長期的に見ればとても重要です。特に海外拠点の立ち上げ時など、不安定な状況では大きな支えになります。ぜひ、自社の状況に合わせた活用方法を見つけてほしいですね。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/andoh-parachemie-2/ (事例動画なし)

インタビューさせていただいた方々
Mrs. Wanida Igarashi – Manager
Ms. Chanakarn Fukuda – Admin Senior Staff
Ms. Angkana Maraiban – IT Developer Senior Staff
Ms. Tippya Pasitwilitham – Helpdesk Leader
QUALICA (Thailand) Co., Ltd.は、製造業および飲食店や小売業の顧客向けに、IoT、クラウドサービス、業務システム開発、ソフトウェアパッケージなど、幅広いITソリューションを提供しています。
同社は、タイにて拠点を設立した直後の2018年からTeachme Bizを活用しています。システム導入後の数年間で経験した変化や、今後の活用方法についてお話を伺いました。
社内外のコミュニケーションのためのシステムと標準の確立
―――Teachme Bizの導入目的についてお聞かせください。
Mrs. Wanida: Qualicaがタイに事務所を設立した当初、まず考えていたことは会社の仕事の仕組みや基準をどう作っていくか、そしてタイ人社員とどのように上手くコミュニケーションを取っていくかということでした。そんな中で、使い方が幅広く、私たちが求めていたニーズを満たしていたTeachme Bizを導入することになりました。具体的には、社内の業務の流れを見える化して標準化したり、マニュアル作りをもっと効率よくしたり。それに、会社のサービスについて外部の人や顧客にわかりやすく説明して、より深く理解してもらうのにも使えると考えたんです。
―――Teachme Bizはどのような場面で使用していますか?
Mrs. Wanida: まず取り組んだのは、会社の方針や規則など、全社員が把握すべき重要な情報に関するプロセスの可視化でした。Teachme Bizを活用することで、マニュアルの改訂、更新、維持のプロセスが大幅に簡素化されました。例えば、新しい労働法が施行された際には、Teachme Biz上の情報をすぐに更新し、全社員と共有することができます。
また、Teachme Bizのトレーニング機能を用いて、新人研修のプロセスを効率化しました。新入社員は自分のペースで会社のポリシーや手順について学ぶことができ、必要に応じて復習することも可能なので、より理解を深めることができています。

Teachme Bizで簡単に、効率的にカスタマイズされたユーザーマニュアルを作成
―――Teachme Bizを使用してみていかがですか
Ms. Angkana: ITサービスプロバイダーである私たちは、お客様ごとの特定のシステムニーズに合わせたマニュアルを作成する必要があります。例えば、当社はKintoneのサービスリセラーでもあります。Kintoneはユーザーが自身のニーズに応じてシステムをカスタマイズできるプラットフォームであり、そのため各ユーザーのシステム構成に違いが生じます。
私たちは単なるサービスのリセラーではなく、Kintoneに関するコンサルティング、アプリ開発、トレーニングも提供しており、それぞれの顧客に応じたマニュアルが必要となります。これに対応するためにTeachme Bizを活用し、Kintoneのマニュアルを作成しています。画像や動画、強調する箇所にはマーキングなど視覚的に分かりやすくする機能が豊富で、顧客の理解を深めるのに役立っています。
Teachme Bizのテンプレートのおかげで、マニュアル作成プロセスが大幅に効率化されました。他のプログラムを使用する場合と比べて、フォーマットやレイアウトを考える必要がなく、Kintoneのユーザーマニュアルをすぐに作成できるようになりました。
カスタマーサポートの効率化
―――お客様サポートにはTeachme Bizをどのように活用していますか?
Ms. Tippya: ヘルプデスクチームは、当社が提供している様々なシステムに関する顧客サポートを担当しており、それぞれのシステムの異なる機能の使用方法やシステムのFAQに関するユーザーマニュアルの作成も担当しています。
Teachme Bizの導入により、顧客からの問い合わせに迅速かつ効率的に対応できるようになりました。顧客から特定の機能の使用方法について質問があった場合、関連するマニュアルのリンクをすぐに送るだけで回答ができてしまいます。これにより、顧客はすぐに必要な情報に簡単にアクセスすることができるようになりました。

明確で一貫した業務基準の確立
―――導入後に感じられたメリットを教えていただけますか?
Ms.Chanakarn: Teachme Bizにより、管理業務の効率が向上しました。例えば、英語版の源泉徴収証明書の発行など、詳細な情報や文書が必要な管理業務を行う場合においても、Teachme Biz上のマニュアルを参照するだけで済みます。準備した書類や記入済みの文書が完全で正確であり、必要な添付書類がすべて含まれているかどうかを迅速に確認できるようになりました。
Mrs. Wanida: Teachme Bizにより、従業員研修のプロセスを簡略化できました。クラウドベースなので、従業員はいつでもどこでもマニュアルにアクセスできるようになり、スムーズに学習を進めていくことができています。以前は、従業員を集めて対面での研修を行っていました。PowerPointで研修資料を作成していましたが、作るのに時間がかかったうえに、そのファイルを社員に共有するのも一苦労。研修後は理解度を確認するために、Googleフォームで問題を作成しなければなりませんでした。
Teachme Bizを導入したことで従業員の学習状況を確認し、プラットフォーム内で直接テストを作成できるようになりました。これにより、外部ツールの使用が不要になり、研修管理も一元化することができたんです。
―――Teachme Biz導入後、具体的な改善点はありましたか?
Mrs. Wanida: Teachme Bizは特に新入社員の研修時間短縮に役立っています。従業員は、理解しやすい、定期的にきちんと更新されているマニュアルを通じて独自に学習することができるようになりました。また、業務プロセスの標準化にも貢献しています。明確なマニュアルがあることで新入社員が確実に正しい手順を覚えることができ、自信を持って働けるようになりました。
さらに、業務に関する問い合わせの数が大幅に減少しました。以前は月に最大20件ほどあった問い合わせが、時にはゼロにまで減ることもあります。
Teachme Bizの「ユーザー」から「サービス提供者」へ
―――今後、Teachme Bizの利用をさらに拡大する計画はありますか?
Mrs. Wanida: 最初は私たちもTeachme Bizのユーザーでしたが、スタディストタイランドとパートナーシップ提携を結び、私たちもTeachme Bizを提供する側になりました。実際にユーザーとして使用している私たち自身の経験を語りながら、海外でのビジネス展開に必要不可欠な機能を備えているTeachme Bizを、タイだけでなくASEANに広めていきたいと考えています。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/qualica-thailand-co-ltd/ (事例動画あり)
単なるスポーツ指導に留まらない人材教育
AMITIE SPORTS CLUB CO., LTDは、2014年1月からベトナムで子ども向けのスポーツスクールを運営しています。2023年7月現在ではホーチミン、ハノイ、ハイフォン、ビンズンでスクールを展開しています。サッカーがメインで、現在ベトナム全土で3,500人ほどの生徒がいます。女の子向けのチアダンスには200人ほどの生徒が在籍しており、今後はバスケットボールも始めたいと考えています。
ボールの蹴り方や止め方、ドリブルの仕方や戦術など、サッカーのやり方を教えるスクールは多くあります。ですが、プロのレベルを除いては、就職時などにサッカーの技術が優位に働くわけではありません。ただ、困難なことが目の前に訪れた場合どうやって跳ねのけるのか、困っている仲間がいたらどうサポートするのか、チームとしてどうしたらいい成果が出せるのかなど、スポーツを通じて学ぶことは社会に出てもとても大切なことです。私たちは単なるサッカーの指導に留まらず、そういう力を身に付けさせてあげることが子どもたちの将来の可能性を広げてあげることだと思っています。

私たちのクラブでは、具体的に意識して行っていることが2つあります。
1つは、「子どもたちに全力を出してもらえるようにすること」です。全力でやってうまくいったからうれしいとか、うまくいかなくて悔しいとか、感情の幅を経験することで人間の幅も広がり、それこそが人が成長する瞬間だと信じています。その前提にあるのが100パーセント全力でやるということ。そうした環境を作るために先生は、松岡修造さんのように熱く、明石家さんまさんのようにユーモアを持って子どもたちと接し、子どもたちの全力を引き出すことを徹底しています。
もう1つは「意識付けと習慣化の徹底」です。私は、良い行動をして、それが習慣になれば良い結果が得られたり、良い方向へ成長することに繋がると考えています。スクールには子どもたちに身に付けてほしい力というものがあります。最後まで諦めないでがんばる力とか、どんなことにも意欲的にチャレンジする力といったものです。それらを身につけるため、毎月「仲間に優しくしよう」というような約束事を設定し、練習開始時、練習終わり、さらに帰る前にもその約束事を生徒と確認することで、例えスクール外であっても、そういう場面に出会した時、良い行動に移してもらえるよう意識付けをし、習慣化することを目指しています。
クオリティのバラつきに課題
現在3,500人ほどの生徒を60人ほどの先生で対応しています。設立当初は私自らがレッスンを行い、ベトナム人の先生への指導も私が直接行っていたので、レッスンの標準化はできていました。しかし、現在は先生も4階層くらいに増え、私の指導が伝言ゲーム状態になってしまっていて、そこにサービスレベルのばらつきが生まれていました。
これまでは毎日の昼礼で、その週に意識するテーマの共有や共有内容を部下から上司へのフィードバック、上司から私へのフィードバックを行い、さらに私のフィードバックを受け、全員で再度トレーニングをしていました。全体のクオリティ維持のためこれを続けてきましたが、何せ効率が悪い。4年後には1万人の生徒規模にしたいという目標があり、そのためには今抱えているクオリティのばらつきや非効率な方法は絶対に解決しなくてはいけないという問題意識がありました。

ベトナムでも手厚いサポート
今回、Teachme Bizの導入に至ったきっかけは知人の紹介でした。実は4〜5年ほど前にベトナムで有名な日系飲食店さんが導入されたことを知り、サービス業で活用できるのなら私たちにも合っているのではと考え、一度、トライアルで利用したことがありました。当時はセルフサーブ型のトライアルで、自分一人でのトライアルで魅力を感じることができず、導入には至りませんでしたが、今回知人の紹介で再度接点を持たせていただき、担当者の方にきちんとご説明いただいたことで、使い方が非常に簡単なことなど4〜5年前にはわからなかったTeachme Bizの魅力が伝わり、効率化やさらなる標準化を図るため導入に踏み切りました。また、ベトナム語にも対応できるようになった点やベトナムでも現地パートナー企業によるサポートが充実していることも導入に至った大きな理由になります。まだ導入して1~2週間ですが、Teachme Bizは生徒数1万人を達成する1つのツールになってくれると期待しています。
アナログな時間を増やすためにテクノロジーを使う
私たちは生徒がどうやったら楽しく話を聞くのか、どのように声をかけてあげたらより理解して成長するのかといったことを常に考えています。そのため、先生が使うマニュアルには、「どうやってインサイドパスを教えるのか」などではなく、「がんばっての『て』の語尾を上げて話す」などといった語感まで言語化して落とし込んだり、練習の説明をするときの質問回数などが細かく記載されていて、よりハートフルなマニュアルになっています。しかし、どうしてもエクセルやスプレッドシートの文字だけでは共通認識が取りづらく、レベルの濃淡が生まれてしまう。そこでTeachme Bizを使い、動画をプラスすることで認識のずれが埋まっていくと考えています。また、これまで流れてしまっていた経験やナレッジを動画でストックしていくことで、会社としての大きなアセット(資産)にもなります。

私たちの商品は人がすべてです。先生が如何に子どもたちに熱く楽しく接してくれるかにかかっています。そのためにはこれまで行ってきたアナログなトレーニングは避けて通ることはできません。ただ、これまでのマニュアル作りや共有にかかっていた時間はTeachme Bizでもっと効率化できます。その結果、より多くの時間をトレーニングに割くことが可能になります。私たちはテクノロジーがアナログな時間の創出を裏側から支えることを目指します。
現時点でもある程度のレベルで我々の理念、それに基づいた指導内容、子供たちへの接し方などは社内で共有できていますが、まだまだ足りません。それをより高い水準に引き上げていくことで、今いる子供たちの成長だったり、保護者の方の満足度に繋げていきつつ、会社の視点としてはたくさんの子供たちが通ってくれることが社会的に意義のあることだと思っています。Teachme Bizを活用して高いレベルでのサービスの均一化を推進していく。どこを切ってもめちゃくちゃ指導のうまい金太郎飴を作れるようにしていきたいですね。

■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/schoolpartnervietnam/ (事例動画なし)
企業の業務効率化・改善をサポート
―――株式会社GlobalB様の事業概要について教えてください。
田川様(以下、敬称略) 当社は、システム開発や業務改善コンサルティング、WEB制作、動画制作、SNS広告などを手掛ける会社です。本社は長崎県にあり、タイ、ベトナムにも拠点を持っています。
また、当社は株式会社サイボウズのオフィシャルパートナーとして、サイボウズのクラウドサービス「kintone」の多言語対応連携サービス「LITONE」を運営しています。「LITONE」を活用すれば、「kintone」に登録したデータをもとに見積書や請求書の帳票を簡単にPDFやExcelに出力したり、出力したデータを「kintone」上に登録されているメールアドレスに対するメールを作成、送信するなど、「kintone」の標準な機能には無い機能を追加することができ、さらなる業務効率化を実現できます。

Ms. Yoshimi Tagawa, System Analyst
―――Teachme Bizを導入した背景を教えてください。
田川 もともと、当社ではPowerPointを活用して「LITONE」のマニュアルを作成していたのですが、作成することに手間も時間もかかるうえに、機能のアップデートのたびに修正、共有しなければならず、対応工数がかかっていました。数年前にPowerPointから別のアプリケーションに移行してから大変さは少し改善されたのですが、それでも手が回っていない状態で、何かもっと良いサービスはないかと探していたんです。
そのタイミングで、タイの展示会でサイボウズの方からスタディストタイランドの方をご紹介いただき、Teachme Bizの詳細を聞いて導入を決めました。
いい意味で期待を裏切られた使用感。多言語対応もスムーズ
―――社内で導入していくにあたって、不安はありませんでしたか?
田川 不安は特にありませんでしたが、正直な話、最初にTeachme Bizのことを紹介された時、私はそこまで期待をしていませんでした。PowerPointから別のアプリケーションに移行した時も、「少し楽になった」程度だったので、今回もそこまで劇的な変化はないんだろうなと。しかし、せっかくおすすめしていただいたので試しに使ってみたら、想像していたよりもかなりマニュアル作成・管理の業務が楽になって驚きました。
―――実際に、どのような点に使いやすさを感じましたか?
田川 Teachme Bizで作成したマニュアルには簡単に画像や動画が入れられますし、ステップ構造であることで内容もより分かりやすくなりました。導入前の課題だった、修正のたびに新しいバージョンを作らないといけない問題が解決されたことも大きいです。該当箇所だけアップデートすればいいので、対応にかかる時間が削減されました。
Anan様(以下、敬称略) 多言語対応のスムーズさもポイントでした。PowerPointでマニュアルを作成していた時は、同じ内容でも言語によって文字数が変わってしまうので、きれいに画面上に収まるように毎回レイアウトを整え直す必要があり、無駄な時間がかかっていました。Teachme Bizでは、画像や動画とテキストフィールドがはっきり分かれているので、文字数が変化しても影響がなく、常にきれいなレイアウトを保つことができます。

Mr. Anan Santayati, Managing Director of Global B (Thailand) Co., Ltd.
―――具体的に、どのようにTeachme Bizを導入していったかを教えてください。
田川 まず、マニュアル作成が必要な項目の洗い出しから始めました。実際にTeachme Bizに触って機能に慣れつつ、社内で2ヶ月ほどかけて現行のマニュアルの整理とリストアップを行い、そこから実際にマニュアルの移行作業に入っていきました。スタディストの方が隔週でフォローアップを行ってくれたので、使い方がわからないといったトラブルもなく、スムーズに作成ができたと思います。
Anan 日本語版のマニュアルは約1ヶ月ほどでほぼ完成の目処が見えてきたので、すぐに英語版にも着手していきました。英語版のマニュアルは、リストアップした順に一から作っていくのではなく、優先度の高い項目や、お客様から問い合わせがあった項目から順次作成していきました。
問い合わせ対応にかかる時間が大幅に削減。お客様の役に立っていることを実感
―――お客さまに対するTeachme Biz の活用方法を教えてください。
田川 お客さまに「LINTONE」をご契約いただいた際、管理画面にデフォルトでTeachme Bizで作成したマニュアルのリンクを埋め込むことで、簡単にアクセスできる環境をつくっています。また、これまでお客様から問い合わせがあった際、メールで何往復もやりとりをしたり、別途Zoom等のオンラインミーティングを設定して対応をしていましたが、Teachme Biz導入後は該当マニュアルのリンクを送るだけなので、素早くお客様の課題解決ができるようになりました。マニュアルがない項目についての問い合わせがきた場合は、すぐに追加でマニュアルを作成し、また同じ問い合わせがきた際に対応できるようにしています。
Anan 実際に使い始めてから便利だなと感じた機能は、複数のフォルダごとにリンクをコピーして共有できることです。これまでは、関連マニュアルを一つ一つ送らないといけませんでしたが、Teachme Bizではドライブ内にフォルダをまとめて、一つのリンクでお客様に共有できます。一つ一つリンクを確認するのは、お客様にとっても手間がかかると思うので、まとめてフォルダを共有し、直感的に知りたい情報だけを探せるのはかなり便利だと思います。

Sample Manual
―――お客さまに対するTeachme Biz の活用方法を教えてください。
田川 Teachme Bizでは、マニュアルの閲覧回数が確認できるのも良いですね。月に700回マニュアルが閲覧されたということは、700回分の問い合わせ対応の業務が削減されたということですから、もっとマニュアルを充実させていこうとモチベーションが上がりますし、お客様の役に立てているんだなと実感できるのもうれしいです。
Anan 以前は、一つの問い合わせに対して多い時で5〜10往復のメールのやりとりがありました。今はTeachme Bizのリンクをお送りするだけでいいので、1往復で対応が終わります。問い合わせを受けた際にお客様が求めるポイントは速さだと思うので、とても助かっています。

今後も社内外のマニュアルを充実させ、きめ細かいサポートを提供していきたい
田川 お客様向けのマニュアルはかなり整備されてきたので、今後は社内向けのマニュアルを作成していきたいと思っています。もともと、お客様向けのマニュアル作成のためにTeachme Bizを導入しましたが、実際に使い始めてみて、新人教育や業務の引き継ぎの際に社内マニュアルがあれば便利そうだなと思うようになりました。
Anan お客様のどんなお問い合わせにも対応できるようマニュアルを充実させていきたいです。例えば、「更新がうまく反映されない際のブラウザのリロードの仕方がわからない」という問い合わせをいただくこともあります。自社サービス自体への質問ではないものの良く同じ質問をいただき、毎度時間をかけてご案内する手間が発生していましたが、Teachme Biz導入後は、サポートの時間が大幅に短縮されたことにより、そういった細かい部分にも対応する余裕が生まれました。今後も、お客様にきめ細かいサポートが提供できるようにしていきたいです。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/globalb/ (事例動画なし)
ブラックボックス化、属人化した業務に危機感
Mr. Kusumoto : 当社の事業は大きく分けて2つあります。1つは車載用の組込みソフトウエアの開発、もう1つは車や民生品向けの電子部品の販売や設計開発支援を行っています。
以前より当社の人事総務部では業務の属人化、ブラックボックス化という課題を抱えていました。少ない人数の中で一人ひとりに業務が偏ってしまい、スタッフが退職したり、病気や家庭の事情によって長期的に業務から離れてしまうと、その担当者以外が業務のやり方を知らない。このようなリスクと常に隣り合わせにおり、この状態を脱しなければいけないという危機感をずっと持っていました。

Mr. Hiroshi Kusumoto, General Manager HR & GA Department
マニュアル作りとマニュアルの常時更新の難しさ
Mr. Kusumoto : このリスクを回避するために、数年前からマニュアルの整備を進めています。それぞれがマニュアルを作って共有することで誰もが同じアウトプットを出す、同じ品質で仕事をすることを目指してきました。しかし、マニュアルを作るのはとても難しい。エクセルやワードを使う人もいれば、パワーポイントで作る人もいて、まったくスムーズに作成が進みませんでした。
たとえ一度作ったとしても、それを更新できていなかったりで、マニュアルが形骸化してしまう。それを何とかしなければ、常に新しいマニュアルをアップデートしていかなければという課題が根本にあり、使い勝手がいいツールをずっと探していました。
気軽さが導入の決め手に
Mr. Kusumoto : Teachme Bizを導入した決め手は気軽さですね。マニュアル作りや更新の煩雑さに課題を感じていましたが、Teachme Bizならマニュアルが気軽に作れる、気軽に更新できる。ここに尽きると思います。Teachme Bizは、フォーマットが決まっていてそこに画像や動画を落とし込んでいく、それだけで簡単に作成、更新もできるので便利だとスタッフからも好評です。
導入して1年ほど経ちますが、すでに部内で良い変化が起きていると感じています。例えばミーティングでディスカッションをした際、「では、Teachme Bizにまとめておきますね」「更新しておきましたよ。後で確認してください」という言葉が出てくるようになりました。少しずつ、自分たちで更新していく癖がついてきたんだと思います。
また最近1人退職者が出たのですが、その方には退職する前に自分の仕事を全部Teachme Bizでマニュアルにしてもらいました。そのマニュアルがあったおかげで、後任として入ってきた人は、すぐに一人で業務を行うことができています。教育する人がいなくてもスムーズな引継ぎができたことは、大きな成果だと思っています。
年間148時間ものトレーニング時間を削減
K. Sriumporn: 私たち研修グループでは、新入社員のオンボーディングや毎年行われる全社員向けの研修において、Teachme Bizを活用しています。
以前の新入社員研修では、会社規則と組織文化についての研修に丸2日間を費やしていました。そのためトレーニングが行われる日には、私たちのチームは残業しなければ他の通常業務を終えられない状況でした。
しかしTeachme Bizがあれば、私たちはトレーニング動画をアップロードするだけで済み、各従業員はいつでも各々のペースでそれを見て学習できるようになりました。もしなにか分からないことがあったとしても、いつでもマニュアルを見直しにくることができるのです。これにより、新入社員・既存社員両方からの問い合わせが大幅に削減でき、より効率的に働けるようになったことで、トレーニングチームの時間を年間最大148時間削減することに成功しています。
入社1週間で、既存社員と同じ水準で仕事ができるように
K. Buchika: 私たち総務グループでは、Teachme Bizを活用して社内コミュニケーションを効率化し、社員からの問い合わせに対応しています。以前は、社員からの問い合わせ対応に毎日4-5時間を費やしていました。しかし今では、社員から何か質問があった際には、理解しやすいTeachme Bizのマニュアルを提供することで、各社員自身で学習することができるようになりました。その結果、今では問い合わせ対応に費やす時間はわずか1時間まで減らすことができたのです。
また以前に、私たちの部署の社員が一気に退職し、部内に数名しか社員がいなくなってしまったことがあります。その時にも、Teachme Bizが助けとなり、新入社員がTeachme Biz上のSOPにアクセスして自分たちで業務を学ぶことができました。その結果、驚くべきことに、その新入社員はわずか1週間で、部内の他のメンバーと同じ水準で働くことができるようになりました。


活用範囲をもっと広げたい
Mr. Kusumoto : 今後の活用範囲として考えているところは、大きく3つあります。
1つ目は現在のメインユーザーである人事総務部から他部門、全社への展開です。すでに経理やITの一部の部門では活用し始めていて、来期を目処に本格的な導入を進めています。それと同時に、各事業部門でも同じように定型化されたマニュアルや手順がありますので、事業部門であるソフト開発を管理するチームや電子部品の事業にも長い目線で展開をしていきたいと思っています。
2つ目に、レクチャー形式の研修の動画教材化です。当社では、毎年行わなければいけない教育があるのですが、これは講師がワンウェイで話をする講義形式なので、これを動画コンテンツに落とし込みたいと思っています。そうすることによって、トレーニングを行う側の負荷、工数を削減できるだけでなく、見たい人がいつでも見られるような環境を作りたいと考えています。
最後に、この作成した教材の他国拠点での活用です。Teachme Bizは国を選ばずアクセスすることができるので、英語で教材を作成し、それをタイだけでなく、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、インドにも展開し、ASEANのすべてのメンバーが同じトレーニングを受けられるようにしたいと考えています。
再現性を担保する仕組み
Mr. Kusumoto : Teachme Bizの導入効果として、マニュアル作成や研修の工数削減という効果はもちろんあると思いますが、私としてはそこにはあまり重きを置いていません。それよりも、誰がやっても同じクオリティになるというところが重要だと思っています。この人がやるとこのアウトプット、別の人がやると違うアウトプットになるということを回避したい。やはり、再現性を担保する仕組み作りができるというのが今、私が考えるTeachme Bizの当社での存在意義だと思います。
部の仲間には以前からずっと、次の当たり前、即ち「Next当たり前」を創るよう話をしています。Teachme Bizをつかうこともその「Next当たり前」になり、条件反射的に「もうTeachme Bizでやっておきましたから」と言ってくれるようになると嬉しいですね。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/toyota-tsusho-nexty-electronics/ (事例動画あり)
赴任してみて驚いた海外拠点のマニュアル実態
Mr.Nakayama:江戸幕末の造船所に端を発する当社は、航空・宇宙、エネルギープラント、橋梁といったインフラシステムのほか、機械事業、物流事業など幅広く業務を手掛けています。このうちIHI ASIA PACIFICでは、自動倉庫や立体駐車場、ファクトリーソリューションなどの各事業を展開しています。
創業170年という長い歴史を持つ企業ですから、社内ルールやマニュアルといった類いのものはバッチリと整備されているという印象を持たれますが、こと海外拠点においては、実態はそうではありませんでした。私自身、赴任してみて驚きを覚えました。
日本国内では、どこに行けば何があるかということは全社員がしっかりと認識しているのですが、少なくともタイではこれが追いついていません。このことが業務の遂行や引き継ぎ、社員教育に少なからず影響を与えていました。ルール集やマニュアルの整備が喫緊の課題として浮上していたはずなのですが、しっかりとした対策が講じられてきませんでした。

Mr. Katsumi Nakayama , Managing Director
存在するものとしないものを検索機能で把握
Mr.Nakayama:Teachme Bizを導入する以前も、ルール集やマニュアルが全く存在しなかったということではありません。それぞれの担当者は、自身の業務としてこれら資料の作成を必要に応じて行ってきました。ただ、各人がWordで作成し、各々のパソコン上のフォルダーで保管していたため、ファイルがどこにあるのか分からない、仮に見つけられたとしても、それが最新版なのかどうかも分からないという状態でした。
また、Wordを活用すると言っても、文章の入力はもとより写真の貼り付けや、見出しを立てる、見やすくするために着色するといったことも全てが手作業なため、パソコンをよく利用する人であっても労力を要し、とても時間がかかっていました。キャプチャー画面の取り込みにも、別のアプリケーションを立ち上げてファイルを加工しなければならないなど大変な作業でした。
早急にこの課題に対応しなくてはならないと考えていた中でTeachme Bizの存在を知り、すぐに導入を決めました。まさに、探し求めていたシステムでした。

属人性を排すことが海外では大切
Mr.Nakayama:Teachme Bizは現在、大きく二つの場面で活躍しています。まず一つ目は作業現場における業務のマニュアル化です。タイ法人の主要な事業である自動倉庫、立体駐車場、ファクトリーソリューション。いずれの業務についても長年培ってきたノウハウや知見、技術といったものがあります。これを確実に次の世代に引き継ぐことが会社として重要になってきます。
こうした伝統の技を、属人的に一握りの社員が独占しているようではいけません。その社員が退職してしまったとしても、安心して引き継ぎが行われるようなそんなマニュアルが必要です。Teachme Bizはその点、とても分かりやすくできていますので、誰もがこれに目を通せば業務を継続していくことが可能です。属人性を可能な限り排し、技術を伝承していくことが、特に海外においてはとても重要となってきます。
もう一つがバックオフィス関連のさまざまなルール集やマニュアルの作成です。例えば、新入社員向けのオリエンテーション資料や各種諸手続のためのルール集。それから業務に使用する各種ソフトウエアの操作マニュアルの作成にもTeachme Bizを活用しています。

ビデオマニュアルでトレーニングの負荷を軽減
K.Duke:新入社員が入社する度に、安全講習を行う必要があります。Teachme Bizに出会う以前は、2人のトレーナーが参加する3時間にも及ぶ研修を行っており、時間も工数もかかっていました。Teachme Bizを導入してからは、動画トレーニング教材をプラットフォームにアップロードするだけで済むので、大幅に時間を削減できています。これによって生まれた余剰時間を、他のタスクの管理に向けることができます。
国籍を問わず、すべての社員が業務プロセスを理解できるように
K.Nita:人事・総務部門においては、外国人社員の入社時や、その他さまざまな活動の管理・サポートを行っています。外国人社員の入社手続きの際にはビザや労働許可証の申請・取得が必要になりますが、その書類は複雑なうえに、英語で入手できないものもあります。このようなシーンで、Teachme Bizのマニュアルが役に立っています。
必要書類のサンプルをアップロードし、テキストや記号を追加して手順を示すだけで、簡単にビジュアルベースのマニュアルが完成します。これを活用することで社員は各自で簡単に書類作成できるようになり、結果的に社内における問い合わせが減り、その対応工数が大幅に削減されました。
またメールでマニュアルを簡単に配信できるため、社員が自主的に書類作成の流れを理解し、必要な事務処理を一人で完結できるようになりました。

(Left) K. Chalee Chalayon (Duke), Safety Officer
(Right) K. Tanyatorn Wasookoonsirirax (Nita), HR & Admin
業務の大幅改善と会社組織の再構築を期待
Mr.Nakayama:IHI Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd.は日系企業のタイ法人ではありますが、れっきとしたタイ企業でもあります。現在は、赴任した親会社の日本人が日本での長年のノウハウを伝え、業務指導を行っていますが、いずれはタイ人マネージャーによる指導体制に切り替えなくてはなりません。そうなることが会社の成長としてもとても大切です。
その障壁の一つとなっているのが、人材の流動性です。キャリアアップのために転職を繰り返すことはタイではよくあることで、そのこと自体を否定するものではありませんが、会社としてはせっかく育てた中堅以上の幹部候補の人材を失うこととなります。
この連鎖を断ち切るために必要とされてきたのが、先にも触れたルール集やマニュアルの存在でした。わずかながらもWordを駆使してマニュアル作りを続けては来ましたが、効果が薄かったのは始めにご説明したとおりです。それを一気に解決に導いてくれたのがTeachme Bizでした。業務の大幅な改善と会社組織の再構築が図られるものと期待しています。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/ihi-asia-pacific-2/ (事例動画あり)
業務プロセスが整っていなかった現場
Mr. Yamaguchi:弊社のタイ・チョンブリ工場では、プラスチックやタイヤの生成機械(カレンダーロール)、設備のメンテナンスサービスを主に提供しています。ここでは日本人とタイのナショナルスタッフ15人ほどが勤務していますが、以前より、業務の流れや手順が整っていないことや、情報の共有に課題を感じていました。解決策を模索している中、「Teachme Biz」を知り、業務プロセスの整備や知識の共有をするプラットフォームとして活用できるのではないかと考えました。

Mr. Takahiro Yamaguchi , Genereal Manager
「Teachme Biz」で写真や動画を使った伝わるマニュアルに
Mr. Yamaguchi:Teachme Biz導入前はあまりマニュアルが整備されておらず、あったとしても日本から持ち込まれた日本語のものがメインで、一部が英語やタイ語に翻訳されている程度でした。そのためマニュアルは使われなくなり、トレーニングも口頭で行われることがほとんどで、結果として、工場内では業務の手順やプロセスに関する問題が日常的に発生していました。「Teachme Biz」を導入してからは、写真や動画の視覚的な要素を入れた手順を可視化することで作業内容をより詳細に伝えることができます。
定例会の実施で活用を推進
Mr. Yamaguchi:ナショナルスタッフは最初、新しいツールにおっくうになっている様子もありましたが、その使いやすさからすぐに慣れていきました。今では月に1回、「Teachme Biz」定例会というものをナショナルスタッフがメインとなって実施しており、作成したマニュアルが現場に浸透するためにどのような工夫をしたか、今後どのように活用していくかという話し合いをしています。このような議論ができるようになったことは「Teachme Biz」の利用そのものが、社内文化として醸成してきた証です。
マニュアル作成により個人の力量向上
Mr. Yamaguchi:導入1年目はマニュアル作成に注力しました。スタッフ個人の業績評価の目標にまで据えて、1人あたり最低でも10件以上作成していましたので、今は全社で300以上のマニュアルがあります。
私たちは主にこれまで可視化できていなかったテクニカルなメンテナンスの要領などを「Teachme Biz」に落とし込んでいますが、この作成のためには作業の内容やノウハウをあらかじめ理解していることが不可欠です。そのため、マニュアル作成自体が個人の業務の理解度や、力量の向上にもつながると考えています。

作業ミス削減のために、Teachme Bizのマニュアルを活用
K. Bird:トレーニングは、まずOJTからスタートします。その後、社員が一人で業務を行う際になにか作業手順について不明な点があれば、いつでもTeachme Bizのマニュアルを参照することができます。この仕組みにより、職位に関係なくすべてのスタッフが常に高い水準で業務を行えるようになり、手順忘れの問題を解消し、現場でのミスを最小限に抑えることができます。
K. Kong:以前は新入社員の教育の際、自分たちでも業務手順に戸惑ってしまうこともありましたが、Teachme Bizを使い始めてからは、それがとても楽になりました。現場で作業する時にも、オンラインで簡単にアクセスできるため、すぐにマニュアルを参照することができます。 また、マニュアルの作成もかなり効率的にできるようになったと感じています。以前はExcelを使ってマニュアルを作成していたのですが、Teachme Bizに切り替えたことで、マニュアル作成が簡単になり、大幅にスピードアップしました。今では以前の半分の時間で、マニュアルが作成できています。

(Left) K. Songklod Jittangtrong (Bird), Supervisor
(Right) K. Nakarin Thiangpa (Kong), Supervisor
「Teachme Biz」を通じて、タイに正しい作業要領を残したい
Mr. Yamaguchi:まだまだ整備しなければならない作業手順や、社内外のプロセスを回すうえで必要な作業要領、マニュアルもありますので、今後も継続して新規のマニュアル作成を進めていきます。その次のステップとして、作成したマニュアルの定期的なブラッシュアップ、改訂をかけて見直していき、最新の正しいマニュアルが整備されている状態を維持していきたいです。
また、日本から技術支援者がタイに来て、OJTトレーニングをすることもあります。今後はこの貴重な機会もその場限りのトレーニングで終わらせることなく、そこで得たノウハウや知識などをしっかり「Teachme Biz」に残し、会社の資産にしていきたいと考えています。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/ihi-asia-pacific-1/ (事例動画あり)
日本のスーパーマーケットチェーン最大手であるイオングループが総合スーパーを皮切りとして、2020年以降マックスバリューをはじめとする小型スーパー16店舗をベトナムに出店させました。大型ショッピングセンターで知られる同社ですが、伝統的な市場であるウェットマーケットが主流であるベトナムにおいては小型の食品スーパーを多数開業しブランド認知を向上させる戦略で、2025年までに100店の出店をめざしておられます。
プロジェクトリーダーとして現地へ赴任し起ち上げから携わられてきたイオンベトナム スーパーマーケットプロジェクト ゼネラルマネージャー 奥 盛宏 様に、Teachme Bizを導入するに至った経緯や活用方法、またどのような効果を感じていらっしゃるか、今後の計画についてお話を伺いました。

イオンベトナム スーパーマーケットプロジェクト ゼネラルマネージャー 奥 盛宏 様
チェーンストア方式を採用した多店舗経営のカギを握るマニュアル
―――導入の背景を教えてください。
スーパーマーケットがASEAN全体でまだまだ浸透しておらず、ウェットマーケットが主流の生活スタイルですから、まずはマックスバリュの存在を知っていただき、身近なところで多店舗展開することをめざしていきました。ベトナムでは物流センターや問屋を利用することができない中で、どう商品を調達し、受け渡しするかを標準化するのが課題でした。また、笑顔でのお出迎えや挨拶、サポートといった接客業におけるサービス精神や顧客満足という概念もほとんどありません。日本での働き方や当社が培ってきた文化に対する理解が得られない場所で、異なる価値観を持つメンバーが集まってスタートすることになったため、人材教育という面で最も苦労したと言えるのではないでしょうか。
―――マニュアルシステムを導入した背景を教えてください。
多店舗経営はチェーンストア方式を採用してはじめて利益が生まれるビジネスモデルなので、将来的に100店舗という規模でのチェーンストア化を見据えると、作業を標準化するためにマニュアルは欠かせないと考えました。そこで日本法人に生鮮部門のものを提供してもらったのですが、紙ベースにして300ページにもおよぶため、ベトナム語で作り直すとなると不可能なことのように感じました。例えば、マテリアルハンドリングで使用する道具は見たことのないようなものばかりで、とてもではないですが現地スタッフにはそのマニュアルを理解できず、他の方法がないかと模索し始めたわけです。

画像や動画を用いることで言語の壁を乗り越えて意思を疎通する
―――導入の決め手はどんなところでしたか?
一時帰国の際にグループ企業を訪問してヒアリングしたところ、マニュアルツールとして名前が挙がったのがTeachme Bizでした。テンプレートに沿って文字だけでなくイラストや画像、動画を入れるだけで手軽に作成・更新できます。手順を1つずつ表示する「ステップ構造」で細かい動きまでビジュアルでわかりやすく表現され、共有するのも簡単です。実際に見てみると、言語の壁を越えて思いが通じるツールで「これしかない」と直感しました。日本の企業が運営するサービスという面で多少の不安はありましたが、運営会社であるスタディスト様はタイにも子会社があり、英語とベトナム語でのサポートにも対応していただけるということで導入を決めました。
―――具体的な活用方法について教えてください。
ベトナムではサプライヤー様からの供給状況に応じて売場を変更しなければならない場面が多々あります。まずはオペレーションを標準化したいという大きな目標のもと、店舗での作業を洗い出すところから着手し、マニュアルとひもづけることを最優先に進めていきました。以前はパソコンで送った陳列指示書を見て変えていたのですが、閲覧できるQRコードを印刷して棚前に貼り付けるようにしました。そうすればスマホやタブレットなどのデジタル端末からQRコードを介して、直接アクセスすることができます。スタッフがいつでも確認できるようにするためには、店舗で使っているワークスケジュールとひもづけすることが、第1段階のゴールではないかと考えています。マニュアルの数が増えれば、必要なマニュアルにたどり着くことさえ負担に感じてしまうこともあるので、重要なものだけをQRコードで出力し、その場所に貼り出しておくことを徹底していきたいです。

言語が通じない環境下でも指示内容が伝わりやすいよう具体化
―――導入の効果はどのようにお感じでしょうか。
本プロジェクトチームにおけるTeachme Bizの役割は言語を越えて指示を伝える、理解するためのツールだと考えています。結局のところ、私たちのめざしたいところやスタッフの教育すべきところを言葉ではなくビジュアルで伝えるのが理解度も1番高いです。動画を通じて伝えたいことを視覚的に表現することができるという点で紙ベースのマニュアルとは大きく異なり、指示内容を具体的に示すというコミュニケーションの場面において最も苦労するポイントを解決してくれました。また、「プロフェッショナルサービス」(※)を利用したことで自分たちだけでは気がつかないような活用方法について、たくさんのヒントをいただけて非常に大きなメリットになったと思っています。
※プロフェッショナルサービス:Teachme Bizをより効果的にご利用いただけるようスタディストの担当者が伴走支援いたします。詳細はお問い合わせください。
―――今後はどのような活用の計画をお考えですか。
言語がうまく話せない、コミュニケーションできないといった問題を抱えながら、海外で働かなければならない人にとっては特に“神ツール”だと感じています。現在(2023年7月)、作成したマニュアル数は店舗の作業で約200、事務所の作業で約100です。マニュアルを「わかりやすい」と評価してもらえることが、作り手にとっては大きなモチベーションになっています。自分が作成したものを誰かが見て、影響を与えることに楽しさややりがいを感じてほしいですね。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/aeonvietnam/ (事例動画あり)
日本最大手のグループウェアの一つ「desknet’s NEO」のASEAN市場開拓
―— タイを中心とした事業概要を教えてください。
Mr. Watanabe : 弊社は、日本本社が開発・提供している「desknet’s NEO」のASEANにおける販売・サポートを行っております。「desknet’s NEO」は、1999年にサービス提供を開始したグループウェアで、同分野では最古参の1つという位置付けです。誕生から20年以上、日本国内でビジネスを展開し、多くのシェアを獲得してきましたが、国内市場の縮小や欧米の競合他社の新規参入といった流れもあり、5年ほど前から経営戦略の一つとしてアジアの市場開拓・販路拡大に向けた取り組みを始めていました。そして2019年12月、マレーシアにASEAN初の拠点を設け、2021年2月にタイ法人を設立し、本格的にASEAN市場へ展開しています。
「desknet’s NEO」は、企業やグループ内での情報をシェアしたりコミュニケーションを図ることが基本になるのですが、ASEAN諸国では情報をシェアしたりコミュニケーションを図るビジネスツールとして、「紙」「スプレッドシート」「LINE」「e-mail」が主流でありこれらのツールが抱える様々な非効率業務を無くしたいと言うニーズが確認でき、我々の製品がアジア市場において需要があるのではと感じ、進出を決めました。

Mr. Tatsuya Watanabe, Managing Director
社内外をケアできる「使いやすさ」と「分かりやすさ」
―— Teachme Bizを導入した背景とは?
Mr. Watanabe : 前述した通り、我々の役割は「desknet’s NEO」の販売および導入後のサポートなのですが、本サービスはサブスクリプション型のビジネスモデルのため、新規のお客さまを獲得し、その方々に長くお使いいただくことで売り上げは自然と右肩上がりに伸びていきます。そのため新規獲得と同時に、一度ご契約いただいたお客さまにいかに継続していただけるかがビジネスモデルとして大きな肝になります。
ただ、当時は立ち上げたばかりということもあり、人的な手厚いサービスを提供することは難しいとは理解していました。マンパワーで補うのではなく、システム的にカバーできるツールを探しているなかで知人に紹介されたのがTeachme Biz であり、スタディスト タイランドさんにサービスの詳細を伺い、導入を即決しました。
―— 導入にあたり、不安を感じていた点はありましたか?
Mr. Watanabe : この手のツールを導入する際に「ローカルスタッフが使いこなせるか」「ローカルスタッフに浸透させられるか」という点は、弊社を含め日系企業の多くが感じることだと思うのですが、デモンストレーションを拝見した時に、Teachme Biz は直感的に簡単にマニュアル作成を進められると感じられたので、特に不安に感じる点はありませんでした。加えて、作成したマニュアルを弊社のお客さまが簡単に理解し、使用できるかという社外に向けた使いやすさも重要なポイントでしたが、Teachme Biz はその点もクリアしており、双方へのケアが実現できることが導入の決め手となりました。
K.Yhok: 弊社ではITソリューションのプラットフォーム「desknet’s NEO」を提供しており、その操作方法に関するマニュアルをTeachme Bizで作成し、社内外で共有しています。例えば社内の営業担当者が操作方法を勉強したい時にTeachme Bizで確認したり、カスタマーサクセス担当者がお客さまにTeachme Bizのマニュアルを送ってサポートをしたりと、社内外の情報共有で活躍しています。

Sangdao Sangarunsuksan (K.Yhok), Customer Service Representative
ゲーム感覚でスタッフに浸透。3言語のマニュアル作成へ
―— Teachme Biz を社内で浸透させるために工夫した点があれば教えてください。
Mr. Watanabe : 予想通り、スタッフが使いこなすようになるまでの時間は短かったと思います。先ほど申し上げた通り、Teachme Biz は直感的に操作がしやすいツールだと感じていたため、スタッフに対しても「習うよりも慣れる」という方針で、Teachme Biz を使った簡単な社内コンテストを実施しました。自己紹介や趣味の紹介といった自由なテーマを通してスタッフが気軽にTeachme Biz に触る機会を設けたことで、より早く社内に浸透したと感じています。
―— 実際にマニュアルはどのような流れで作成したのでしょう?
Mr. Watanabe : 前提として、弊社はマレーシアにも拠点があり、また日系企業の方々のご利用もあるため日本語・タイ語・英語と3言語のマニュアルが必要でした。その素材はもともと日本本社にあったので、まず私自身が各コンテンツをTeachme Biz に落とし込み、そこからタイ語・英語へとローカルスタッフが作り替えていきました。
K.Yhok: 私はマニュアル作成を担当しているのですが、以前はPower Pointを使って1つあたり30分程度かかっていましたが、Teachme Bizを導入してdesknet’s NEOからは5~15分程でできるようになりました。マニュアルができたことで(「desknet’s NEO」の使い方に関する)質問に繰り返し対応する必要もなくなり、全体として70~80%もの工数を削減できました。さらに、出来上がったマニュアルは画像や動画があり、またStep構造であることでより分かりやすくなりましたし、アップデートも簡単にできます。
導入後の問い合わせが半分に! 顧客トレーニングにも活用
―— お客さまに対するTeachme Biz の活用方法を教えてください。
Mr. Watanabe : お客さまに「desknet’s NEO」をご契約いただいた際、管理画面にデフォルトでTeachme Biz へのリンクを埋め込むことで、誰もが簡単にアクセスできる環境をつくっています。
Teachme Biz導入前は、ご契約いただいたお客さまから「desknet’s NEO」の使用方法について月に50〜60件の問い合わせを頂いていたのですが、導入後は20〜30件と約半分になりました。他方で、「desknet’s NEO」をご契約いただいたお客さまへのトレーニングの効率化にも効果を発揮しており、従来2時間〜2時間半ほどかかっていたトレーニング時間を1時間半ほどに短縮できた点においても非常にメリットを感じています。
K.Yhok:以前はマニュアルの更新をする際、そのファイルを探すことに時間がかかり、更新を完了するまでにかなり時間がかかっていました。さらに、マニュアル更新をお客さまへ連絡する際、ファイルの添付を忘れて別途ファイルを送ることがあり、お客さまにご迷惑をおかけすることが度々ありました。Teachme Bizを導入してからは、更新も簡単にできますし、お客さまへの連絡も「マニュアルを更新したのでリフレッシュボタンを押してください」と伝えるだけで済みます。また、私たちがすぐにお問い合わせに対応ができない時にも、お客さまご自身でキーワード・タグ検索で知りたい情報を調べていただくことができます。
マニュアル作成が“顧客に対する理解度向上”にも繋がる
―— その他の変化についてはいかがでしょう?
Mr. Watanabe : お客さまに対するスタッフの意識にも変化がありました。コロナ禍ということもあり、また「desknet’s NEO」の特徴を踏まえるとお客さまとはオンラインでのやり取りが基本になるのですが、その際にスタッフ側はどうしてもお客さまの立場やサービスに対する理解が希薄になりやすいという懸念がありました。
しかし、お客さまの立場になり、お客さまがいかに使いやすいかということをイメージしながらTeachme Biz でマニュアルを作成することで、スタッフの意識が変わり、これまで以上に鮮明にお客さまを理解することができるようになったと感じています。
―— Teachme Biz の使用方法について、今後の展望をお聞かせください。
Mr. Watanabe : 現在は、主にお客さまに対するサポートに焦点を当てて使用していますが、次のステップとしては社内の業務・情報をマニュアル化し、各スタッフがスムーズに業務に取り組めるような仕組みを構築したいと考えています。今後、ビジネスを拡大するなかでスタッフの採用が増えていくことは明らかなので、それぞれがスムーズに業務を始められるよう社内マニュアルの作成にも注力していきたいと思います。
K.Yhok: 将来的に、desknet’s NEOのユーザー様向けのオンライントレーニングにTeachme Bizを活用したいと考えています。リアルタイムでトレーニングに参加できなかった方や、参加したものの内容を忘れてしまった方が、Teachme Bizで復習したり、学んだりできるようにしたいです。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/neo-thai-asia-2/ (事例動画あり)
水と風に関わるサプライチェーンをタイで確立
「TERAL THAI」は1991年に設立し、30年以上にわたり揚水や給水、消火栓に関わるポンプと産業用ファンの製造を主軸にタイで事業を展開しています。もちろん、前述した他にさまざまな種類の製品を扱っています。
そして、本社は創業1918年と日本で100年を超える業界のトップランナーとして走り続けると同時に、中国やインド、ベトナム、インドネシア、フィリピン、アラブ首長国連邦、カナダなどさまざまな国に支社を構えています。
お客さまは、建設会社や自動車メーカー、工業団地にある工場などが大部分を占めます。またタイには子会社が2つあり、製造部門と営業・アフターサービス部門に分かれています。アフターサービス部門を設けることでお客さまのニーズを理解することができ、求められる品質に応えられるよう日々改善を続けています。

日々発生する紙のマニュアル更新をTeachme Bizで効率化
前述しましたが弊社ではお客さまの声に応えるため、常に作業を改善しています。それはつまり、日々作業マニュアルのアップデートが必要になるということです。
しかし以前は紙のマニュアルを用いていたため、紙のマニュアルの更新が非効率で追いついていませんでした。また、文字が羅列されたマニュアルを読むことが苦手な人も一定数おり、文字だけで読み取ろうとすると誤った解釈をすることがあり、作業ミスに繋がるという悪循環が発生していました。
この課題を解決することが急務と考え、探したところ、Teachme Bizに出会いました。詳しい情報を調べたところ、ビジュアルベースでマニュアル作成ができることに加え、管理・共有もすぐにできるなど我々が求める機能がすべて揃っていることが分かり、導入を決めました。

デジタルプラットフォームの構築で新たなステージへ
近年の世界水準に適応するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)が欠かせません。Teachme Biz導入を機に、弊社ではDXに取り組み始めました。作業マニュアルをすべてデータ化してTeachme Bizに保存し、共有したことでそれぞれがスマートフォンから容易にアクセスできるようになったことは、DXの第1歩です。従業員がTeachme Bizに慣れていけば、将来的に想定される他のシステム導入時にもスムーズに受け入れてもらえると考えています。
私自身、初めてTeachme Bizを触った時、複雑な操作がなかったため「非常にいい」と感じました。視覚的に情報を捉えることができ、操作がシンプルで簡単。従業員からのフィードバックは予想以上に良く、教えたこと以上の利用方法を知りたがっていると報告を受けました。そして、当初持っていた利用アカウント数をあっという間に超えてしまい、現場に合わせてアカウント数を増やしました。その反響には驚きましたね。
また、以前のマニュアルでは文字だけで覚えられなかった人も、Teachme Bizに切り替えてからは作業内容の理解力が高まりましたし、これまで誤った覚え方をしていた従業員を正すチャンスだと感じました。これにより会社全体の共通認識が生まれ、サービスの標準化・向上、ひいてはお客さまの信頼獲得に繋がると考えています。
Teachme Bizで属人化を解消
弊社ではまず製造部門からTeachme Bizを使い始め、品質管理部門と組立部門へと展開しました。
製造部門では、大きく分けて自動機械と手動機械の2種類を使用しています。導入前から気になっていた点は、従業員ごとに作業スキルが異なるため製品のクオリティが不安定なことでした。特に手動機械は、ほぼ従業員のスキルに頼るなど属人化していました。スキルの高い従業員も定年になれば退職してしまいます。若い従業員にしっかりとした教育を行い、“その時”に向けて備えなければいけないですし、そのためにもTeachme Biz を現場でうまく活用していきたいと考えています。
加えて、品質管理部門においても作業の正確性が以前から気になっていました。この部門では、顧客に製品を納品する前にさまざまな数値を用いて製品のクオリティを確認しなければいけません。弊社の製品が一定のクオリティに達しているか、お客さまの求める製品として自信を持って出荷できるかを管理するための心臓部でもあります。正確な作業を実現する上でもTeachme Biz には期待しています。
「値段以上の価値があるのに、手が届きやすい」
Teachme Bizは効果的な機能をさまざまに備えているのに、ハイコストなイメージのあるデジタルプラットフォームの中で手が伸びやすい値段設定という点も魅力です。業務パフォーマンスを管理するのはもちろん、属人化を回避するなどリスク管理の面でも長期的に見て価値のある投資だと考えています。
【担当者の声】「Teachme Bizは現場を明るく、楽しくする」
Teachme Bizを導入後は、紙のマニュアルを使用していた頃に比べて、従業員同士のコミュニケーションが円滑になり、作業に対する理解が容易になりました。これまでの文字が並ぶマニュアルを敬遠する従業員も少なくなかったのですが、今では使うのが楽しくて、自らマニュアルを作るようになりました。作業に対して以前より興味を持つようになったのもTeachme Bizのおかげだと感じますし、現場の雰囲気が明るく、楽しくなるという相乗効果も生まれています。

ISOに則った運用をTeachme Bizでより容易にする
ISOの目的は製品の品質を満たすように作業手順を統一、管理することです。作業手順は紙でもデジタルでも問題ありません。
従業員の作業手順の理解を容易にするために、ISO上、紙である必要がないものは、Teachme Bizでデジタル化し、ISOに定義されている基準に従って、紙とデジタルの両方で管理する方針です。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/teralthai/ (事例動画あり)
事業に不可欠なエンジニアの人件費高騰を見据え、タイに進出
—— タイ進出の経緯をお伺いできますか?
バンコクに現地法人を開設したのは2014年です。弊社の事業にエンジニアは欠かせないのですが、当時の日本では年々その人件費が高騰していました。将来的にコストの負担が大きくなると感じ、日系企業、特に製造業が多く進出し、東南アジアの中枢であるバンコクを弊社の海外初拠点に選びました。
本社は自動車や航空機、精密機器など製造業が盛んなエリアの愛知県・名古屋市に構えていて、製造業界を中心としたお客さまに向けたスマホアプリや業務支援システムの開発、それに伴うITソリューションの提案をはじめ、ITインフラ構築といったIT事業を軸にビジネスを展開しています。
—— サービス内容は日本と同様でしょうか?
大部分は変わりませんが、日本よりもシンプルです。皆さまシステム構築やアプリ開発を求めているのかと思いきや、進出当初の依頼の多くはホームページ制作。本社のホーム ページはしっかりと整っているのに、タイ側では手をつけていない企業が予想を超えてあったことには少々驚きました。そうしたタイのニーズを掴み始めた3年目から人員を強化し、開発・制作総務と、私を含めた現在の7名体制が出来上がりました。
「手の施し用がない」と諦めていたスタッフ間の業務量の差を Teachme Biz で最適化
—— Teachme Biz 導入を決断したきっかけは?
スタッフ間の意識や業務量の差が広がっていることに不安を覚えたからです。特に、立ち上げから一緒にやってきたスタッフは自分のペースで仕事を進められるようになってはいるものの、後輩が入っても業務の引き継ぎがうまくいかず、業務量に差が生まれていました。そして、解決策を投じながらも実を結ばない日々が続き、半ば諦めかけた時に知人から紹介されたのがTeachme Biz でした。
ただ、正直に言うと説明を聞くまではあまり期待していませんでした。当時の私は、 Teachme Biz = 業務マニュアルを簡単に作るだけのサービスだと思っていたんです。過去の経験から、マニュアルは作っても誰も見ない、一切活用されないものだと記憶に刷り込まれていたため、問題解決に繋がるイメージが湧きませんでした。
けれど、説明を聞いてみたら単純な業務マニュアル作成だけでなく、スタッフの業務を可視化することで業務格差の改善にも繋がる。まさに今、自分が求めているものだとすぐに導入を決意しました。その話を聞いたのが2020年夏だったのですが、ちょうど本帰国が決まったタイミングでもあり、自分がタイにいる間に今の問題をクリアしたいという想いが重なったことも一因です。

E-STAGE CO., LTD./E-STAGE (THAILAND) CO., LTD. 志水 辰彦 様
属人的になっていた業務をマニュアル化したら…3人分の作業が2人で完結!
—— 現場ではどのようにTeachme Biz を取り入れたのでしょう
属人化され、ブラックボックスと化していた業務を何とかしなければとそれぞれの業務をすべて洗い出し、マニュアルを作るよう現場スタッフに指示を出しました。私自身はマニュアル制作に一切関わっていません。Teachme Biz を提供するStudist (Thailand)にはタイ人担当者がおり、操作方法からトレーニング研修まで行っていただいたので、タイ人同士でのやり取りが中心です。
また、導入後に不明点が出てきたらLINEですぐに問い合わせできますし、毎週金曜にはStudistオフィスで無料相談会を行うなどアフターフォローも万全。安心して任せられました。
—— タイ人スタッフに戸惑いはありませんでしたか?
第一弾として、ルーティーン業務が多い総務スタッフにマニュアル作成を依頼しました。自分の業務を説明する人とTeachme Biz を操作する人の2人1組で行ったところ、特に躓くことなく、スタッフのみで進めることができました。操作を担当したスタッフは大学を卒業したばかりの新入社員だったのですが、すぐに操作方法を覚えるなど、利用開始直後は非常にスムーズに進みました。
操作がシンプルなため現場スタッフに浸透するのが早い。これはTeachme Biz の魅力だと感じます。今はパソコンの他タブレットやスマートフォンなどデバイスが多様化していますが、Teachme Bizはそのすべてに対応していますし、ちょっとした修正ならスマホで即座に対応できる。若い世代はワードやエクセルよりも、Teachme Biz のようなツールの方が順応しやすいでしょうね。
—— 導入してまだ半年ほどですが、効果を実感する場面はありますか?
総務スタッフの業務はすべてマニュアル化できたのですが、内容を見てみると月ごとや週ごとなどのルーティーン業務が大部分を占めており、一人当たりの勤務時間と照合すると業務量が少ないことが判明しました。過去に「自分は忙しい」と新しい業務を受け入れてもらえなかった経験があるのですが、業務が可視化できたことでそういったセリフを言われても反論できるようになりました。
そうして業務全体が見えたことで、これまで3人で行ってきた作業も2人で十分対応できると分かった点は会社として大きな進歩でした。1人分の手が空いたことで、これまでに手が回らなかった業務を依頼できますし、ひいては会社の成長に繋がる。たった半年ですが、長く抱えていた悩みがクリアになったことは紛れもない効果です。また、マニュアルというそれぞれの業務を振り返る場所ができたことで、安心してタイを離れることができました。

テレワークで増える申請手続きの対応もTeachme Biz に置き換え可能
—— その他に活用している場面があれば教えてください
日本に帰任後、Teachme Biz を使用しているうちに、自分の中でストレスになっている業務がTeachme Biz のマニュアルに置換できることに気づき、試験運用しているところです。
その業務とは、社内で発生するさまざまな申請手続きの問い合わせ対応です。メールやカレンダーのアカウント発行や備品の手続きなど、こまごまとした社内申請が弊社ではフロー化されておらず、また昨年からテレワークを始めたことにより社外から社内サーバーへアクセスするための申請が新たに加わったため、その方法や申請先の問い合わせが急増したんです。弊社はまだ人数が少ないので一つひとつ処理することもできますが、大企業になればそうもいかないでしょう。
ささいなことですが、積み重なれば時間的にも精神的にも大きな負荷になり、生産性がどんどん低下してしまう。こうした悪循環を断ち切るためにも、Teachme Biz は最適だと感じました。まだ試験運用中ですが、マニュアルの保管先であるリンクを社内で共有したら、想像以上に反響がありました。
それぞれの申請マニュアルはTeachme Biz のサーバー内に「申請一覧」フォルダを作って一括しているので、各々が探しているデータを簡単に見つけられる。さらに、それぞれの申請ステップには説明と一緒に画像を添えられるので、考えなくともゴールまで辿り着くことができる。まだ試験段階ですが、社内の申請に関する問い合わせがゼロになることを期待しています。
人材育成や引き継ぎもTeachme Bizのマニュアルがあれば心強い!
—— 本社でもTeachme Biz の活躍の場は多そうですね
はい。Teachme Bizはタイ法人として導入しましたが、アカウントを分け、すでに新人教育を目的に日本でも活用しています。テレワークに起因するかもしれませんが、社会人としての基本的な応対やマナーを十分に教育できていないと感じる場面が見受けられ、挨拶の仕方や掃除、お客さまを社内へ案内する際の手順など当たり前の行動一つひとつをマニュアルに落とし込みました。
上司からしたら何度も注意したくないですし、新人からしたら何度も怒られたくないじゃないですか。そういったお互いのストレスもマニュアルがあるだけで解消できる。もちろん新入社員に限らず、外部から新しく赴任してきた人たちにも各業務を把握できるマニュアルがあるだけで、仕事のスピード感が大幅に増しますよね。
タイ法人は現在私が日本から遠隔でマネジメントしているのですが、次の駐在者が決まったらTeachme Biz で作った現地用の業務マニュアルを共有して送り出すつもりです。「これが駐在セットだよ」って。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/e-stage-thailand/ (事例動画なし)
ユーザー数450万人超のグループウェア「desknet’s NEO」がASEAN進出
——タイは海外2拠点目だと伺いました
日本本社が展開するグループウェアサービス「desknet’s NEO(desknet’s NEO)」の海外市場開拓・販路拡大として 2019年にマレーシア法人、その2年後にタイ法人「NEO THAI ASIA」が開設されました。desknet’s NEOは現在450万人を超える方々にご利用いただいており、スケジュール管理や文書確認などに加え、議事録やアンケート機能など業務効率化とコミュニケーションの円滑化を図る27のツールが特徴です。
弊社は人口減少の一途を辿る日本市場を補填するべく近年、海外展開に力を入れていますが、その第1号であるマレーシア法人の立ち上げ人として白羽の矢が立ったのが、当時本社で5年勤務し、技術者として経験を積んでいたマレーシア人のアイエマンでした。私は以前にタイ、マレーシア、シンガポールにてITビジネスの経験があり、2020年4月に日本本社に入社しASEANビジネスの立ち上げを開始しました。現在、マレーシアとタイそれぞれに営業・サポート・マーケティング・アドミンの4チームがあり、私はその全体を統轄する立場となっています。
——ASEAN のどういった点に勝機を感じたのでしょう?
ASEAN、特にタイはここ10年ほどで産業高度化・IT化が進み、近年は国としてDX(デジタルトランスフォーメーション)普及に力を入れるなど、その成長には目を見張るものがあります。以前は安い人件費で「質より量」のビジネスを展開してきた企業も少なくありませんでしたが、今は人件費の高騰に比例して「量より質」の時代が到来しています。少ない人数でも現場を動かせる優秀な人材はもとより、誰でも安定したパフォーマンスを発揮できるツールが今、求められていると感じますし、その需要にdesknet’s NEOなら応えられると思っています。
「既存ユーザーが使い続ける」フォローアップ体制の構築へ
——Teachme Biz 導入前に抱えていた課題は何だったのでしょう?
desknet’s NEOはメインとしてサブスク型の販売形態(定額制)をとっているのですが、その売上基盤になるのが「新規ユーザーの獲得」と「既存ユーザーの維持」です。特に、desknet’s NEOのような広く社内業務に関わるツールは、一度導入していただくとご利用が長期化しやすい傾向にあるため、既存ユーザーの維持はより重要な役割を担っています。マンパワーがあれば各企業に特化したサポートサービスのご提案ができますが、弊社はまだ駆け出しです。リソースの数に限りがあるので、一度作ってしまえばその後の同じような場面で何度も活用できるマニュアル作成のためのツールを探していました。

また、desknet’s NEOをご利用いただいている方々に向けたフォローアップとして、WEBサイト上にFAQを設定しているのですが、恥ずかしながら、ユーザー目線で作られているとは言えず、文字だけで分かりづらいという課題もありました。それらの課題を解決できる方法を探している際に、知人から紹介されたのがTeachme Biz でした。もともとその名前は耳にしていましたが、具体的な特徴や現場での利点などを突き詰めて考えたことはありませんでした。けれどその使用方法を説明されるやいなや、「自社にとって非常に魅力的なツールだ」とその場で契約を決めました。
——予算面の懸念はなかったのでしょうか?
新たに発生する経費に対しては常にシビアな目で検討していますし、Teachme Biz のイニシャルコストは通常だと渋っていたと思いますが(笑)、導入後のメリットが明確に見えていたので躊躇なく決断することができましたね。
ローカルスタッフが受け入れやすい「使いやすさ」「更新のしやすさ」
——導入の決め手を教えてください
自社の課題解決に直結することは前述させていただきましたが、機能として惹かれてたポイントが2つあります。まず1つは、Teachme Biz 最大の特徴でもある「操作の簡易性」です。こういった新たなツールを会社として導入する場合、特に海外では現地スタッフが理解できるかどうかが、効果的な運用に繋がります。つまり、スタッフとの溝が生まれない、使いやすいツールが最優先事項だと考えていました。その点、Teachme Biz は難しい操作が不要ですし、また社内スタッフへの使い方の説明の際にも視覚的に伝えられるため溝ができることなく浸透していくだろうと予想することができました。
そして2つ目は「更新のしやすさ」。これまでは更新が起きるたびにファイル分け・フォルダ分けをするなどバージョン管理を行ってきましたが、更新頻度が高いこともあり、最終的にファイル数が多くなって現場では混乱が生じることもしばしば。Teachme Biz に切り替えたことで、今アップロードされているデータが常に最新情報だという共通認識ができ、迷うことなく正しい情報を共有することができると感じました。「思い立った時にすぐ答えがある」という環境づくりが自ずと構築できる点も決め手の1つでした。
約3ヶ月で750点の操作マニュアルが完成!
——導入後、Teachme Biz を使って現場でどう活用したのでしょう?
導入してからまだ約3ヶ月ですが、日本語・英語・タイ語それぞれでdesknet’s NEOの操作マニュアルを延べ750前後を作成しました。仮にパワーポイントで作ったとしたら、2年はかかってしまうんじゃないかと思うくらいの量がありましたし、各スタッフが通常業務との並行作業だったにも関わらず、こんなに早く完成させるとは本当に驚きました。現場スタッフにとっても、相当使いやすいんだなと感じました。これまでは月80〜100件あったユーザーの皆さんから頂くお問い合わせに1件1件メールや電話で対応してきたのですが、Teachme Biz のマニュアルができたことで問い合わせの数が減少でき、それと同時に、対応に割かれていた時間も大幅に短縮できるのではと期待しています。
——ローカルスタッフの反響や手応えは?
マレーシア法人を率いるアイエマンによると、みんな一様に「作りやすい」「使いやすい」という声を上げていると聞きました。「レイアウトなどデザインに関わることを一切考えなくていいので、サクサクと作れることができるんです。また、マレーシア人は説明を読むことが苦手な人も少なくないので、ビジュアル重視で“情報を見せることができると”いう点も現地にマッチしていると感じます(アイエマンさん)」。
半永久的な会社の財産をTeachme Biz で積み上げる
——今後の運用プランがあれば教えてください
Teachme Biz を使い始めたことで、今まで業務マニュアルの作成時に発生していた生産性のない作業・時間を見つめ直し、会社として解決することができました。こういった作業・時間に気づいていながらも、「目の前のことで手いっぱい」「新しいツールを浸透させる余裕がない」といった理由で解決できていない方々がいらっしゃると思いますが、長期的な目で会社の成長を考えれば、Teachme Biz を現場で運用していくことが経費削減(一人当たりのマンパワー向上)や業務効率向上、共通スキルの底上げといった形として会社の財産に変化していくと感じました。業界や会社規模などに関係なく、すべての企業に当てはまるツールではないでしょうか。
弊社の次のステップとして考えているのは、機能別で分けられた既存の操作マニュアルを場面ごとに置き換え、ユーザーの皆さん目線でイメージしやすく、使いやすいものにしていくことです。この他、社内情報の共有や人材育成の場面にも活用していきたいと考えています。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/neo-thai-asia/ (事例動画なし)
タイを製造拠点に世界へ! グリスニップルのリーディングカンパニー
―— タイ法人設立から今年で10年目です
弊社はグリスニップルや油圧・潤滑・空圧配管継手、ハブボルト&ナット、自動車・特殊車両部品、建設機械部品などの製造・販売を日本で行う「三和金属工業」のタイ法人として2011年に設立し、翌年に工場を稼働させました。日本国内で事業を展開する際も、自社の貿易機能を使ってアジア、特に東南アジアへ自社製品を輸出するなどその基盤はあったのですが、現地でのさらなる顧客開拓・ニーズへの対応を目的にタイ進出を図りました。グローバルネットワークを構築するための拠点として、日本のクライアントが多く進出するタイは最適でした。
タイでは自動車や農機などに使われるグリスニップルの製造・販売を中心に据えながら、CNC旋盤・マシニングを使った金属製品の受託加工も請け負っており、現在は工場とオフィスを合わせて約50人体制で取り組んでいます。
「現場の情報を残しづらい」とTeachme Biz 導入を決意
―— Teachme Biz 導入のきっかけを教えてください
弊社では製造に力を入れており、私自身も日頃から工場に足を運んでいるのですが、作業時のトラブルや不具合といった「現場の情報を残しづらい」という悩みを数年前から抱えていました。それぞれの作業に手順書があるためそこに反映・共有していけばいいのですが、その手順書は古い体裁を踏襲しており、文字だけが並んでいるため注意点を加えても目に入らないですし、更新した後に刷り直し、配るという手間もかかる。「なんだか面倒くさい、伝わりにくい」と心にずっと引っかかりがありました。
そのような状況の中で、取引先の京都銀行さんが主催するビジネスセミナーの講師がStudist(Thailand) 代表の豆田さんでした。業務改善に関するセミナーで、セミナー内で触ったTeachme Bizの機能が自分のなかの課題にピッタリはまって「求めていたのはコレだ!」と強く感じました。写真や動画を使って、なおかつ簡単に作成できるTeachme Biz なら前述した複数の課題を一つで解決できると思い、導入を決めました。

動画や写真を添えて手順書をアップデート! 未来に活きるマニュアルへ
―— 現場ではどのように活用しているのでしょう?
一番の役割として考えているのは、文章が羅列されただけの作業手順書をTeachme Biz でマニュアル化し、視覚的な情報として分かりやすく共有していくこと。長く勤めているスタッフなら見慣れたマニュアルかもしれませんが、新しいスタッフにとっては理解するまでに時間がかかり、分かりづらいなど本来のマニュアルの意味をなしていませんでした。また「あの手順書が見たい」と思ってもどこにあるか探すのに時間がかかる場合もありました。
そういった現場の非効率な出来事を解消するために、現在一つひとつTeachme Biz を使ってマニュアル化している最中です。なかでも、優先的に反映していきたいと考えているものとしては月1回、年1回といった作業頻度が低い作業です。毎日行う作業ではないからこそ正確な作業内容や手順が曖昧になってしまい、今まではスタッフが忘れるたびに私が説明を繰り返していたのですが、Teachme Biz のマニュアルがあればそういった時間を費やさずに作業を進めることができる点は非常に魅力的だと感じます。
―— その他の場面ではいかがでしょう?
もちろん日々の業務も同様です。これまで思うようにできていなかった社内の情報共有も、Teachme Biz の場合はアップデートと同時に関係者へ情報を共有できる。タイムラグなく注意点やその場の不具合を共有できることは作業ミスを減らし、生産性向上に繋がると期待していますし、こうして手順書をTeachme Bizでマニュアル化することは、会社としての技術的な財産が蓄積されていくと捉えています。今後は新人教育にも活用していきたいですし、目の前の課題解決というメリットはもちろん、長期的な視点で見た時にTeachme Biz で作ったマニュアルがさまざまな場面で活きてくると見込んでいます。
完成度へのこだわり不要! 見やすいフォーマットで作業・共有スピード大幅アップ
―— 導入後に気づいた新たな魅力は?
「マニュアルは完璧に仕上げなくていい」と豆田さんから言われたアドバイスがきっかけで、作業スピードと同時にスタッフへの共有スピードが大幅に上がりました。これまでのイメージだと手順書や記録書といった全体に共有する資料は、文字のバランスや体裁、言葉遣いなどを完全な形になってから共有するものだという意識が染み付いていたので、その分どうしても共有するタイミングが遅くなっていました。けれど、製造時の注意点や作業手順の更新といった社内での情報共有は完成度よりもスピード感が重要ですし、Teachme Biz 導入後は100点ではなく50点でいいから「とりあえず作ってみる」という考え方に転換できました。それは「見やすい」「分かりやすい」フォーマットが設定されているTeachme Biz だからこそ。自然に体裁が整うので負担が大きく軽減されると感じます。

また、これまで作業時のトラブルや不具合など日常的に生じていた出来事を備忘録として自分のパソコンで記録していたのですが、今後はそういった簡単な記録事項もTeachme Biz で共有していきたいですね。機械や製品といったトラブル時の写真など記録として撮り貯めていたものがあるのですが活用しきれていなかったので、どんどんTeachme Biz に反映し、より質の高い製品を提供していきたいと思います。そこで記録として残しておけば、タイの作業状況を日本へ報告する際にも活用できますし、これまで定期的に日本からタイに来ていた出張者の数も減らせ、コスト削減にも繋がると考えています。
トレーニングプランを活用してスタッフのTeachme Biz 理解度を向上
―— 社内での手応えはいかがでしょう?
数字的な手応えはこれからだと思うのですが、現場のスタッフに少しずつTeachme Biz が浸透してきたとようやく感じられるようになりました。導入当初、現場のスタッフにTeachme Biz の特徴や使い方を共有したのですが、長く勤めているスタッフを筆頭に既存の手順書に慣れていたこともあり、なかなか全体に浸透できていませんでした。けれど現場にiPadを設置し、根気強く周知を図ってその場で機能を体感してもらうことで「Teachme Biz で作られた手順書って分かりやすいね」と言われる回数が増えてきました。また最近、過去に共有したマニュアルを改めて見直したら、その閲覧数が予想以上に増えていて驚きました。閲覧回数を見られる機能もTeachme Biz の特徴だと思うので、今まで可視化できていなかった各スタッフの業務への理解度も把握していけたらと思います。
―— 今後の展望をお聞かせください
スタッフへTeachme Biz より普及していくためには具体的な機能やメリットをしっかりと理解し、イメージできる体験が必要だと感じ、近々Studist(Thailand) 側が提供するTeachme Biz のトレーニングを現場スタッフに向けて予定です。私自身もまだTeachme Biz の活用方法に対して手探りな点があるため、同社側の目線で直接トレーニングしていただくことでその特徴をより深く理解できる。そういったアフターフォローがある点もありがたいと感じます。
そしてこれは次のステップですが、スタッフそれぞれがTeachme Biz を「現状の課題をクリアするためのツール」として捉え、その都度、自分たちで考えて活用できる状態まで引き上げていきたいです。それが、会社全体の成長とリンクしていくと思っています。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/sanwa-metal-thailand/ (事例動画あり)
1957年に豊田通商グループ初の海外拠点としてタイに進出し、自動車や金属、化学、食品、物流など幅広い分野を取り扱う総合商社へと発展してきた「Toyota Tsusho Thailand 」。近年はその多彩なネットワークを活かした日本ブランドの販促やマッチングビジネス、スタートアップ企業との連携など新規事業への取り組みが加速。そんな同社で、“昼寝スペース”開設やタイにおけるDX(デジタルトランスメーション)イベント開催など、既存の枠に囚われないアイディアで構想をカタチにしてきたのが同社の市原さん。日本への本帰国直前にこれまでのタイでの活動、そしてタイにおけるDX化について尋ねた。
シンガポール法人から日本、タイと3カ国の現場を経験
―— 市原さんはもともとシンガポール法人にいらっしゃったのだとか
そうなんです。弊社の中ではやや特殊ではあるのですが、最初にシンガポール法人に在籍し、その後の日本勤務を経て2015年3月にタイ赴任になりました。私自身は、既存の業務ではなく潮流に合わせた新規サービスの立ち上げを中心に担当してきました。
―— 具体的にはどのような事業に関わってきたのでしょう?
分かりやすい例として3つ挙げるならば、まず一つは日本のグルメや観光、ファッション、伝統芸能などを通した日タイ交流イベント「Toyotsu Japan Festival」です。2016年が開催初年度となり、2019年の第4回開催時には来場者10万人超え、出店企業も増加するなど年々その規模を拡大しました(2020年は新型コロナウイルスの影響により中止)。
そして、タイ航空によるバンコク— 仙台間の直行便再開に向けたタイ側の調整。2014年から運行停止となっていた同便の復活を目指し、豊田通商が運営に携わる仙台空港とタイ航空の仲介役として調整を重ね、2019年10月末に運行再開が実現しました。新型コロナウイルスの影響により現在運休していることは非常に残念なのですが、タイ法人としては引き続き双方の活性化に向けて尽力していく予定です。
また2020年4月からは、タイ法人の食料・生活本部傘下として新設された「Toyotsu L&C (Thailand)」のゼネラルマネージャーとして、これまで以上に日本ブランドの販促やビジネスマッチングに取り組んできました。その一つとして取り扱っているのが、日本No.1の品質を誇るマットレスブランド「Nishikawa Air」のセールスプロモーション。チャオプラヤー川沿いの商業施設「サイアム髙島屋」内に出店すると同時に、タイ本社に併設したショールーム、仮眠による生産性向上を目的とした従業員のための“昼寝”スペース「Nap Station」などを通し、タイの方々へのブランド訴求を行っています。今後も日本ブランドのタイ進出を後押ししていきたいと考えています。
アドミンから派生し、社内でのさまざまなオペレーションにTeachme Biz を活用
―— Teachme Biz のサービスはご存知でしたか?
タイ法人として2020年3月から業務の簡略化・効率化を図ろうとアドミン(総務・経理部)からTeachme Biz の導入が始まったと聞いていますが、私が直接的に関わりを持ったのは11月頃です。現在はアドミンから派生し、他の部署でもTeachme Biz を活用しているのですが、弊員周りでの活用例としては、部署内の輸出入、在庫管理に関するオペレーションのノウハウ蓄積、そしてNishikawa AiRの販売員の教育、PoP UP的に参加しているイベントの当日の動きなど向けにマニュアルを作成し連動させております。
また現在、弊社が投資・提供するドライバーの運転・勤怠管理システム「Flare」があるのですが、やはりオペレーションに対しての教育、ノウハウ蓄積は必要と感じており、今後Teachme Biz と連携したい分野であると思っております。

タイのDX化促進を目的に「Toyotsu DX Event」を初開催
―— 2020年にDXをテーマにしたセミナーを初開催していましたが、その経緯とは
6月に開かれる予定だった「Toyotsu Japan Festival」の中止が決まり、その代わりに何ができるかを考えていたところ、頭に浮かんだのがDXでした。コロナ禍で求められているのはお祭りではなく、デジタルを駆使した将来に繋がる仕組みづくりだと。
そうしてIT技術の活用を通じて組織やビジネスモデルを変革するDXの促進、日タイのスタートアップ及び、大企業側の連携・関係強化を目的に、同年12月に「Toyotsu DX Event」を開催しました。近年、タイで支持を高めるスタートアップ企業としてTeachme Biz を提供する「Studist(Thailand)」、スマートフォンのアプリを使ったクラウドドライバー管理サービスを提供する「Flare」、オンライン上での請求書発行や会計ソフトウエアによる業務効率化を図る「Flow Account」それぞれの視点から業務の簡略化・効率化についてお話しいただき、参加者の皆さんは熱心に耳を傾けていました。
―— タイにおけるDX化の現状について
日本同様、まだまだ普及に向けての取り組みが不可欠ですが、さまざまな外的要員を吸収しながら急成長を遂げてきたタイは、新しい技術への抵抗がない分、その浸透スピードはある意味日本より速いと言えるかもしれません。
前述したDXイベントは今年も引き続き開催することが決まっているのですが、ただ同じことをするのではなく、いかに需要を把握し、求められているサービスを提供できるかだと考えていますので、私自身も常にアップデートしていきたいと思います。
イベント案内でTeachme Biz が活躍。作業の負担が大幅に軽減!
―— 前述したイベントにもTeachme Biz を活用されたと伺いました
会場へのアクセスや事前資料、登壇者のプロフィール、事後レポートといった参加者の方々への連絡に活用しました。
特に、目に見えて効果があったのは会場へのアクセスです。通常のイベントでは3日ほど前から会場についての問い合わせが届き、当日の慌ただしい状況でも多くの問い合わせ対応に追われていたのですが、Teachme Biz で作成した案内はサイアムパラゴン外観から会場までのルートを細かく場面分けし、視覚的に分かるようにしたら問い合わせがほぼゼロになり、当日の現場作業やアテンドに集中することができた点は非常に助かりましたね。
※実際に作成したマニュアル
TOYOTSU DX Event 2020
TOYOTSU DX 2020 – Introduction of guest speaker
また、これまでは事前案内や事後レポートといった資料はメールで共有していたのですが、万が一内容に誤りがあった場合、改めて説明のメールと共にデータを送り直さなければいけない。けれどTeachme Biz はサーバー上にデータを保管しているので、小さな誤りはその場ですぐに資料をアップデートできる。さらに、メール添付できないような容量が重いデータもリンクを送るだけで共有できるので総合的な作業量が大幅に軽減されました。
Teachme Biz が、日本でも推し進められているDX化に対する一つの選択肢になるのはもちろん、他の管理アプリやシステムと連動した新たな活用方法が見出せるよう私自身も追求していきたいですし、関わる皆さまにとって最良のシナジーを生み出せるよう注力していきたいと思います。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/toyotsu-lc-thailand/ (事例動画なし)
日本で求められる人材をタイから紹介
―— 新型コロナウイルスの影響で渡航が遅れたと伺いました
もともと大学卒業後の2020年4月から、タイ国内における人材紹介やレンタルオフィス事業などを展開する「PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) 」で働く予定だったのですが、当時は感染拡大の真っ只中。渡航予定日にタイの入国ができなくなり、その影響により日本の支店に属して1年ほどリモートにて研修を行っていました。そして、晴れて今年の4月からタイでの勤務が始まりました。
―— タイではどのような業務を担当するのでしょう?
私は PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) のグループ会社であり、タイから日本に向けた人材紹介を行う「THAI NIPPON FELLOWSHIP RECRUITMENT」の新規事業部にも所属しています。ノウハウが確立されたタイ国内の人材紹介事業と比較すると、まだまだこれからの事業ではありますが、どのようにすれば皆さまに利用したいと思っていただけるサービスになるのか、模索しながらベストな方法を見つけていきたいと考えています。
※PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) の紹介記事はこちら
日本での研修期間にTeachme Biz でタイ業務の事前準備!
―— 日本での研修期間にTeachme Biz を活用していたのだとか
実際に使用したのはタイ入国前の1ヶ月ほどだったのですが、タイ法人の社内体制や就業規則、手続きの流れといった基本情報がTeachme Biz のマニュアルに落とし込まれていたので、一つひとつ自分で内容を確認することができました。また、人材紹介に関わる業務などもマニュアル化されていたので、それを見ることで日本にいながらタイで働く具体的なイメージができましたし、私が所属する新規事業部にも共通する内容があり、しっかりと心の準備ができたのはTeachme Biz のおかげだなと感じます。タイで業務が始まってからでは他に覚えるべきことがたくさんあるので、事前に基本的なポイントを頭に入れられたことは現場での業務習得のスピード向上にも繋がりますよね。
もし業務内容を失念してしまったとしても、キーワードを検索すればすぐにマニュアルが探せますし、自分だけですぐに基本に立ち返ることができる点も魅力だなと感じました。
長く勤めている人の“当たり前”をTeachme Biz でマニュアル化
―— マニュアル作成もすでに自ら行っているのでしょうか?
私自身が来タイして感じた体験をもとにマニュアルを作りました。タイでの業務が始まってすぐ、社内のプリンタの使い方が分からなかったんです。Teachme Biz でマニュアルがあるか検索したところまだ無かったので、それなら私が作ってみようと。
説明のために必要な写真を携帯で撮り、それをすぐにTeachme Biz のマニュアルに落とし込んで5分ほどで完成しました。私にとってTeachme Biz は初めて触れるツールでしたが、決められたフォーマットがあるので操作が本当に簡単で、つまづくことなく作ることができました。実は使用する前まで、どのデバイスでも見やすい反面、作る側は大変なのでは…と心配だったのですが、「作りやすいし、見やすい」 と双方にとってメリットのあるツールなのだと実感しました。
出来上がったものを上司に確認してもらった際に「気づいた点はどんどんマニュアル化していきましょう」と言ってもらえたので、今後も積極的に実戦していきたいと思います。
※小林さんが作成・公開したマニュアル例
【パーソネル/お客様向け】コロナ禍のタイ渡航に関する情報まとめ(2021年4月30日時点)
https://teachme.jp/88343/manuals/11885522/
完璧を目指さず、50%でも「まず作る」ことで新たなマインドセットを
―— 実際に現場に立って感じたことはありますか?
前述したプリンタの例もそうですが、長く勤めている方々にとって“当たり前”になって見落とされている可能性がある業務こそ、新入社員の私の視点で気づき、マニュアル化を提案できると感じました。私が疑問に思うことは、後から入社する人たちも同様に感じると思いますし、私の時点でマニュアル化しておけば、次の人が混乱したり、誰かに聞いたりということを繰り返さなくて済むなど、いいことだらけではないでしょうか。
それに、マニュアル作成にあたりStudist(Thailand) から頂いたアドバイスも私にとっては大きかったです。「完璧なマニュアルである必要はない。最初は50%の完成度でもいいからマインドセットを構築することが重要」と言っていただけたことで、マニュアル作成に対する肩の力が抜けました。完璧を目指すと時間も比例して増えてしまいがちですが、日常的に活用するTeachme Biz はそういったツールではないと思いますし、肉付けは後からいつでもできるなと。
―— 今後、Teachme Biz をどのように活用していきたいですか?
社内で日常的に登場する基本的な操作や業務などはもちろんのこと、現時点でまだ存在しておらず、私自身が現場で悩んだマニュアル作成〜公開までのステップ(誰に確認し、共有していけばいいか)という「作るまでの手順」もマニュアル化していきたいと考えています。
また今後、新たな業務にあたる際はその一つひとつのステップがTeachme Biz のマニュアル化へと繋がるとイメージできるので、現場の記録を撮影やメモしておこうと思いますし、そうすればすぐにマニュアル作成に移れる。作成スピードがさらに上がっていくのではと期待しています。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/personnel-consultant-thailand-2/ (事例動画なし)
タイ初の日系企業向け人材紹介会社として創業から27年
—— 事業概要をお聞かせください
弊社は1994年に、日系企業に向けたタイ人及び日本人の人材紹介会社としてスタートしました。当時のタイには同様のサービスがなく、現地の日系企業の方々が「スタッフを雇ってもすぐに辞めてしまう」という悩みを抱えていた背景があり、それならば私がと一念発起。その場しのぎの採用ではなく、求職者も求人側も納得できるよう、“人と人”で向き合う人材紹介をモットーに事業を続けてきました。
—— 現在は人材紹介以外の事業も展開しているのだとか
前述した人材紹介の他、グループ会社を通してタイ語・日本語・英語の翻訳、レンタルオフィス「OFFICE23」運営、通訳者・会計事務等の短期派遣業務、日本人・タイ人向けセミナーの開催、ビジネスコンサルタントを行っています。グループ全体のスタッフは約80人となり、ありがたいことに年々その規模は拡大しています。
事業拡大に伴い多様化していった業務をTeachme Biz で統一
—— Teachme Biz を導入した経緯とは?
導入を開始したのは2019年末でした。その1年ほど前にStudist(Thailand) 代表の豆田さんとお会いしており、そこでTeachme Biz というサービスを知ったのですが、当初は目の前の業務に追われていたため、すぐの導入には繋がりませんでした。
しかし、その間にスタッフの入れ替わりや社内体制が変動したこともあり、現場での実務のやり方が担当者ごとで異なるなど業務が属人化しているという問題が浮き彫りになっていきました。今後、より良いサービスの提供を目指すためにはそういった問題を一つひとつ解決していかなければいけない。それぞれの業務を統一し、かつ高いクオリティでサービスを平準化していかなければ…。そう危惧していた際にTeachme Biz が頭に浮かび、改めてそのメリットや導入コストなどの説明を受け、導入に至りました。

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER(THAILAND) CO., LTD. Managing Director 小田原 靖様
—— 新型コロナウイルス感染拡大当初に、Teachme Biz を用いたデリバリー紹介ページを作成したと伺いました
コロナの影響はさまざまな業界にダメージを与えましたが、その中でも特に店内営業停止の規制が出た飲食店の方々の苦しむ声が私のもとに届いていました。それぞれデリバリーに切り替えて営業を続けていましたが、少しでも情報発信の手伝いができればと作ったのが、47店のデリバリー情報を載せた紹介ページ「みんながヒーロー!!」です。こうした咄嗟のアイディアをすぐカタチにできたのもTeachme Biz があったからこそでした。
※飲食店デリバリー情報ページ「みんながヒーロー!!」
https://teachme.jp/88343/manuals/8316587
各部門の業務を洗い出し、Teachme Biz で業務を平準化
—— 実際に利用してみて、Teachme Biz が魅力的だと感じる点は?
やはり手軽に、かつスピーディーにマニュアル作成ができる点が一番でしょう。これまでもエクセルやパワーポイント、ワードなどで部門ごとの業務をデータとして残してはいたものの「見やすさ」を意識して作られたものではなく、せっかく時間をかけて作っても誰にも見られず眠っている状況でした。また、そういったデータは制作者の作りやすいようにできているため、第三者が少し手直ししようといじっただけでデータ内の文字がズレたり画像が消えてしまったりと扱いづらいものでした。
けれど、Teachme Biz では最初からフォーマットが設定されているので誰が操作しても等しく高い完成度を保つことができる。さらに画像や動画を簡単に挿入でき、文字が並ぶだけだと流されがちな情報も視覚的に捉えることができる。これは、業務内容の統一・平準化を目指す弊社にとって最適なサービスだと感じました。
—— 現場スタッフの反応はいかがですか?
まだ全体で活用し切れているわけではないのですが、過去に製造業勤務でマニュアル作成の手間や大変さを痛感していたスタッフはTeachme Biz のあまりの容易さに「マニュアル作成=非常に面倒な作業というマイナスな印象が消え去った」と驚いていました。

Y LINK CO.,LTD. KOKOKARA CO.,LTD. Senior manager 松本 裕美様
—— 新しいスタッフが入った際にも重要な役割を担いますね
27年の間に何度もスタッフの入れ替わりを経験しましたが、Teachme Biz 導入前は前任・後任者同士の直接的な引き継ぎが主でしたし、そのほとんどは勤務期間が重ならない場合が多く第三者を介して業務の説明を行ってきたため、人によって説明にズレが生じていました。しかし、Teachme Biz で作成したマニュアルがあれば、人を介さなくとも常に正確な業務内容を伝えることができ、新人教育にかける時間も大幅な短縮が可能です。
現在は、それぞれの部門で行ってきた業務一つひとつを各スタッフにヒアリングし、マニュアル化している最中ですが、新人スタッフが研修期間に覚えるべきことや習得すべきこともマニュアルに落とし込んでいき、業務への理解度を測る指標としても活用していきたいと思います。
人材紹介・レンタルオフィス・翻訳部門それぞれの業務をマニュアル化へ
—— 具体的には各部門でどのように活かされているのでしょう?
Teachme Biz の活用がもっとも進んでいるのは、レンタルオフィス「OFFICE23」です。こちらは日本人スタッフが常駐し、日系企業の皆さまがタイでの事業立ち上げ当初に構えるオフィスとしてご利用いただいているのですが、そこでの業務は現場の日本人担当者により業務マニュアルはひと通り完成しました。業務内容が契約書や請求書の作成、領収書の発行、契約更新の連絡などルーティーンワークが中心であることも、マニュアル化が進んだ理由でしょう。

マニュアル作成後に入社した日本人スタッフに早速、マニュアルを通して業務の流れを確認してもらったのですが、こういった手順は初めてだったにも関わらず「特に疑問が生じることなく業務内容を理解でき、またTeachme Biz の操作もシンプルで簡単だったためスムーズに適応できた」というフィードバックをもらいました。このスタッフはまだ入社して3カ月ほどですが、すでに上司と確認しながらマニュアル内容をアップデートする役割を請け負っています。また、これまで指導する側だったスタッフも「何回も教えなくて済むようになり、自分の業務に集中する時間が増えた」と喜んでいます。
今後は、初めて利用する方へ向けた案内など頻繁に問い合わせを受ける内容に関しても、マニュアル化する予定です。そしてTeachme Biz を使った体制がしっかりと整った際には、これまで現場に付きっきりだったスタッフに営業の役割も任せていきたいと考えています。マニュアルに頼る部分と、人の手で実行する部分の住み分けが明確になったこともTeachme Biz を導入して良かった点です。
BTSアソーク駅からOFFICE23の行き方
https://teachme.jp/88343/manuals/7660737/
—— 他の部門ではどうでしょう?
人材紹介はもともと勤務年数が長いスタッフが多く、それぞれの頭の中に業務内容が把握できていたことにより属人化が進んでしまっていたのですが、最近ようやく各業務内容の洗い出しが終わり、マニュアル作成の段階へ入りました。業務をどんどん「見える化」していくことで一人ひとりのパフォーマンスのバラつきを解消し、サービスの底上げを図っていきたいと考えています。そして次の段階になりますが、採用ステップの中での基本情報やスケジュールなどのお知らせといった共通業務をマニュアル化し、業務効率を上げていきたいです。
翻訳部門(タイ語・日本語・英語)ではマニュアルが完成し、現場での活用度を高めていく段階です。翻訳は案件によって表現の仕方やテイストが変わるのですが、その土台となる基本ルールや業務の流れなどはマニュアルを通してどんどん共有していきたいと思います。
Teachme Biz を社外への告知や案内、情報共有へ発展させる
—— 今後の展望をお伺いできますか?
まだまだ社内でTeachme Biz の活用に対する足並みが揃えられていないので、まずは日本人・タイ人問わずしっかりと全員が利用できる体制を構築することが最優先。現在は移行期間のため、過去のアナログなやり方とTeachme Biz が併存している状態になっていますが、しっかりと一本化できるよう現場での話し合いを増やし、会社全体の業務効率化・サービスの底上げを目指していきます。また、ゆくゆくはお知らせやご案内、サービスの利用方法など社外に向けた活用へと発展させていきたいと思います。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/personnel-consultant-thailand/ (事例動画あり)
10店舗のホテルへ“自分がいなくても”想いを共有できる仕組みを
―――事業内容を教えてください。
松田様(以下、松田) 「Kokotel Bed & Cafe(以下ココテル)」は、タイにたくさんある50~150室の小規模ホテルの運営をオーナーさんから委託していただき、お客様にサービスの提供をしています。タイ全土で11店舗を展開しており、今後新たに8店舗の展開を予定しています(2020年9月現在)。お客様に最高の体験をしていただくための宿泊サービスはもちろんのこと、質の高い食事を提供する“Bed & Cafe”としてのポジション確立を目指しています。
―――ココテルの名前の由来は?
松田 ココテルは、日本語で「ハート」を意味する「こころ」に由来しています。「We Are Friends & Family Serving Friends & Family」をコンセプトに、日本の高水準のサービスとタイ式の「微笑み」のサービスを融合させ、心温まる体験を提供することが自分たちの役割だと考えています。

ココテルのホテルの様子。スペースやデザインに特徴がある
―――Teachme Bizの第一印象は?
松田 初めて聞いた時、日本でもたくさんの企業がすでに利用されていて、その中には同業のホテルも含まれていたので、きっとうまくいくに違いないと思いました。日本の事例を紹介していただき、弊社もそろそろこのようなツールを使わないといけない時期に差し掛かっているとも感じました。スタッフにTeachme Bizの概要を説明したところ、「ホテルのプレオープニングに使える」という意見をもらい、導入を進めました。
―――Teachme Bizをどのように使っていますか?
松田 現在11店舗のホテルを運営していますが、今後もさらなる拡大を目指しているので新しいスタッフを採用することはもちろん、教育し続けていかなければなりません。そのためには、より簡単に初期研修ができる各ホテル共通の業務マニュアルが必要だと感じ、手始めにフロント、キッチン、ハウスキーピングなどの業務にTeachme Bizを適用しました。最近では、バックオフィス業務や、当初の予定にはなかった本社業務にも活用しています。営業部門をはじめ、経理・人事部門でも、手当ての申請方法やシフト変更の申請方法などに加え、社員とのコミュニケーション手段としてもTeachme Bizを有効に使えているなと実感しています。

Kokotel (Thailand) Co.,Ltd. CEO 松田 励 様
「ホテル業界の厳しい課題は、サービス水準の維持と各支店のスタッフの育成」
―――Teachme Bizに対するスタッフの反応はいかがですか?
松田 他のマニュアル作成ツールとは違ってスマートフォンで写真や動画を撮るだけで、すぐにマニュアルを作ることができるので、「とても使いやすい」という反応をもらっています。「頭を抱えて長い時間をかけて作るもの」という従来のマニュアル作成の方法やイメージ、手順が大きく変わりました。
特に厨房部門では、指先だけで写真や動画をアップロードすることができ、紙のレシピよりもはるかに簡単にレシピが作成可能になったことで、作業時間の大幅短縮に繋がりました。また、教わる側も写真と動画で簡単に作業内容を理解できるので、スタッフ間におけるレシピの認識違いを防ぐことにも役立っています。
―――今後の利用方法について。
松田 Teachme Bizを実際に使用した所感としては、単純なマニュアル作成ツールというより、会社全体の企業文化を変えるプラットフォームだと感じています。マニュアル作成で業務を標準化し、改善するというマインドをスタッフに意識づけする効果もあると手応えを感じています。また、社内向けの業務改善プラットフォームとしてTeachme Bizを活用するだけでなく、お客様とのコミュニケーションツールとして、さらに活用していきたいと考えています。
―――続いて Jojo シニアマネージャー(以下、Jojo)のインタビューです。
Teachme Bizが“ココテルらしさ”を維持する鍵に
―――Teachme Bizを導入してみての感想は?
Jojo これまでの私の経験上、ホテルの基準やマニュアルのほとんどがハードコピーでした。毎日のように大量の紙を使って打ち合わせをしてきましたが、オンラインツールであるTeachme Bizの存在を知ってからは、重たくて場所をとる紙のマニュアルを持ち歩かず、またマニュアルを保管している場所に足を運ばず、自宅でも本社でも業務マニュアルを見ることができるようになりました。
以前は接客や清掃といったサービスの提供場面で、会社の基準に則していないという問題がごくまれにありました。しかし、Teachme Bizを活用することによって、会社の基準に則しているかどうかをスタッフが現場ですぐに確認・判断ができ、ホテルごとのサービス水準におけるバラつきがなくなりました。これは、全社的な業務を標準化することができるようになったということですね。
―――複数あるホテルを物理的に管理することは難しいですもんね。
Jojo その通りです。サービスを複数展開する上で、ホテル間の連絡や移動の問題に加え、同じレベルのサービスを維持するためにはスタッフ教育を徹底することが必要です。
ココテルでは新入社員の初期研修とは別に、年に2回のスキルオンラインテストを実施しています。テストの結果が最も悪かったホテルには、復習してもらうためにTeachme Bizにあるマニュアルを送っています。これを定期的に繰り返すことでサービスやスタッフの教育水準の維持及び向上に繋げています。
―――Teachme Bizに対するスタッフの反応は?
Jojo 例えば、Teachme Bizを導入する前はスタッフが社内用の申請書などが欲しい場合、その都度本社に連絡して書類がどこにあるかを聞いたり、届けてもらったりしなければなりませんでした。ですが、Teachme Biz導入後は、書類をオンライン上に保管できるようになり、本社に連絡しなくてもそれぞれで確認・申請できるようになりました。そのおかげで、それぞれの作業時間を妨げることがなくなり、お客様への対応に時間を充てることができるようになりました。
―――現場での具体的な活用方法はいかがですか?
Jojo スタッフの反応も良好、かつTeachme Bizは作成・活用・アクセスがしやすいプラットフォームではありますが、導入初期はスタッフがちゃんと理解してシステムを使いこなせているか不安でした。そこでTeachme Bizにある、「レポートを見る」という機能でスタッフのアクションを確認することができるので活用したところ、マニュアルを確認していないスタッフがいることがわかりました。これまでの紙のマニュアルでは見えなかった点が見えたことは収穫でした。
マニュアルを確認をしていないスタッフに対して、どうにかしてマニュアルの活用を促せないかと考え、「SOP of the day」という企画に辿り着きました。既に利用していたLine Botと組み合わせて、Teachme BizのマニュアルのURLを毎日自動的にホテルのスタッフへ送る設定をしています。そうすることで習慣の中にマニュアルを確認するという行為が根づき、スタッフはそこから知識を増やし、その知識がパフォーマンス向上に繋がっています。

接客用のマニュアル。英語はもちろん、デバイスによってはタイ語にも対応している
――― トンローに新たなホテルを開業すると伺いました。
Jojo はい。現在、トンローで新しい支店の準備を進めているのですが、その中で新規採用スタッフの教育は不可欠です。そこで活用すべきはやはりTeachme Biz。これを使うことで、膨大な量のテキストを読む必要がなく、写真や動画で操作手順を覚えることができ、そうすることにより研修の流れをスムーズに進めることができます。
日常では、作業手順を覚えられないときや作業に困ったとき、すぐに操作マニュアルを確認したり、出勤前に携帯電話でその日の準備や改善すべき点を調べたりとお世話になっていますね。
エコ時代に対応する新プロジェクトをTeachme Bizで
———今後の取り組みについてお聞かせください。
Jojo 現代のニーズに応えるべく、環境に配慮しながら、お客様により良いサービスを提供できるよう新プロジェクト「Koko Loves Eco」を立ち上げました。具体的には、これまで提供してきたペットボトルの飲料水の代わりに再利用可能なガラス瓶を使用したり、いつでも給水所でガラス瓶を補充できたりするようにしました。また、これまで紙でしかなかった部屋帳をTeachme Bizによってデジタル情報に置き換えることで、更新が容易になりました。紙の使用量が削減され、お客様がホテルサイトに簡単にアクセスでき、また部屋にあるQRコードをスキャンするだけで最新情報にアクセス可能になりました。
このプロジェクトをさらに浸透させるために、Teachme Bizを使って全ての作業内容をマニュアル化しました。今後は社内だけでなく社外へ、そしてお客さまへ共有できるようTeachme Bizを展開していきたいと思います。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/kokotel-thailand/ (事例動画あり)
日本式居酒屋チェーン「しゃかりき432”」がタイに出店したのが2012年7月。現在では各種居酒屋のほか、炭火焼肉店など、マレーシアやミャンマー、タイ、日本で33店舗を展開しています。そんな店舗を支えるのは約600名のスタッフ。日本人は15名のみで、あとはほぼミャンマー人とカンボジアやラオスといった隣国のスタッフが働いています。
レシピの映像化で言語や文化のハードルも解消
―――Teachme Bizを導入した背景を教えてください。
「見切り発車」が影響して、料理のクオリティが安定しないなど、常に問題は山積み状態でした。必死に動いていたのですが、解決しようにも言語の壁はもちろん、日本とは料理や文化がまったく違うので、どこが重要なのかを説明するのも一苦労。教える側の人員も限られる中、オーダーとは別に、マンツーマンで実際の食材で作って見せる。ただ、それが人から人へ伝言ゲームのように伝わるうちに、料理のクオリティが不安定になってしまっていました。
―――導入の決め手は?
以前からその評判を耳にする機会はありましたが、実際にアプリを見た瞬間に「これだ」という直感がありました。
一番気に入ったのは機械音痴な自分でも操作しやすい、誰でも簡単に操作できるところ。どんなスタッフでも国籍に関係なく、1つの目標に向かっていけると感じました。

SHAKARIKI432 Co.,Ltd. 代表取締役代表 清水 友彦 様
Teachme Biz導入によって現地スタッフの自主性が育つ
―――どのようにマニュアルを作っていますか?
現在、レシピの数はもうすぐ300になります。マニュアル作成を担当するのは3~4名。莫大な量になるので、とても憶えられるものではありません。日々の修業でしかつかめない感覚もありますが、やっぱりマニュアルがあることによってベースができて、その上で新しいメニューが生まれることもある。現場サイドとしても、Teachme Bizを導入するべきだと考えていました。
レシピは食品ロス率が高いものや原価の高いもの、クレームに繋がりやすいものを優先して作成していくようにしました。最初でこそ戸惑いながらでしたが、今では日本人スタッフが指示しなくても、タイ人スタッフが先頭になって作成するという流れになっています。

レシピマニュアルの例
料理のクオリティの安定化により顧客クレームが80%減!
―――導入の効果はいかがでしたか?
Teachme Bizならレシピを映像化できるので、言語の壁も越えて理解が圧倒的に早くなりました。しかも、調理手順まで確認できて、料理の品質も安定。なぜその手順が必要かということから、日本の食文化まで理解し、成長してくれていっているようです。実際、店舗に設置しているアンケート用紙でも、月10件あったクレームが1~2件になりました。

外国語にも対応しているため、現地スタッフも理解しやすい
また、スタッフが調理する映像をチェックすることで、細かいところまで指導できるだけでなく、教える側にとっても気付くことが多く、逆に指導しやすくなったように感じます。
さらに、食材ロスも大幅削減できました。購入した食材はだいたい20~30%をスタッフ指導に使用してきたのですが、現在では、指導用食材は10%以下になりました。
Teachme Bizは企業の将来に可かせないツール!
―――今後の活用計画を教えてください。
Teachme Bizは、しゃかりき432”の未来を明るいものにしてくれる、特別なツールです。キッチンのマニュアル作成は第一段階をクリアしたので、次はホール、サービスのほうにも活用の幅を広げていきたい。今後は“オススメ”を売る力やお客様を楽しませる力を磨いてもらって、お客様だけでなくスタッフも楽しめるお店にしていきたいですね。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/shakariki432/ (事例動画あり)
モリトモタイランドは、グローバルとローカルをつなぐディストリビューターです。主な事業はスキンケアおよびパーソナルケア製品の輸入販売です。日本の親会社である森友通商株式会社は、1854年(安政元年)に設立され、モリトモタイランドは2009年に設立されました。現在、タイでの従業員数は42名です。
今回は、人事総務部責任者Ness様と営業部シニアセールスのBoat様にTeachme Bizの活用状況、効果、将来の活用計画についてお話を伺いました。
Teachme Bizの導入きっかけ
Ness様(以下、Ness) 当社には、標準化された具体的なマニュアルがありませんでした。新入社員の教育は、口頭やOJT、あるいはパワーポイントなどで各自が作成したノートを見せる方法で行われていました。教育内容は担当者に依存しており、定められた内容と異なる場合がありました。また、会社の成長とあわせて、会社としては、従業員が様々なことに対応できるようマルチスキルを身に着けてほしいと思っています。この課題解決と要望を実現するために、Teachme Bizを導入することに決めました。
導入前の課題
Ness 長く勤めていても、たまにしか発生しない業務を忘れることがあります。作業内容がわからず、中断してしまったり、ノートを確認する必要がありますが、どこにノートがあるか分からず探すことに時間がかかることもあります。新入社員が入社した場合でも、前任者が教える時間がなかったり、うまく引き継げないこともあり、前任者が退職すると、その人が蓄積したノウハウが失われることもあります。
しかしTeachme Bizを導入してからは、公式な手順書をすぐに見つけられるようになりました。また、新入社員が入社したら、公式な手順書をまず見せるようにしています。そうすることで実際に現場に入ってもすぐに慣れ、作業に取り組むことができるようになります。早期に作業に取り組めるようになることで、改善点や新しい取り組みなどのアイデアが生まれることもあります。また、新入社員から手順書のフィードバックをもらうことで、手順の改善にもつながるので、非常に効果的だと感じています。
Boat様(以下、Boat) 今まで働いていた他の企業の教育方法だと、口頭で教えられてあとで見返せるように自分たちでメモを取ることが多かったです。そうすると、教えられるべきことが抜けていたり、間違った理解でメモを取ることもありました。トレーニング後に手順を忘れることがあれば、指導者や上司にもう一度教えてもらったり、時間がなければ、自分で思い出して作業しなければならないこともありました。
しかし、モリトモタイランドでは、事前にTeachme Bizで作業内容を理解してから現場に入ります。手順書で理解するので、抜け漏れがなくなりました。どこでも何回でも確認できるので、失敗を避けることができます。この方法を取り入れたことで、作業内容の把握がより確実になり、生産性が向上したと感じています。

(写真左) Kattareeya Takamthiang様 (Ness), HR & General Affairs Senior Officer | (写真右) Channut Wuttichalermwat様 (Boat), Senior Sales Executive
Teachme Bizをどの部門で活用していますか
Ness 現在、総務、デザイン、マーケティング、営業、輸出入、オンライン営業のバックオフィスのメンバーはほぼ100%Teachme Bizを活用しています。1~2名しかいない部門もあるため、誰かが不在でももう一人が対応できるように、手順を共有することが重要です。たとえば経理部では、かつてはオフィス系プログラムで手順をまとめていましたが、フォーマットがバラバラで分かりづらく、更新もできていませんでした。しかし、Teachme Bizを導入したことで、プログラムの使い方、お客様への連絡方法、書類の作成方法など、全ての業務の手順をSOPで共有することができるようになりました。これにより、誰かが不在でも他のスタッフが書類作成やお客様対応ができるようになりました。輸出入部でも、海外からの請求書の確認方法、関税関連の書類の準備、FDAに提出する書類の準備方法などの手順書を作成しています。
Boat 営業部では、お客様ごとに異なるニーズに合わせた提案や対応が求められます。そのため、記憶に頼ることができず、失敗のリスクも高いという課題がありました。
そこで営業部では、お客様ごとに作業フローを作成し、共有することで、スムーズかつ正確な業務の実行を実現しています。具体的には、各お客様の連絡先や問い合わせ内容、製品の提案の流れ、契約書の取り扱い、配送の流れなどを明確にした手順書を作成しています。

SOPのサンプル
知識を世代から世代へ
Ness 我々の会社は若手もいればシニアの従業員もいます。もちろん、それぞれの得意分野が違います。シニア世代の従業員は問題解決のスキルや交渉スキルが高いものの、ITツールを使うことはあまり得意ではないことが多く、SOPの作成が進まず、若手に知識を共有することも少なかったです。しかしシニア世代でもスマホは使いこなせるので、スマホで簡単に作成できるTeachme Bizであれば問題なくSOPを作成できるようになり、現在では少しずつ知識を共有できるようになってきました。
SOPを使ってもらうためにどう促進しましたか
Ness 導入当初は不安でした。従業員だけでなく、私たちも「何を作ればいいのか分からない」という状態でした。そこで、デイリー、マンスリー、3か月ごとの作業をメモしてもらうことから始めました。全業務を洗い出した結果、何を作る必要があるか、何を作らなくてもよいかが明確になりました。現在、すべての部署のSOPが完成しました。作成が完了した後は、複合機操作のSOPのQRコードを必要な場所に貼るなど、活用を促進するための取り組みを開始しています。スキャンするだけで、使用方法が表示されるので便利です。休暇中に他の従業員に代理で作業を依頼する必要がある場合には、SOPがあれば作業内容を簡単に伝えられるため、安心して休むことができます。このように、Teachme Bizの便利さが従業員に伝わると、彼ら自身がSOPを作り出すようになります。

QRコードをスキャンしてSOPを確認
従業員の理解の確認に活用
Ness SOPは、担当者が作成した後に上長に確認してもらいます。新入社員の教育が終わった後には、新人にSOPを作成してもらい、理解度をチェックします。このシステムにより、新人が業務をどの程度理解しているかをすぐに確認できます。
将来の活用計画
Ness 現在、SOPの完成度は60%程度です。100%完成後には、各従業員にマルチスキルを持ってもらうことで個々の能力を向上させるため、ジョブローテーションを実施する予定です。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/morimoto-thailand/ (事例動画なし)
Teachme Bizがハイスピードな店舗展開のアクセルに
―――貴社の事業内容をお聞かせください。
「食から世界を幸せに」を企業理念に、タイで日本食サービスを提供するTeppenは、2019年5月時点で7店舗、年内にはさらに3店舗を展開予定。おもてなしのサービスでお客様の心を幸せに、そして健康な食でお客様の体を幸せに、アジアそして世界の未来をつくっていきたいと願っています。
―――Teachme Bizを導入した背景を教えてください。
タイで事業をスタートして6年、現場スタッフを教育するのも自ら。店舗ごとにスタッフを集め、出向き教えてチェックする。全店舗に教え終わるには時間がかかり、メニュー開発のまとまった時間をなかなか取れていませんでした。
さらに、大きな壁になったのが言葉のニュアンスの違い。導入前まではなるべく書面として残すようにしたり、日に何度もミーティングを重ねたりしていましたが、コミュニケーションの土台となる信頼関係の構築に時間がかかっていました。

TEPPEN(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director 柳本 貴生 様
―――導入の決め手は?
出会った瞬間、Teppenのこれからの展開において絶対必要な存在だと思いました。それまでは150あるレシピも紙に書いたり、Office系のソフトに写真を貼り付けたりしながら作ってきたのが、Teachme Bizなら大幅に時間短縮できます。
なにより、写真や動画ベースで工程まで作成できるので、一目瞭然。あとは褒めて育てることを意識すれば、早く信頼関係が構築できるので、Teachme Bizを見てもらえば、教育する作業が要らなくなりますよね。その分、店舗展開を加速できるので、世界進出も現実味を帯びてきました。
東南アジアの激しいマーケットの中でリアルタイムに対応
―――どのように活用していますか?
「見える化」したのは、レシピや「今日のおすすめ」、企業理念、朝のミーティング方法、手の洗い方、出社から退社まで何をするのか等、多岐にわたります。キッチンのメンバーであれば、出社したらまず包丁を研ぐ、悪くなりやすい食材をチェックする、ごはんの温度を確認するといった作業がGoogleのツールでタスク管理されています。もし分からないことがあれば、Teachme Bizで、すぐ確認できるので便利です。

Teachme Bizで実際に作成、共有されたレシピなどのマニュアル
2週間ぐらいかかっていた新レシピの適用も、今ではレシピ確定後、翌々日には店頭に並べることができます。弊社のレシピ作成は、デジタルマーケティングを駆使しています。例えば、刺身ならツマ・大葉の有り無しなど、さまざまなバージョンを撮影し、InstagramやFacebookに投稿。「いいね」やコメントの数で反応が分かるので、その中でも一番反応が良いものを採用し、Teachme Bizでレシピを即配信してお客様に提供します。そのあとは、お客様や現場の声を反映しながら微修正を繰り返し、完成形に近づけていく。レシピ変更もたった1分という手軽さなので、その即時性が私たちの“武器”になっています。
>実際のレシピマニュアル例(ビジュアルベースで完成形がきちんと伝わる)
目標の可視化によってスタッフの意欲や社長自身の考えにも変化
―――導入の効果はいかがでしたか?
なんと言っても、Teachme Bizで「見える化」するという社内文化を作れたことが、最大のメリットです。
私たちが願うのはお客様だけでなく、事業に参画する仲間の幸せでもあります。そのためには、楽しくて成長できる環境づくりが大事です。決められたポジションをずっと務めることも悪くないのですが、新しいスキルを求めて転職するなら、いろいろなポジションに異動しながら、マネージメントやリーダーシップも身につけていってほしい。例えば、マネージャーの仕事内容も公開しているので、次のステージに向けて学ぶことができます。またどうすれば評価されるのか、どうすれば給料が上がるのかをルールとして明確にすることで目標を設けやすくなり、モチベーション向上にもつながっているようです。

「見える化」がモチベーションの向上をもたらした
その影響は店舗スタッフだけでなく、私自身にも変化をもたらしました。「自分が全部やらなければ」という考えがあったため、新店舗の起ち上げから約2ヶ月間は現地を離れることができなかったのですが、今はTeachme Bizという“先生”が各ポジションにいるので、約2週間で離れて任せられるようになったのです。
「世界で最も必要とされる食のグループ」を目指して
―――今後の活用計画を教えてください。
キッチンやホールのサービスについてはもちろんのこと、総務や財務、マーケティングのやり方など、もっとさまざまなことにTeachme Bizを活用して、「誰かに頼らない経営」を確立したい。
そして、「世界で最も必要とされる食のグループ」になっていきたいですね。
■事例を共有される場合は以下のURLをご共有ください
https://biz.teachme.jp/casestudy/teppen-thailand/ (事例動画あり)